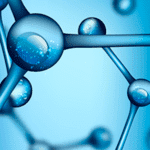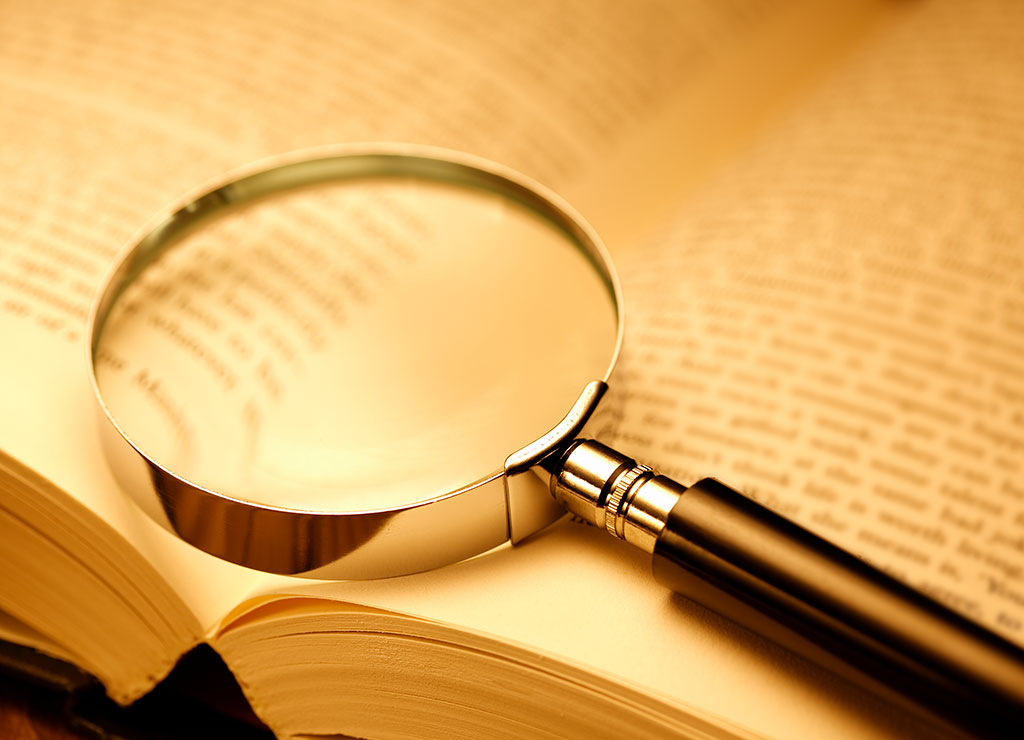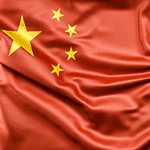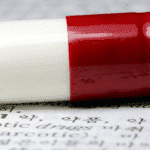| 法令の情報時期:2024年12月 統合版 | ページ作成時期:2025年07月 |
目的

本規制の目的は、防衛、災害、国家的危機等の非常時において必要となる労働力需要を的確に把握・登録し、円滑に確保・配分するための手続きを定めることである。
概要

民間の、および公的な雇用者は、労働確保法の適用時に必要な労働力を自社内で確保できない場合、労働局に需要を申請する義務がある。
労働局は申請を受理すると、職種、人数、技能、開始時期など詳細を把握する。
労働力はまず志願者で確保(任意配置)し、足りない場合に限り強制配置が行われる。強制配置にあたっては、まず非就業者を優先し、それでも不足する場合に限り就業者を配分する。
労働局は、需要の緊急性に応じて配分を決定し、公共性の高い業務(防衛、警察、民間防衛、生活必需品の供給など)を優先する。通常は労働力委員会の意見を聴く必要があるが、公共の利益のため即時決定が求められる場合は事後通知でよい。
労働局および連邦労働庁には労働力委員会が設置され、労働力の配分計画への助言や関係機関との調整を行う。
注目定義
<対象者>
■ 「雇用者」(Arbeitgeber)
| 「雇用者」とは、被雇用者を雇い入れ、労働契約に基づき労働を提供させる権限と義務を有する者をいう。 |
■ 「被雇用者」(Arbeitnehmer)
| 「被雇用者」とは、雇用者との労働契約に基づき、労働を提供し、その対価として報酬を受ける者をいう。 |
■ 「非就業者」(Nichterwerbstätige)
| 「非就業者」とは、職業に従事していない者をいう。 |
<対象施設>
■ 「労働局」(Agentur für Arbeit)
| 「労働局」とは、労働力需要の受付、把握、配分、充足を行う地域の行政機関をいう。 |
■ 「連邦労働庁」(Bundesagentur für Arbeit)
| 「連邦労働庁」とは、労働庁を統括し、必要に応じてその業務を指揮・調整する連邦レベルの機関をいう。 |
<対象製品>
■ 「需要の把握」(Bedarfsfeststellung)
| 「需要の把握」とは、必要となる労働力の種類、人数、条件などを明確にすることをいう。 |
■ 「需要申請」(Bedarfsanmeldung)
| 「需要申請」とは、労働力を必要とする事業者(公的機関を含む)が、把握した労働力需要を所管の労働庁に対して正式に届け出ることをいう。 |
■ 「任意原則」(Grundsatz der Freiwilligkeit)
| 「任意原則」とは、労働力需要の充足には、まず志願者を優先し、強制配置は必要最小限にとどめるという原則をいう。 |
■ 「労働力の配分」(Verteilung der Arbeitskräfte)
| 「労働力の配分」とは、地域や職種ごとの労働需要に応じて、労働庁が必要な労働者を割り当てることをいう。 |
■ 「労働力委員会」(Arbeitskräfteausschuss)
| 「労働力委員会」とは、労働庁や連邦労働庁の下で労働力の配分や確保計画について助言・審議を行う委員会をいう。 |
■ 「強制配置」(Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse)
| 「強制配置」とは、任意で必要な労働者を確保できない場合に、労働庁が法に基づき労働者を割り当てる措置をいう。 |
■ 「優先配置」(vorrangige Heranziehung)
| 「優先配置」とは、就業者よりもまず非就業者を配置するなど、特定の属性を持つ者を優先して労働需要に充てる措置をいう。 |
■ 「需要の緊急性」(Dringlichkeit des Bedarfs)
| 「需要の緊急性」とは、労働庁が労働力を配分する際に、必要性の切迫度や社会的重要性を考慮する基準をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

本規制には適用除外条項は設けられていないが、本規制の根拠法である「労働確保法(ASG)」の第5条「適用除外」により、下記の対象が本規制の適用除外とされている。
-
重度障害者(障害等級50%以上)
-
要介護の家族を世話している者
-
労働能力が恒久的に低下している者(50%以上)
-
連邦議会・連邦参議院等の最高憲法機関の議員
-
終身または任期付きの裁判官
-
プロテスタント(福音派)教会に属し、公認された司祭
-
カトリック教会に属し、副助祭以上の聖職者
-
他の宗派に属し、公的に専従(主業)として活動しており、その地位がプロテスタント司祭または副助祭以上のカトリック聖職者に相当する者
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
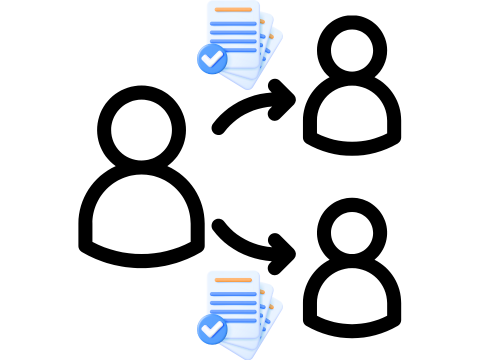
ドイツ国内で事業を行うすべての雇用者は、労働確保法適用時(戦争、テロ攻撃、暴動発生時の特別動員や、大規模な災害、パンデミック発生時の医療提供危機などの非常時)に必要な労働力を自社内で確保できない場合、所管の労働局に労働力需要を申請しなければならない。
例外的に非常時前でも、将来の需要確保が困難であると考えられる場合には申請が推奨される。
また、申請後に需要に変更が生じた場合にも、所管の労働局に届け出る必要がある。
(詳しくは第1条「需要の把握および需要申請」および第2条「管轄の労働庁」参照)
(1)労働局は、労働需要を把握する際、特に次の事項を確認しなければならない。
-
雇用者(被雇用者を雇用する権限を有する者を含む)の名称または名称・商号および所在地
-
予定される就業場所(事業所等)の名称または名称・商号および所在地
-
要求される被雇用者の人数および必要に応じて性別
-
予定される職務の種類
-
当該職務に必要とされる特別な知識および技能
-
労働契約における重要な条件(賃金、勤務時間など)
-
就業開始場所
(2) 労働確保法第3条に定める労働力確保の要件が発生している場合、労働局はさらに次の事項も確認しなければならない。
-
就業開始時期
-
予想される雇用期間
(第3条「需要の把握」)

労働局は、労働確保法第3条に基づく労働力確保の要件が発生した場合、申請された労働力需要および今後見込まれる追加需要が充足されるよう、必要なすべての措置を講じなければならない。
労働確保法に基づく強制配置は、労働需要を満たすために十分な志願者を確保できない場合、または適時に確保できない場合に限って実施される(労働確保法第1条)。
(第4条「需要の充足、任意原則」)
労働局は、労働確保法(同法第4条)の適用範囲内において、業務を適時かつ適切に実施することに支障がない限り、まず非就業者を斡旋、または必要に応じて配置しなければならない。
労働局の管轄区域内で十分な非就業者が確保できない場合は、隣接する労働局の管轄区域から、可能な限り非就業者で需要を充足するよう努めなければならない。(第5条「非就業者の優先配置」)

労働局は、非就業者で需要を満たせない場合、就業者を配分する。その際、まず労働確保法の適用外で働く者を優先し、次に適用範囲内で働く者を対象とする。
他の事業所や官庁から労働者を配置転換する場合は、業務への支障や労働者への影響が最も少ない者を選ぶよう努めなければならない。
労働局は、労働力配分を決定する際、需要の緊急性に基づいて優先順位を決める。特に、防衛、警察、民間防衛、生活必需品や医療の供給に関わる需要を最優先とする。
通常、労働局は決定前に労働力委員会の意見を聴かなければならない。ただし、公共の利益上、即時決定が必要な場合は例外で、事後に委員会へ通知すればよい。(詳しくは第6条「労働力の配分」参照)
労働局は、労働確保法第3条の要件発生後、申請者の要請に基づき需要充足の可否を決定し、結果を通知する。
拒否する場合は理由を文書で示さねばならず、申請者からの異議申立てがあれば連邦労働庁が担当部署で審査し、事前に労働力委員会の意見を聴取する。(詳しくは第7条「労働局による決定」参照)
目次
第1条 需要の把握および需要申請
第2条 管轄の労働局
第3条 需要の把握
第4条 需要の充足、任意原則
第5条 非就業者の優先配置
第6条 労働力の配分
第7条 労働局による決定
第8条 労働局における労働力委員会
第9条 連邦労働庁理事会が指定した機関における労働力委員会
第10条 労働力委員会および連邦労働庁のその他の任務
第11条 補償および実費の払い戻し
第12条 施行日
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 労働確保法に基づく労働需要の決定および適用に関する規制 (ArbSV) |
| 公布日 | 1989年05月30日 |
| 所管当局 | ドイツ連邦労働庁 |
作成者