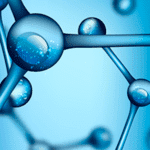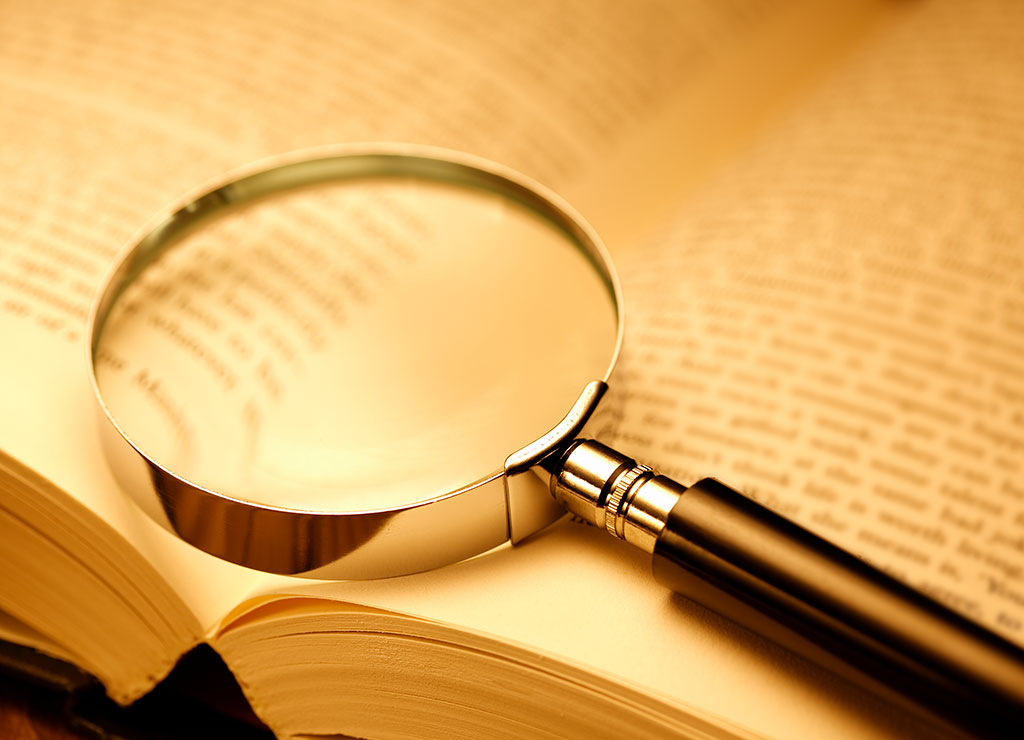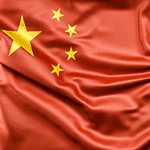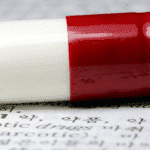人用の処方薬を同一処方箋で繰り返し交付するには処方医の指示が必要で、初回のあと最大3回まで許可できる。処方箋には再交付用である旨の表示が必要で、再交付時の包装規格は初回と同一でなければならない。動物用では、同一処方箋で処方量を超える再交付は禁止されている。(詳しくは第4条参照)
| 法令の情報時期:2025年02月 統合版 | ページ作成時期:2025年08月 |
目的

本規制の目的は、医薬品の誤用・乱用を防ぎ安全性を確保するために、医薬品のうち安全性や適正使用の観点から医師等の管理下での使用が必要なものを指定し、これらを処方箋によってのみ販売・交付できるようにすることである。
概要

本規制は、医薬品のうち処方箋による販売が義務づけられている物質および製剤を定め、その交付を医師、歯科医師または獣医師による処方に限定するものである。
第1条では要処方箋の範囲を規定しており、第2~3条では、処方箋の有効性や交付方法、第4~5条では特定の処方様式や例外規定が定められている。
附属書1には対象となる物質や製剤が列挙されている。なお、第6~9条は削除されている。
注目定義
<対象者>
■ 「医師」(Arzt / Ärztin)
| 「医師」とは、処方箋を発行する資格を有する医学的専門職としての医師をいう。 |
■ 「歯科医師」(Zahnarzt / Zahnärztin)
| 「歯科医師」とは、歯科的治療に関連する医薬品について処方箋を発行する資格を有する者をいう。 |
■ 「獣医師」(Tierarzt / Tierärztin)
| 「獣医師」とは、動物用医薬品の処方箋を発行することが許可された獣医学の専門職をいう。 |
<対象製品>
■ 「処方 / 処方箋」(Verschreibung)
| 「処方」または「処方箋」とは、医師、歯科医師または獣医師が、特定の医薬品の交付を許可する行為、またはそれを目的として発行する書面をいう。 |
■ 「処方箋医薬品」(verschreibungspflichtige Arzneimittel)
| 「処方箋医薬品」とは、第1条および附属書1に基づき、処方箋なしでは販売または交付することができない医薬品をいう。 |
■ 「要処方箋 / 処方箋義務」(Verschreibungspflicht)
| 「要処方箋」または「処方箋義務」とは、対象医薬品の販売または交付には処方箋の提示が必須であるという法的要件をいう。 |
■ 「Tーレセプト」(T-Rezept)
| 「Tーレセプト」とは、本規制の第4条に基づき、特定の高リスク医薬品に対して用いられる特別な書式の処方箋をいう。 |
■ 「テレマティック・インフラストラクチャ」(Telematikinfrastruktur)
| 「テレマティック・インフラストラクチャ」とは、ドイツの医療分野で整備されている全国統一のデジタル通信基盤であり、医師、薬局、病院、保険者などの医療関係者が安全に情報をやり取りできるネットワークをいう。 |
■ 「交付」(Abgabe)
| 「交付」とは、薬局などが処方箋に基づき、被雇用者または動物の所有者などに医薬品を渡す行為をいう。 |
■ 「ホメオパシー薬局方」(Homöopathisches Arzneibuch)
| 「ホメオパシー薬局方」とは、ドイツで公式に認められた、ホメオパシー医薬品の製造・品質管理に関する標準書をいう。一般的な薬局方のホメオパシー版であり、製剤の希釈法、原料の定義、製造工程の基準等が定められている。 |
<対象施設>
■ 「薬局」(Apotheke)
| 「薬局」とは、処方箋医薬品を販売・交付することが許可された医薬品取扱施設をいう。 |
■ 「連邦医薬品医療機器研究所(BfArM)」(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)
| 「連邦医薬品医療機器研究所(BfArM)」とは、ドイツの連邦保健省所管の連邦上級機関であり、医薬品・医療機器の承認・安全対策・リスク管理を担う中央当局をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

附属書1に記載されている物質またはそれを含む製剤であっても、ホメオパシー製法、特にホメオパシー薬局方の規定に従って製造されたもの、またはそのような物質・製剤の混合物からなる医薬品については、完成品中の最終濃度が10,000分の1(第4十進希釈、すなわちD4)を超えない場合には、処方箋義務の対象から除外される。これらの医薬品には、処方箋義務のない物質または製剤を混合することも許される。
(第5条)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

次のいずれかに該当する医薬品は、後続の規定に別段の定めがない限り、医師、歯科医師または獣医師の処方箋がある場合にのみ交付できる(処方箋医薬品)。
1. この規則の附属書1に定められた物質、またはそれを含む製剤
2. 附属書1に定められた物質、またはそれを含む製剤から構成される製剤
3. 上記1または2に掲げる物質または製剤を添加している製剤
(第1条)
有効な処方箋は、自筆署名された書面でなければならず、医師等の氏名・住所・発行日・使用目的(必要に応じて)などを含む必要がある。
電子的処方箋は、電子署名や技術要件を満たしていれば使用可能。
(詳しくは第2条参照)
第2条第3項に定める医薬品の処方箋は、原本と複写の2通を作成しなければならない。原本および複写は、製薬企業(医薬品製造販売業者)に送付するものとする。
製薬企業は、医薬品法(Arzneimittelgesetz)第47a条 第2項第1文に基づき、原本および複写に、交付した包装の連続番号および交付日を記入し、複写を妊娠葛藤法(Schwangerschaftskonfliktgesetz)第13条にいう施設に医薬品とともに送付しなければならない。
処方箋の原本は製薬企業に留め置かれ、製薬企業はこれらを年代順に整理し、5年間保管するとともに、所轄当局からの請求があれば提示しなければならない。
処方を行った者は、処方箋の複写に、医薬品の受領日および使用日、さらに匿名化された形で患者記録との対応を記載しなければならない。また、この複写を年代順に整理し、5年間保管して、所轄当局からの請求があれば閲覧に供さなければならない。(詳しくは第3条参照)

レナリドミド/ポマリドミド/サリドミドの処方は、「Tーレセプト」と表示された特別処方でなければならず、連邦医薬品医療機器研究所(BfArM)交付の公定様式、またはテレマティック・インフラストラクチャ経由の電子的形式の処方でなければならない。
医師は、最新の専門情報に基づく安全対策(必要なら妊娠予防プログラム、患者への情報提供)を遵守したことを処方上で確認し、(紙のTーレセプトでは)適応内外の別を記載する。
薬局は、処方箋の写しを毎週BfArMへ提出しなければならない。電子の場合はテレマティック・インフラストラクチャのサービスが情報を送信する。(詳しくは第3a条参照)
電子処方箋の技術的な要件として、専用の情報技術システム(テレマティック・インフラストラクチャ)を通じて管理されなければならない。(詳しくは第3b条参照)
緊急で処方薬の使用を遅らせられない場合、処方医等はまず電話などで内容を薬剤師に伝えてよい。薬剤師は処方医の身元を確認し、処方医はその後すみやかに書面または電子の処方箋を送付する義務がある。

目次
第1条
第2条
第3条
第3a条
第3b条
第4条
第5条
第6条(削除)
第7条(削除)
第8条(削除)
第9条(削除)
附属書1(第1条第1号および第5条に関連)
第1条第1号に該当する物質および製剤
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 医薬品の処方箋義務に関する規制 (AMVV) |
| 公布日 | 2005年12月21日 |
| 所管当局 | 連邦保健省 |
作成者

株式会社先読