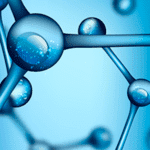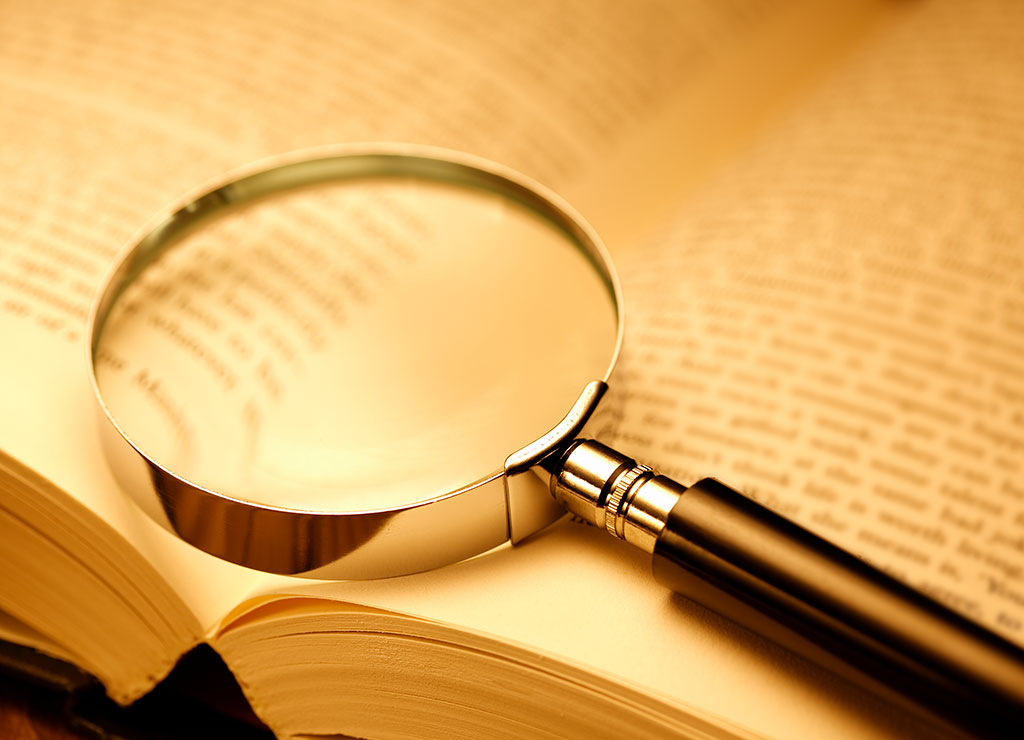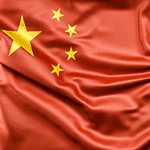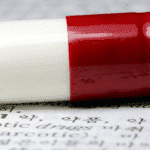| 法令の情報時期:2024年10月 統合版 | ページ作成時期:2025年07月 |
目的

ドイツ連邦共和国および排他的経済水域における労働時間の設定に際し、被雇用者の安全および健康保護を確保し、柔軟な労働時間のための枠組条件を改善すること
日曜日および国家が認めた祝日を、被雇用者にとっての休息と精神的高揚の日として保護すること
概要

平日の労働時間は原則1日8時間まで、最長でも平均8時間を超えない範囲で10時間まで延長が可能である
休憩・休息時間、夜勤・交替勤務、日曜・祝日の労働について詳細に規定されている
例外的な状況に応じた特例が設けられている
労働時間の記録や監督機関による執行、違反に対する罰則が定められている
特定の管理職、公務員、家庭内介護従事者などには本法の適用除外がある
注目定義
<対象者>
■ 「被雇用者」(Arbeitnehmer)
| 「被雇用者」とは、労働者および事務職員、ならびに職業訓練に従事している者をいう。 |
■ 「夜間労働者」(Nachtarbeitnehmer)
| 「夜間労働者」とは、以下のいずれかに該当する被雇用者をいう。 1. 勤務体制上、通常、交替制により夜間労働を行っている者 2. 暦年中に少なくとも48日間、夜間労働を行っている者 |
<対象製品>
■ 「労働時間」(Arbeitszeit)
| 「労働時間」とは、休憩時間を除いた業務の開始から終了までの時間をいう。複数の雇用者の下での労働時間は合算される。地下鉱業においては、休憩時間も労働時間に含まれる。 |
■ 「夜間」(Nachtzeit)
| 「夜間」とは、23時から6時までの時間をいう。ただし、製パン業および菓子製造業においては、22時から5時までとする。 |
■ 「夜間労働」(Nachtarbeit)
| 「夜間労働」とは、夜間のうち2時間を超える業務をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

(1)本法は、以下の者には適用されない。
1. 労働協約法 第5条 第3項に定める「管理職」および「主任医師」
2. 公的機関の長およびその代理者、ならびに人事に関する自主的判断権を有する公務員でない公的部門の被雇用者
3. 支援・保護を任された者と家庭内で同居し、自主的に教育・介護・監護する被雇用者
4. 教会および宗教団体における典礼分野
(2)18歳未満の者の雇用には、本法に代えて青少年労働保護法が適用される。
(3)商船に乗り組む乗組員の雇用には、本法に代えて海上労働法が適用される。
(第18条「本法の不適用」)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

被雇用者の平日の労働時間は、1日8時間を超えてはならない。ただし、6か月間または24週間のいずれかの期間において、1日あたりの平均労働時間が8時間を超えない限り、最大で10時間まで延長することができる。
(第3条 「被雇用者の労働時間」)
労働時間が6時間を超え9時間以下の場合は30分以上、9時間を超える場合は45分以上の休憩を、あらかじめ定められた時間に与えなければならない。この休憩時間は、それぞれ15分以上の時間区分に分割することができる。
被雇用者を6時間以上連続して、休憩なしで就労させることはできない。
(第4条「休憩時間」)
被雇用者は1日の勤務終了後に連続11時間以上の休息を取る必要がある。病院や飲食業、運輸、農業などの特定業種では最大1時間の短縮が可能だが、月内または4週間以内に他の休息を12時間以上に延長して補う必要がある。また、病院等では呼び出し待機による中断分を後で補填することも認められる。
(詳しくは第5条「休息時間」参照)
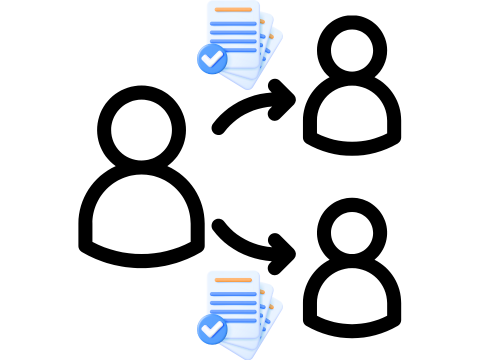
夜勤・交替勤務者の労働時間は、人間工学に基づく適切な労働設計原則に従って決定しなければならない。
夜間労働の時間は1日8時間まで。ただし、月または4週間単位で平均8時間を超えない限り、10時間まで延長可能。該当しない期間には第3条の規定が適用される。
夜間労働者には、雇用開始前およびその後3年ごと(50歳以上は1年ごと)に産業医による健康診断を受ける権利がある。費用は雇用者が負担する。
以下の場合、被雇用者の請求により日勤への配置転換を受ける権利がある。
a)健康上の理由
b)同居の12歳未満の子の世話ができない場合
c)重度介護を要する家族の世話を担う場合
ただし、業務上の重大な事情がある場合は拒否できる。
夜間労働に対する補償として、有給の代休または賃金への適正な割増支給が必要(労働協約で別途定めがある場合を除く)。
夜間労働者も、他の被雇用者と同様に、職業教育や昇進機会にアクセスできるように配慮されなければならない。
(詳しくは第6条「夜間および交替勤務」参照)
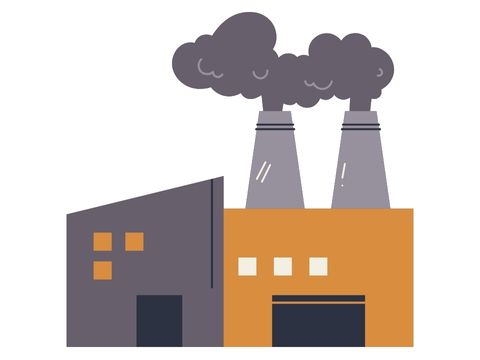
(1)被雇用者は、日曜および法定祝日において、0時から24時までの間に就労させてはならない。
(2)定常的に昼夜交替制を採用している事業所では、日曜・祝日の休業の開始または終了時刻を最大6時間まで前倒しまたは後倒しすることができる。ただし、休業開始後24時間は操業を停止していなければならない。
(3)運転手および助手(同乗者)については、24時間の休業の開始時刻を最大2時間まで前倒しすることができる。
(第9条「日曜・祝日の休業」)
救急・消防、治安維持、医療・介護、飲食・宿泊、報道・放送、交通、農業、警備、設備保守、研究活動、自然物の腐敗防止などの業種を対象とし、業務が平日に実施できない場合に限り、第9条にかかわらず被雇用者を日曜・祝日に就労させることが認められる。
また、生産ラインの停止がかえって多くの人手を要する場合や、パン・菓子製造業では当日販売分の準備のために最大3時間までの就労が許容される。さらに、EU加盟国で必ずしも祝日とされていない平日の祝日については、金融決済や取引業務のための就労も可能とされている。
(詳しくは第10条「日曜・祝日の就労」参照)
年間15日以上の日曜日は就労を禁止し、日曜・祝日に働いた場合は代替休日を与える必要がある(日曜勤務は2週間以内、祝日は8週間以内)。労働時間は他条の上限を超えてはならず、代替休日は休息時間と連続して与えることが原則である。
(詳しくは第11条「日曜・祝日勤務に対する代替休暇」参照)

雇用者は、労働時間法や関連する政令・労使協定を、従業員が確認できるよう社内に掲示または電子的に提供する義務がある。また、法定労働時間を超える労働の記録および労働時間延長に同意した従業員の一覧を作成し、少なくとも2年間保存しなければならない。
(詳しくは第16条「掲示義務および労働時間記録」参照)
本法および関連政令の遵守は、各州の法律で定められた監督当局が監督する。
監督当局は、雇用者に対して必要な措置の実施を命じることができる。
連邦の公務部門および連邦直属の公法人等における監督は、所管の連邦省庁が担当する。
監督当局は雇用者に対し、必要な情報の提供や、労働時間記録・協定文書の提出を求めることができる。
監督官は、就業時間中に事業所へ立ち入り・調査する権限を持つ。住宅を事業所とする場合には、緊急性がある場合を除き、同意が必要となる。雇用者は立入を許可しなければならない。
情報提供を求められた者は、自身または一定の親族が刑事処分や制裁の対象となるおそれがある場合には、その情報の提供を拒否することができる。
(詳しくは第17条「監督当局」参照)
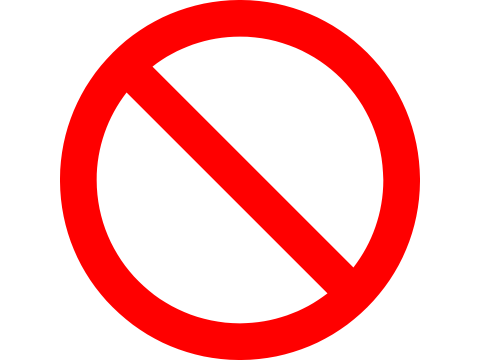
雇用者が労働時間や休憩・休息時間、日曜・祝日の就労制限、記録義務、監督当局の命令などに違反した場合、過料(行政罰)の対象となる。違反内容に応じて、最大3万ユーロの過料が科されることがある。掲示義務違反については、上限5千ユーロとされている。
(詳しくは第22条「過料規定」参照)
雇用者が労働時間や休憩・休息、日曜・祝日の就労制限などの規定に違反し、それによって従業員の健康や労働力を危険にさらした場合、または違反を繰り返した場合は、最大1年の懲役または罰金刑が科される。過失によって危険を生じさせた場合は、最大6か月の懲役または180日分の罰金が科される。
(詳しくは第23条「刑事罰規定」参照)
目次
第1章 一般規定
第1条 本法の目的
第2条 用語の定義
第2章 平日の労働時間および非労働時間
第3条 被雇用者の労働時間
第4条 休憩時間
第5条 休息時間
第6条 夜間および交替勤務
第7条 例外規定
第8条 危険業務
第3章 日曜・祝日の休業
第9条 日曜・祝日の休業
第10条 日曜・祝日の勤務
第11条 日曜・祝日勤務に対する代替休暇
第12条 例外規定
第13条 委任、命令および承認
第4章 特例措置
第14条 異常な事態
第15条 承認および委任
第5章 法律の施行
第16条 掲示義務および労働時間記録
第17条 監督当局
第6章 特別規定
第18条 本法の不適用
第19条 公務における就労
第20条 航空分野における就労
第21条 内陸水運における就労
第21a条 陸上運送における就労
第7章 刑事罰および過料に関する規定
第22条 過料規定
第23条 刑事罰規定
第8章 最終規定
第24条 国家間協定およびEU法の実施
第25条 労働協約に関する経過措置
第26条 (削除)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 労働時間法 (ArbZG) |
| 公布日 | 1994年06月06日 |
| 所管当局 | 連邦労働社会省 (BMAS) |
作成者