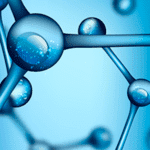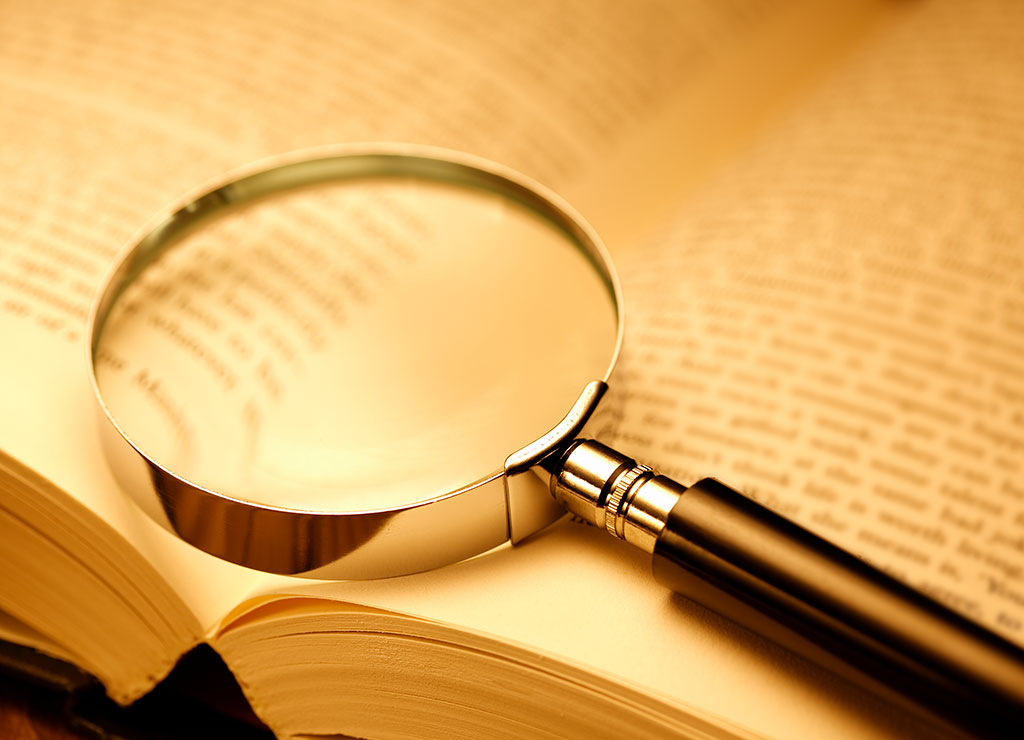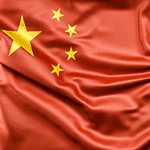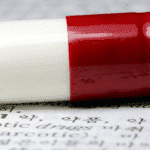| 法令の情報時期:1987年12月 統合版 (附属書2のみ2015年12月の改正に準拠) | ページ作成時期:2025年09~10月 |
目的

本法は、インドにおける工場の労働環境、安全衛生、労働時間などを規制する基本法であり、工場で働く被雇用者の健康、福祉、安全を確保し、労働基準を整備することを目的としている。
概要

本法は、インドの工場における労働者の健康・安全・福祉と労働時間を包括的に定める基本法である。
適用対象は一定規模の工場で、次のような事項について章立てで規定している。
- 設立許可と届出
- 監督官の権限
- 衛生(清潔・換気・飲料水等)
- 安全(機械防護・火災・危険物)
- 福祉(食堂・休憩所・保育室)
- 成人の労働時間・休日
- 残業割増
- 未成年者の就業制限
- 年次有給休暇
- 罰則・手続 等
有害工程や許容ばく露限界を附属書で扱い、中央政府の指示と州労働当局の監督で運用される。
近年(2013年、2015年)は附属書の更新が官報通知で行われている。
実務においては、州規則が具体的な様式・締切・掲示体裁を定めるため、操業州の工業規則に合わせる必要がある。
注目定義
<対象施設>
■ 「工場」(factory)
| 「工場」とは、構内を含む事業所で、直近12か月のいずれかの日に、動力ありで10人以上、または動力なしで20人以上が就業し、製造工程が行われているものをいう。 |
<対象者>
■ 「worker」(労働者)
| 「労働者」とは、賃金の有無、雇用者の知否、直接・間接(請負等)を問わず、製造工程に従事するか、またはその機械・敷地の清掃に従事するか、または製造工程やその対象物に付随・関連する他の作業に従事する者をいう。 |
■ 「成人」(adult)
| 「成人」とは、満18歳以上の者をいう。 |
■ 「青年」(adolescent)
| 「青年」とは、満15歳以上満18歳未満の者をいう。 |
■ 「児童」(child)
| 「児童」とは、満15歳未満の者をいう。 |
■ 「未成年者」(young person)
| 「未成年者」とは、児童または青年をいう。 |
■ 「占有者」(occupier)
| 「占有者」とは、工場の業務について最終的な支配権を有する者をいう。会社については取締役の一人、合名会社については無限責任社員の一人、政府が所有または管理する工場については政府により当該工場の業務管理のために任命された者とする。 |
■ 「監督官」(inspector)
| 「監督官」とは、州政府によって任命され、本法の運用・監視・検査を担う行政官をいう。 |
<対象製品>
■ 「製造工程」(manufacturing process)
| 「製造工程」とは、物品・物質を使用・販売・輸送・引渡し・処分目的で、製作・変更・修理・装飾・仕上げ・包装・注油・洗浄・清掃・破砕・解体等で取り扱い・適合させる工程をいう。 |
■ 「有害工程」(hazardous process)
| 「有害工程」とは、附属書1に掲げる産業に関連する工程または活動であって、当該工程または活動における原料・中間製品・最終製品、または副産物・廃棄物等が、特段の注意を払わない限り、労働者の健康に実質的な障害を引き起こすか、または環境汚染の危険を発生させるおそれのあるものをいう。 |
■ 「暦年」(calendar year)
| 「暦年」とは、いずれの年においても1月1日に始まる12か月の期間をいう。 |
■ 「日」(day)
| 「日」とは、午前零時に始まる24時間の期間をいう。 |
■ 「週」(week)
| 「週」とは、規則で別段に定めがない限り、土曜日の夜の午前零時に始まる7日の期間、または主任監督官の承認した他のいずれかの曜日の午前零時に始まる7日の期間をいう。 |
■ 「動力」(power)
| 「動力」とは、電気エネルギー、または機械的に伝達されるその他の形態のエネルギーであって、人力または畜力によって生成されないものをいう。 |
■ 「原動機」(prime mover)
| 「原動機」とは、動力を発生するか、またはその他の方法で動力を供給するあらゆる機関・モーターまたは装置をいう。 |
■ 「伝導装置」(transmission machinery)
| 「伝導装置」とは、原動機の運動が機械または器具に伝達されるか、または当該機械もしくは器具がそれを受けるために用いられる、軸、車輪、ドラム(巻胴)、滑車、滑車装置、カップリング、クラッチ、伝動ベルト、その他の器具または装置をいう。 |
■ 「機械」(machinery)
| 「機械」とは、原動機、伝導装置、ならびに動力が発生・変換・伝達・適用される他のあらゆる装置をいう。 |
■ 「規定する」(prescribe)
| 「規定する」とは、この法律に基づき制定された規則で定めることをいう。 |
■ 「グループ/班」(group / relay )
| 「グループ」または「班」とは、同種の作業を1日の異なる時間帯に交替で行う労働者の組をいう。 |
■ 「シフト」(shift)
| 「シフト」とは、グループまたは班が業務に従事する特定の時間帯をいう。 |
■ 「公共の緊急事態」(public emergency)
| 「公共の緊急事態」とは、インド全体またはその一部の安全に対して外敵の侵略、外部からの侵略、内乱に由来する切迫した危険をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
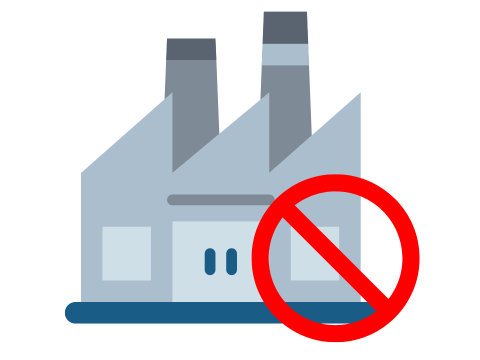
下記のものは工場の定義自体から除外されるため、本法の適用外となる。
- インド鉱山法の適用を受ける鉱山
- 軍の移動装置
- 鉄道車両の車庫
- ホテル、レストラン、飲食店
(第1条参照)
公共の緊急事態の場合には、州政府が官報により、本法の規定の全部または一部の適用を最長3か月間停止できる。
(第5条参照)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

工場を新設・増築するには、事前に設計図を提出し、州政府または主任監督官から書面による許可を得ることが必須となる。
工場の新設または増築に関する許可申請から3か月以内に通知がない場合、黙示的許可が成立したとみなされる。
許可拒否への不服申立て先は、州政府決定の場合は中央政府、主任監督官決定の場合は州政府となる。
(詳しくは第6条参照)
占有者は、工場稼働開始日の遅くとも15日前までに、主任監督官に対し定められた様式で、書面による届出を提出しなければならない。記載が義務付けられている事項には、工場の名称および所在地、占有者の氏名および住所等の基本的なものに加え、製造工程の種類、工場に設置済みまたは設置予定の定格馬力の合計値、工場で雇用される予定の労働者数等が定められている。
(詳しくは第7条参照)
占有者は、合理的に実行可能な範囲で、安全衛生・リスク低減のために下記の措置を実施しなければならない。
(a) 安全で健康に危険のない設備と作業体制を整備・維持すること。
(b) 物品や物質の使用・保管・輸送に伴う危険を防止する仕組みを設けること。
(c) 労働者の安全を確保するために必要な情報・指導・訓練・監督を行うこと。
(d) 作業場所と出入口を安全で健康に危険のない状態に維持すること。
(e) 安全で健康に危険のない作業環境と十分な福祉施設を確保・維持・監視すること。
(詳しくは第7A条参照)
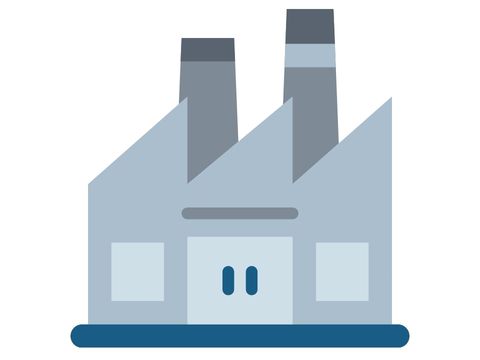
監督官は、工場またはその付属地への立入検査を行う権限を持ち、書類・記録等・設備・機械の検査や、物質の調査・試料採取等を行うことができる。事業者は、これらの調査行為を妨げてはならず、資料・情報提供等に協力しなければならない。
(詳しくは第9条参照)
すべての工場において、危険な可動部分(原動機のすべての可動部分および原動機に連結されたフライホイール、水車および水力タービンの上水路および下水路、旋盤の主軸頭を越えて突出する素材棒の部分)を防護柵・覆いで囲い、接触による事故を防止しなければならない。監督官が求める場合は追加防護を設置しなければならない。
(詳しくは第21条参照)
工場で作動中の機械を点検・調整・ベルトの装着などの作業を行う場合は、特別に訓練を受けた成人男性労働者のみが実施できる。その労働者は、占有者支給の密着した作業衣を着用し、氏名を登録簿に記録され、任命証明書を交付されていなければならない。
女性および未成年者は、原動機または伝導装置のすべての部分を、作動中に清掃、潤滑または調整してはならず、また、当該機械または隣接機械の可動部分による傷害の危険にさらされるおそれがある部分を清掃・潤滑・調整してはならない。
(詳しくは第22条参照)
州政府が規則で定める機械については、未成年者のその機械での就業、または就業を許可してはならない。ただし、未成年者が当該機械に関連して生ずる危険および遵守すべき安全措置について十分な指導を受けたうえで、作業について十分な訓練を受けている、または当該機械に関し十分な知識と経験を有する者の適切な監督下にある場合を除く。
(詳しくは第23条参照)

通常1,000人以上の労働者が雇用されている工場、または州政府の判断により、工場で行われる製造工程または作業が、労働者に身体的傷害、中毒、疾病その他健康への危険を伴うと認められる場合には、占有者は州政府の告示で定められた人数の安全担当官を雇用しなければならない。安全担当官の職務、資格および勤務条件は、州政府が規則で定めるところによる。
(詳しくは第40B条参照)
有害工程を行う工場の占有者は、危険情報の開示、安全衛生方針の策定と報告、緊急時対応計画の承認・周知、および有害物質の取扱い基準の設定・公表を定められた方法によって行わなければならない。MSDS、オンサイト緊急計画の整備・通報等は州規則で具体化されている。
有害工程を行う工場の占有者は、有害物質の取扱い、使用、輸送、貯蔵の方法および工場外での処理・廃棄方法を定め、定められた方法で労働者および周辺住民に周知・公表しなければならない。
(詳しくは第41B条参照)
有害工程を伴うすべての工場の占有者は、次の事項を履行しなければならない。
(a) 工場内で化学物質、有毒物質その他の有害物質にばく露する労働者について、正確かつ最新の健康記録(医療記録)を作成・維持し、定められた条件の下で労働者がそれを閲覧できるようにすること。
(b) 有害物質の取扱いに関して必要な資格および経験を有する者を監督者として任命し、作業現場において労働者の安全を確保するための必要な保護設備を提供すること。なお、当該任命者の資格・経験に疑義が生じた場合には、主任監督官の判断を最終とする。
(c) すべての労働者に対し、有害物質の取扱い業務に就く前、在職中、および離職後において、12か月を超えない間隔で定められた方法による健康診断を実施すること。
(詳しくは第41C条参照)
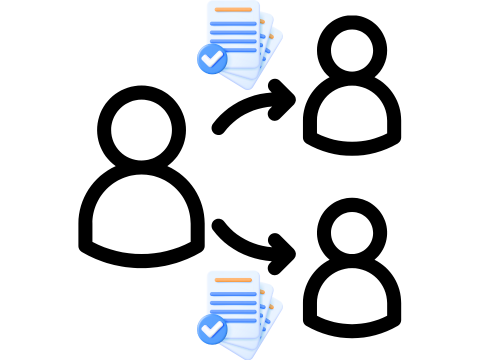
占有者は、労働者の清潔保持のための洗浄設備(第42条)を設け、作業衣などの保管・乾燥のための衣類設備(第43条)、作業の合間に休息できる休憩所・座席設備(第44条)を提供しなければならない。また、一定規模以上の工場では応急手当設備(第45条)や食堂(第46条)の設置が義務化され、女性労働者が一定数以上いる場合には保育室(第48条)の設置も必要となる。
(詳しくは第第42〜48条参照)
大規模工場では福祉担当官を任命し、福祉関連の運営・指導を行うことが求められる。これらの施設の設計、衛生基準、管理方法、ならびに設置後の届出・検査手続は、州政府の規則によって細かく定められている。
(詳しくは第49条参照)
占有者は、成人労働者の作業時間・シフト・休憩時間などを記載した就業時間表を所定の様式で作成し、工場内の見やすい場所に掲示しなければならない。また、変更を行う場合には、事前に監督官の承認を得る必要がある。所定様式および変更時の事前承認については州規則で求められるのが通例となっている。
(詳しくは第61条参照)
占有者は、成人労働者全員の氏名、勤務時間、交替班、作業区分などを記載した成人労働者名簿を備え付け、常に最新の状態に保たなければならない。
(詳しくは第62条参照)
女性労働者について、夜間就業など一定の時間帯(午後7時~翌午前6時)の労働を原則として禁止または制限しており、例外的に認められる場合でも、州政府の規則や通達に基づく特別許可を得ることが義務付けられている。
(詳しくは第66条参照)
満15歳未満の児童の就業は禁止されている。
(第67条)
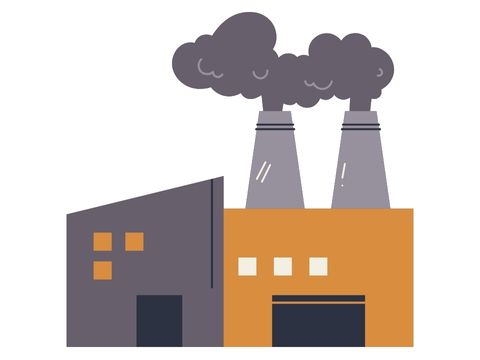
工場で就業する未成年者は、識別票(トークン)を携行しなければならない。この識別票には、健康適正証明書の番号など必要事項を記載し、工場内での本人確認や就業資格の確認に用いることとされている。
(詳しくは第68条参照)
工場で就業する未成年者について、作業に従事させる前に証明医師による健康適正証明書を取得しなければならないと定めている。また、この証明書を持たない未成年者を就業させることは禁止されている。
(詳しくは第69条参照)
占有者は、工場で就業する児童または未成年者の就業時間やシフトを記載した掲示表を所定の場所に掲示しなければならない。
(詳しくは第72条参照)
占有者は、工場で就業するすべての児童または未成年者の名簿を備え付け、その氏名、年齢、就業の区分などを記録し、常に最新の状態に保たなければならない。
(詳しくは第73条参照)
占有者は、労働者の勤務日数に応じて、一定期間勤務した労働者に対し、翌暦年に定められた日数の休暇を与えなければならない。また、未成年者には成人より多い休暇日数を付与することが求められる。
(詳しくは第79条参照)
工場で一定の災害が発生した場合、占有者は、定められた様式に従って直ちに当局へ届出を行わなければならない。災害の内容、負傷者の氏名、発生日時などを正確に報告することが求められる。
(詳しくは第88条参照)
災害に至らない場合でも、爆発、倒壊、火災などの一定の危険事象が発生したときは、占有者が速やかに州政府の規則で定められた様式および期限で当局に届出をしなければならない。
(詳しくは第88A条参照)

指定された特定の疾病が診断された場合、診断した医師と工場の占有者の双方が、定められた書式と期限に従い当局へ届出を行わなければならない。これにより職業性疾病の早期把握と対策が可能となる。
(詳しくは第89条参照)
占有者または関係者が、許認可や命令などの行政処分に不服がある場合、定められた期間内に審査請求を行わなければならない。申請の書式や添付資料の内容は規則で詳細に定められている。
(詳しくは第107条参照)
占有者は、工場内の労働者が容易に確認できる場所に、関係する規則、命令、または当局からの告示などを掲示しなければならない。掲示は常に最新の状態を保つ必要がある。
(詳しくは第108条参照)
占有者は、工場の運営状況に関する年次または半期ごとの定期報告書を、定められた様式で提出しなければならない。報告には、雇用者数、労働時間、事故件数、休暇状況、福利施設、残業などに関する情報を含める必要がある。
(詳しくは第110条参照)
附属書1には、有害工程として指定された製造活動が示されている。これに該当する工場の占有者は、危険情報の開示や緊急時対応計画の策定など特別な安全管理義務を負う。
附属書2は、作業環境中の化学物質の許容濃度を定めた基準であり、占有者は濃度を超えないよう監視・管理しなければならない。2015年12月の改正により、金属リサイクル業で扱われる放射性核種(Co-60、Cs-137、Am-241、Ir-192)の許容放射能濃度が追加された。
附属書3は、届出対象疾病の一覧である。該当疾病が診断された場合には、医師および占有者が当局に届け出なければならない。
附属書4は、和解の対象となる特定の違反行為を定め、該当する場合は副主任監督官以上の職員が、法定上限の範囲内で和解金を徴収できるとする。
目次
第1章 総則
第1条 短縮題名、適用範囲及び施行
第2条 定義
第3条 一日における時刻の基準
第4条 異なる部門を別個の工場とする、または複数の工場を単一の工場として申告する権限
第5条 公共の緊急事態における適用除外の権限
第6条 工場の承認、免許及び登録
第7条 占有者による届出
第2章 監督職員
第7A条 占有者の一般的義務
第7B条 工場で使用される物品及び物質に関する製造業者等の一般的義務
第8条 監督官
第9条 監督官の権限
第10条 認定外科医
第3章 衛生
第11条 清潔
第12条 廃棄物及び排出物処理
第13条 換気及び温度
第14条 粉じん及び煙霧
第15条 人工加湿
第16条 過密状態
第17条 照明
第18条 飲料水
第19条 便所及び小便所
第20条 痰つぼ
第4章 安全
第21条 機械の防護
第22条 作動中の機械上または付近での作業
第23条 危険な機械を用いる業務への未成年者の就業
第24条 打撃装置及び動力遮断装置
第25条 自動機械
第26条 新設機械の防護覆い
第27条 綿開機付近での女性及び児童の就業禁止
第28条 巻上機及び昇降機
第29条 揚重機、鎖、ロープ及び吊具
第30条 回転機械
第31条 圧力装置
第32条 床、階段及び通路
第33条 坑・集水槽・床の開口部等
第34条 過大な荷重
第35条 眼の保護
第36条 危険な蒸気及びガス等に対する予防措置
第36A条 携帯電灯の使用に関する予防措置
第37条 爆発性または可燃性の粉じん及びガス等
第38条 火災の場合の予防措置
第39条 欠陥部の仕様提出または安定性試験の要求権限
第40条 建物及び機械の安全
第40A条 建物の維持保全
第40B条 安全担当官
第41条 本章を補足する規則制定権
第4A章 有害工程に関する規定
第41A条 立地評価委員会の設置
第41B条 占有者による情報の強制開示
第41C条 有害工程に関する占有者の特定の責務
第41D条 中央政府による調査委員会任命権
第41E条 緊急基準
第41F条 化学物質及び有毒物質のばく露許容限界
第41G条 安全管理への労働者の参加
第41H条 差し迫った危険に関する労働者の警告権
第5章 福祉
第42条 洗浄設備
第43条 衣類の保管及び乾燥設備
第44条 休座設備
第45条 応急手当設備
第46条 食堂
第47条 休憩所、休憩室及び昼食室
第48条 保育室
第49条 福祉担当官
第50条 本章を補足する規則制定権
第6章 成人の労働時間
第51条 週労働時間
第52条 週休日
第53条 代替休日
第54条 日労働時間
第55条 休憩時間
第56条 一日の拘束時間
第57条 夜勤
第58条 重複交替の禁止
第59条 残業の割増賃金
第60条 二重就業の制限
第61条 成人の就業時間の通知
第62条 成人労働者名簿
第63条 第61条通知及び第62条名簿との時間整合
第64条 免除規則制定権
第65条 免除命令発出権
第66条 女性の就業に関する追加制限
第7章 未成年者の就業
第67条 幼年児童の就業禁止
第68条 未成年労働者の識別票携行義務
第69条 健康適性証明書
第70条 青年への健康適性証の効果
第71条 児童の労働時間
第72条 児童の就業時間の通知
第73条 児童労働者名簿
第74条 第72条における通知及び第73条における名簿との時間整合
第75条 医学的検査を求める権限
第76条 規則制定権
第77条 他法の特定規定の適用妨げなし
第8章 年次有給休暇
第78条 本章の適用
第79条 年次有給休暇
第80条 休暇中の賃金
第81条 一部前払い
第82条 未払賃金の回収方法
第83条 規則制定権
第84条 工場の適用除外権限
第9章 特別規定
第85条 特定の事業所への本法適用権限
第86条 公共機関の適用除外権限
第87条 危険作業
第87A条 重大な危険による就業禁止権限
第88条 特定の災害の届出
第88A条 特定の危険事象の届出
第89条 特定疾病の届出
第90条 災害または疾病の事案に対する調査指示権
第91条 試料採取権限
第91A条 安全及び労働衛生調査
第10章 罰則及び手続
第92条 一般罰則
第92A条 特定の違反の和解処理
第93条 一定の場合の建物所有者の責任
第94条 既往有罪後の加重罰
第95条 監督官職務妨害による罰
第96条 第91条における分析結果不正開示による罰
第96A条 第41B条・第41C条・第41H条違反による罰
第97条 労働者による違反
第98条 虚偽の健康適性証使用による罰
第99条 児童の二重就業許可による罰
第100条 [削除]
第101条 特定の場合の占有者または管理者の免責
第102条 裁判所の命令権限
第103条 雇用に関する推定
第104条 年齢に関する立証責任
第104A条 実行可能性の限界等の立証責任
第105条 違反の受理権限
第106条 起訴の時効制限
第106A条 犯罪手続等を受理する裁判所の管轄
第11章 補則
第107条 不服申立て
第108条 通知の掲示
第109条 通知の送達
第110条 報告書類
第111条 労働者の義務
第111A条 労働者等の権利
第112条 一般的規則制定権
第113条 中央政府の指示権限
第114条 施設および用具の無償提供
第115条 規則の公示
第116条 政府工場への本法の適用
第117条 本法に基づく行為者の保護
第118条 情報開示の制限
第118A条 情報開示の追加制限
第119条 1970年法第37号等に優先
第120条 廃止及び経過措置
附属書
附属書1 有害工程を伴う業種の一覧
附属書2 作業環境における特定化学物質の許容濃度
附属書3 届出義務疾病一覧
基礎情報
| 法令(現地語) |
An Act to consolidate and amend the law regulating labour in factories (The Factories Act, 1948) |
| 法令(日本語) | 工場労働規制統合及び改正法 (工場法, 1948) |
| 公布日 | 1948年09月23日 |
| 所管当局 | 雇用労働省 |
作成者