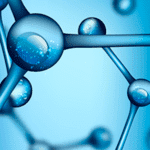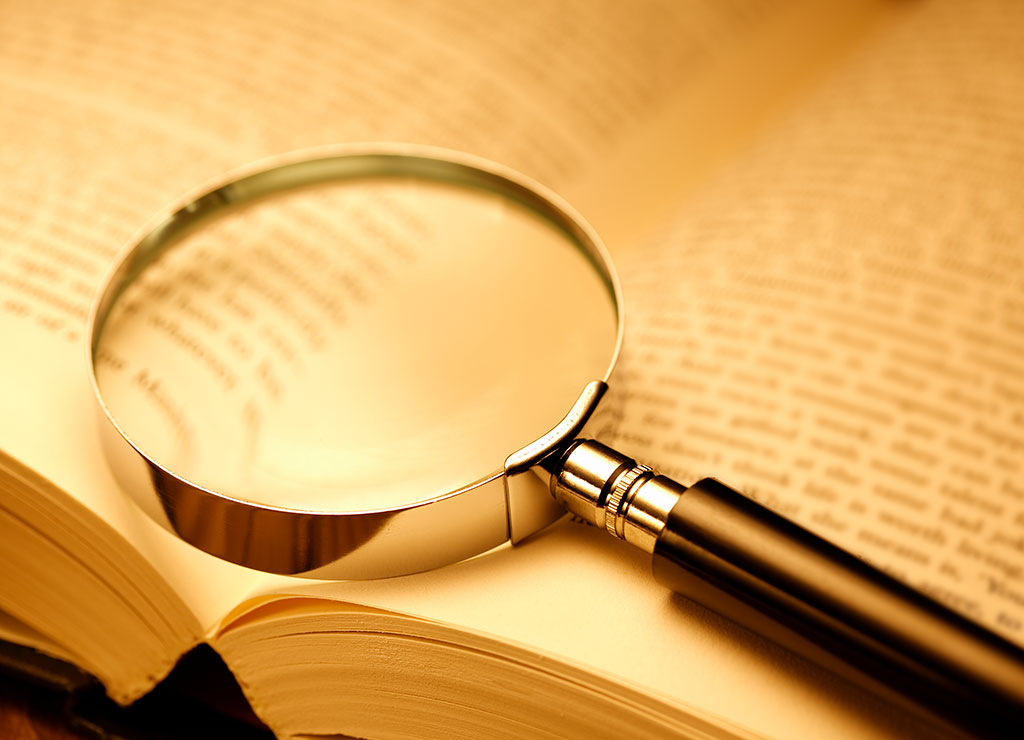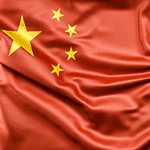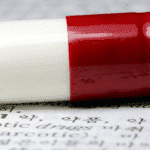| 法令の情報時期:2015年03月 統合版 | ページ作成時期:2025年06月 |
目的

本法律は、消費者の社会的・経済的福祉の向上を目的とし、以下を実現するための枠組みを提供する。
- 公正・持続可能・アクセス可能な消費者市場の確立
- 弱者(低所得者、辺地住民、高齢者、読み書き困難者など)の保護
- 不当・欺瞞的・詐欺的取引からの保護
- 情報提供と教育による消費者意識の向上
- 自主的な紛争解決制度と救済制度の確立
概要

本法律は、南アフリカにおける公正で持続可能な消費者市場の確立を目的とした包括的立法である。
消費者の選択の自由、返品・修理・情報提供に関する権利、誤解を招く表示や不当な取引からの保護など、幅広い権利を明文化している。
特に社会的弱者の保護を重視し、すべての消費者に対する実質的平等の実現を目指す。
国家消費者委員会を中心に執行体制を整備し、紛争解決と救済の制度を設けている。
事業者には公正取引と明確な情報開示を義務づけ、契約や広告等における透明性と誠実性を確保する。
注目定義
<対象者>
■ 「消費者」(consumer)
| 「消費者」とは、特定の商品またはサービスに関して、次のいずれかに該当する者をいう。 (a) 通常の供給者の業務の過程において、当該商品またはサービス提供または宣伝される者 (b) 通常の供給者の業務の過程において供給者と取引を行った者(ただし、その取引が第5条第2項または第5条第3項により本法の適用除外とされる場合を除く) (c) 文脈がそのように要求または許容する場合には、当該商品の使用者、または当該サービスの受領者もしくは受益者であって、当該商品またはサービスの供給に関する取引の当事者であったかどうかを問わない者 (d) フランチャイズ契約に基づくフランチャイジーであって、第5条第6項(b)から(e)の範囲において該当する者 |
■ 「供給者」(supplier)
| 「供給者」とは、通常の業務として商品やサービスを提供する者をいう。 |
■ 「輸入者」(importer)
| 「輸入者」とは、特定の商品に関して、当該商品を通常の営業の過程で供給可能とする意図をもって、国外から共和国内へ持ち込むか、または持ち込ませる者をいう。 |
■ 「製造者」(producer)
| 「製造者」とは、特定の商品に関して、以下のいずれかに該当する者をいう。 (a) 商品を通常の営業の過程で供給可能とする意図をもって、当該商品を共和国内において育成、養殖、収穫、採掘、発電、精製、創作、製造、またはその他の方法で生産するか、またはこれらの行為のいずれかを行わせる者、または (b) 当該商品にまたはそれに関連して、個人名・事業名・商標・取引表示・その他の視覚的表示を表示することにより、その者が上記(a)に該当する者であるという合理的な期待を生じさせた者 |
■ 「仲介者」(intermediary)
| 「仲介者」とは、第三者の財やサービスを紹介・販売・斡旋する者をいう。 |
■ 「小売業者」(retailer)
| 「小売業者」とは、特定の商品に関して、通常の営業の過程においてその商品を消費者に供給する者をいう。 |
■ 「法的主体」(juristic person)
| 「法的主体」とは、以下のものを含むものをいう。 (a) 法人 (b) パートナーシップまたは団体 (c) 「1988年信託財産法」において定義される信託 |
■ 「大臣」(the Minister)
| 「大臣」とは、本法の施行および管理を担当する貿易・産業・競争大臣をいう。 |
<対象製品>
■ 「取引」(transaction)
| 「取引」とは、対価を伴う商品・サービスの供給、またはそれに関する契約・やり取りをいう。 |
■ 「契約」(agreement)
| 「契約」とは、法的関係を構築することを目的とした二者以上の合意をいう。 |
■ 「広告」(advertisement)
| 「広告」とは、商品・サービスの存在・特性等を広報する目的の視覚・音声的伝達をいう。 |
■ 「販売促進」(promote)
| 「販売促進」とは、対価を得ることを目的に商品・サービスの提供を誘引する行為をいう。 |
■ 「マーケティング」(market)
| 「マーケティング」とは、商品・サービスの宣伝・供給を行うことをいう。 |
■ 「表示」(trade description)
| 「表示」とは、商品に関する数量・製造者・原材料・産地等を示す記述をいう。 |
■ 「商標」(trade mark)
| 商標とは、商標法に基づく登録商標または著名商標をいう。 |
■ 「サービス」(service)
| 「サービス」とは、金銭その他の対価の有無を問わず、ある者が他者のために提供する業務または便益の総称をいう。サービスは以下のものを含むがこれらに限られない。 (a)労務提供 (b)教育・情報・助言の提供 (c)金融サービスの提供 (d)輸送サービス (e)施設・イベント・インフラへの立入・参加機会提供、使用機会等の提供 (f)不動産に関する権利の提供 (g)フランチャイズ契約に基づく権利の供与 |
■ 「商品」(goods)
| 商品とは、消費用物品、無形財(ソフトウェア等)、土地関連権利、電力・水などを含む。 |
■ 「委員会」(Commission)
| 委員会とは、第85条により設置された国家消費者委員会をいう。 |
■ 「審判所」(Tribunal)
| 審判所とは、国家信用法第26条に基づき設置された国家消費者審判所をいう。 |
■ 「直接販売」(direct marketing)
| 直接販売とは、個人に対する直接または電子的手段での販売勧誘をいう。 |
■ 「ネガティブ・オプション・マーケティング」(negative option marketing)
| 「ネガティブ・オプション・マーケティング」とは、消費者が明示的に拒否をしない限り、自動的に商品やサービスを購入したものとみなす販売手法をいう。 |
■ 「ロイヤルティ・クレジット/ロイヤルティ・アワード」(loyalty credit / loyalty award)
| 「ロイヤルティ・クレジット」または「ロイヤルティ・アワード」とは、ロイヤルティ・プログラムに基づいて消費者に付与される以下のいずれかをいう。 (a) 消費者に生じる利益 (b) 消費者に付与される、商品、サービス、またはその他の利益に対する権利 (c) 一定量蓄積されることにより、その保有者が商品、サービス、またはその他の利益を要求・請求・主張することができるポイント、クレジット、トークン、デバイス、その他有形または無形のもの。 |
■ 「ロイヤルティ・プログラム」(loyalty programme)
| 「ロイヤルティ・プログラム」とは、通常の営業の過程において、商品またはサービスの供給者、その供給者の団体、またはそのような供給者に代わり、またはそれらと連携する他の者が、取引または契約に関連して消費者に対してロイヤルティ・クレジットまたはロイヤルティ・アワードを提供または付与する制度をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
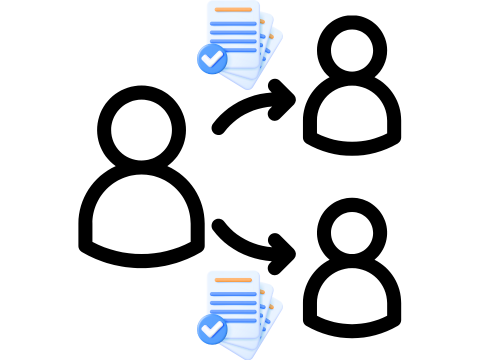
本法律は、以下のいずれかに該当する取引には適用されない。
(a) 商品またはサービスが国家に対して宣伝または供給されることを内容とする取引
(b) 取引の時点で、消費者が第6条に基づき大臣により定められた閾値金額に等しいかそれを超える資産価値または年間売上高を有する法的主体である場合の取引
(c) 第5条 第3項および第4項に基づき大臣により免除が認められた取引
(d) 当該取引が「国家信用法」に基づくクレジット契約である場合。ただし、そのクレジット契約の対象となる商品またはサービス自体は本法の適用範囲から除外されない。
(e) 雇用契約に基づいて提供されるサービスに関する取引
(f) 憲法第23条および「1995年労働関係法」の意味における団体交渉協定を実施することを目的とした取引
(g) 「1995年労働関係法」第213条に定義される団体協定を実施することを目的とした取引
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
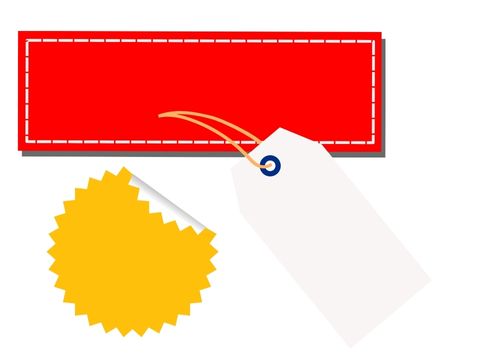
- 本法または他の法令に基づき消費者に提供される通知・文書・表示は、所定の様式があればそれに従い、なければ一般の消費者が容易に理解できる平易な言語で作成されなければならない。
文書の分かりやすさは、語彙や文構造、文脈、図解等を総合的に見て判断される。 - 委員会は判断基準のガイドラインを公表できる。
(詳しくは第22条「平易かつ理解しやすい言語での情報提供」参照)
- 原則として、小売業者は商品を表示販売する際に価格を提示しなければならず、明示された価格を超える金額を消費者に請求してはならない。
- 価格表示には、商品に直接貼付されたものやカタログ等による掲示が含まれる。
- 価格の誤表示や無断改ざんがある場合は、一定条件下でその価格に拘束されない。
(詳しくは第23条「商品またはサービス価格の開示」参照)
- 商品に用いられる表示(取引表示)は、誤認を招く内容であってはならず、改ざん等によって消費者を欺く行為も禁止される。
- 小売業者は、誤解を招く表示がある商品を販売・陳列してはならず、その防止措置を講じる責任がある。
- 大臣は原産国表示など必要情報を義務付けることができ、遺伝子組換え成分の表示も規制に基づき義務付けられる。
(詳しくは第24条「製品ラベルおよび取引表示」参照)

(1)仲介者は、以下のすべての関係者に対して、定められた情報を開示しなければならない。
- 販売のために仲介者が勧誘または代理を行う者、または販売目的で財産を預かる者
- 第三者が所有する財やサービスについて、供給を提案または実施する相手方
また、仲介者はこれらの関係・取引について定められた記録を保存する義務がある。
(2)本条は、以下の立場にある仲介者には適用されない。
- 被相続人の財産の管理者(遺言執行者等)
- 破産財産の管財人
- 信託財産に関する受託者
(3)大臣は、以下を規定することができる。
- 仲介者(またはその類型)が開示すべき情報とその形式・方法
- 保持すべき記録の様式および内容
(詳しくは第27条「仲介者による情報開示」参照)
商品やサービスの配送、設置、修理などに関わる業者は、消費者に対して自らの身元や所属事業者を明確に示さなければならない。供給者は、それらの業者が識別可能な標識や証明を保持・表示することを確保する責任がある。
(詳しくは第28条「配送者・設置業者等の識別」参照)

- 供給者またはその代理人は、商品・サービスの提供や契約交渉等において、暴力、強制、威圧、ハラスメント、不当な戦術等を用いてはならない。
- 消費者が身体的・精神的障害、無知、言語理解力の不足などにより自身の権利を守れない状態にあることを知りながら、その状況を悪用する行為も禁じられる。
(詳しくは第40条「不当な行為」参照)
- 商品やサービスの販売促進において、事実に反する説明、誇張、曖昧な表現、重要な事実の不開示など、誤解を招く表示は禁止される。
- 表示されている品質、性能、原産地、使用実績、価格などが事実と異なる場合、虚偽表示と見なされる。
(詳しくは第41条「虚偽・誤解・欺瞞的表示」参照)
- 商品・サービスの供給や契約への勧誘に関する通信において、実際には提供されない商品を提示したり、虚偽の条件で契約を誘導するなど、詐欺的手法は禁止される。
- 虚偽情報に基づく勧誘や意図的な誤認表示があれば、法的責任が問われる。
(詳しくは第42条「詐欺的スキームと申出」参照)
- ピラミッド販売、連鎖販売、マルチ商法など、主に新規参加者の勧誘によって報酬が得られるスキームへの参加・促進を禁じる。
- 顧客や参加者に20%以上の年利回りを保証する投資なども違法とされる。
(詳しくは第43条 ピラミッド方式等のスキーム」参照)
- 実際には提供できない商品・サービスについて、金銭の受領や予約受付を行うことは禁止されている。
- 十分な在庫・能力がない状態で供給を約束した場合、消費者への返金と損害賠償が義務付けられる。
(詳しくは第47条「過剰販売および過剰予約の禁止」参照)
- 法の目的を無効化したり、消費者を誤導・欺瞞・詐欺に陥れる内容の契約は無効とされる。
- 消費者の権利を放棄させる条項、供給者の義務を逃れる条項、または違法行為を許可する内容はすべて禁じられる。
- 第31条(ネガティブ・オプション・マーケティング)に違反する提案や、別契約を強要する条項も無効とされる。
(詳しくは第51条「禁止される取引・契約・条件」参照)
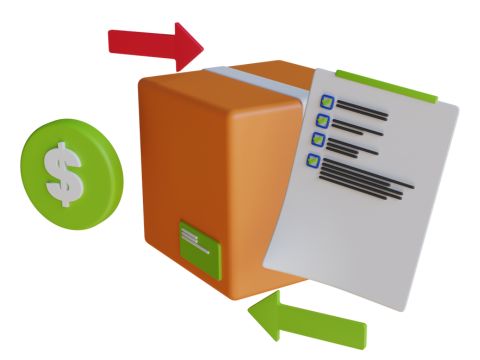
- 消費者には、通常使用に耐える安全かつ良質な商品を受け取る権利がある。
- 商品は合理的な耐用期間内、安全に使用でき、正常に機能するものでなければならない。
- サービスについても、技能的に適切で、消費者にとって合理的な品質が求められる。
- 本条は、第45条に規定される競売において購入された商品には適用されない。
(詳しくは第55条「安全で良質な商品についての消費者の権利」参照)
- 商品が新品である場合、6か月間の無償修理・交換・返金の権利が自動的に付与される。
- 欠陥が販売後に発見された場合でも、通常使用の範囲であれば消費者は救済を受けられる。
- 修理された商品にも、再度3か月間の保証が適用される。この期間内に故障・欠陥・危険な特徴が改善されなかったとき、または新たな故障・欠陥・危険な特徴が判明したときは、供給者は以下のいずれかを行わなければならない。
(a) 商品の交換、または
(b) 消費者が当該商品に対して支払った代金の返金。
(詳しくは第56条「品質の黙示保証」参照)
- 委員会は、製品の不具合や危険性に関する苦情、返却、事故報告などの情報を受け取り、分析・監視するための業界共通の実務規範の策定と適用を促進する。これにより、製品の潜在的リスクを早期に特定し、必要に応じて調査、消費者への警告、リコール(修理・交換・返金)を行う体制を整える。
- 委員会が、商品に安全上の問題があると判断し、製造者や輸入者が適切な対応をしていない場合には、書面通知により調査やリコールの実施を命じることができる。当該通知を受けた事業者は、その全部または一部の取消しを審判所に申請できる。
(詳しくは第60条「安全監視およびリコール」参照)
- 製造者、輸入者、流通業者、小売業者は、商品が危険であった場合や、欠陥や不備がある場合、危険性に関する指示や警告が不十分であった結果として生じた損害について、過失の有無にかかわらず責任を負う。
- サービス提供に付随して商品を供給した者も、その商品について同様の責任を負う。これらの責任は連帯して負うものとされ、消費者は関係者のいずれに対しても請求できる。
- 以下の場合は責任が免除される。
(1)欠陥等が法令遵守の結果である場合
(2)供給時に欠陥等が存在しなかった場合
(3)上位供給者の指示による場合
(4)流通業者等が欠陥を発見することが不合理である場合
(5)損害の発生やそれに関する重要事実の認識から3年以上が経過している場合 - 本条で対象となる損害には、人の死亡・負傷・疾病、財産の損壊、これらに伴う経済的損失が含まれる。
(詳しくは第61条「商品に起因する損害の責任」参照)

- 供給者は、取引の相手方である消費者がその名称・連絡先を認識できるよう、明確に表示する義務を負う。
- この情報は、領収書、契約書、広告、請求書などで明示されなければならない。
(詳しくは第79条「供給者の識別義務」参照)
- 商号を使用する供給者は、所定の料金を支払い、下記の事項を所定の機関(企業・知的財産委員会)に登録しなければならない。
(a) 自身の事業において現在使用している、または将来使用予定の1件以上の商号の登録
(b) 同一の商号を、南アフリカ共和国の複数の公用語に翻訳した形での登録
(c) 登録済み商号の変更
(d) 登録済み商号の他者への譲渡。 - 登録は個人・法人を問わず適用され、誤認を防ぐための措置でもある。
- 商号が登録された後、登記官がその者が6か月以上その商号で事業を行っていないとみられる場合には、登録者に対して、登録を抹消すべきでない理由を所定の方法で示すよう求めることができる。
登録者が所定期間内に通知に応答しなかった場合、または登記官が納得できる形で、当該商号で事業を行っている証拠を提出できなかった場合等には、登記官は登録者の登録を所定の様式で抹消することができる。
(詳しくは第80条「商号の登録」参照)
- 商号には、日常的な語句や造語を含む任意の言語の語に加えて、文字・数字・句読点、特定の記号(+, &, #, @, %, =)、規則で許可された記号、および対の丸括弧を含むことができる。これらは自由に組み合わせて用いることが可能である。
- 商号は、以下のいずれにも該当してはならない。
(1)他の法人名や登録商標などと同一または紛らわしい類似性があること
(2)他者や国家機関、特定の資格者などとの誤認を招くような内容を含むこと
(3)憲法第16条第2項により制限される表現(例:憎悪表現など)を含むこと - 大臣は、商号に用いることができる記号として、新たに一般的に認識される記号を規則で定めることができる。
(詳しくは第81条「商号に関する基準」参照)

- 審判所の命令に違反または不履行があった場合は違反となる。
- 以下の行為も違反となる。
(a)審判所や規制当局に対し、不正に影響を与えようとする行為
(b)調査に関する判断を先取りし、影響を与えようとする行為
(c)調査に関連し、法廷侮辱と同等とみなされる行為
(d)虚偽情報の故意の提供
(e)審判所またはその構成員に対する名誉毀損
(f)審理の場での妨害行為や不品行
(g)捜索令状に違反する行為
(h)権限がないのに第103条を装って、立入・捜索・押収を行う行為
(詳しくは第109条「委員会および審判所に関する違反行為」参照)
- 権限なく、表示価格やラベル、商品説明を改ざん・隠蔽・削除・省略することは違反である。
- コンプライアンス通知に従わなかった場合も違反となるが、その不履行に対して委員会が審判所へ行政罰を申し立てた場合は、重ねて刑事訴追は行われない。
(詳しくは第110条「禁止行為に関する違反」参照)
目次
第1章 解釈、目的および適用
A部 解釈
第1条 定義
第2条 解釈
B部 本法の目的、方針および適用
第3条 本法の目的および方針
第4条 消費者権利の実現
第5条 本法の適用
第6条 基準値の決定
第7条 フランチャイズ契約の要件
第2章 基本的消費者権利
A部 消費者市場における平等の権利
第8条 差別的マーケティングからの保護
第9条 特定の事情における差別的取扱いの合理的根拠
第10条 本部に関する平等裁判所の管轄
B部 プライバシーに関する消費者の権利
第11条 不要なダイレクトマーケティングの制限権
第12条 消費者への連絡時間の規制
C部 選択に関する消費者の権利
第13条 供給者選択の権利
第14条 定期契約の終了および更新
第15条 修理・保守サービスの事前承諾
第16条 ダイレクトマーケティング後のクーリングオフ期間
第17条 予約・注文等の取消権
第18条 商品の選択・検査の権利
第19条 商品の配送またはサービス提供に関する権利
第20条 商品の返品に関する権利
第21条 無断提供された商品またはサービス
D部 情報開示と説明の権利
第22条 平易かつ理解しやすい言語での情報提供
第23条 商品またはサービス価格の開示
第24条 製品ラベルおよび取引表示
第25条 再生品・並行輸入品の開示
第26条 販売記録
第27条 仲介者による情報開示
第28条 配送業者・設置業者等の識別
E部 公正かつ責任あるマーケティングの権利
第29条 商品・サービスのマーケティングに関する一般基準
第30条 おとり広告
第31条 ネガティブ・オプション・マーケティング
第32条 ダイレクトマーケティング
第33条 カタログ販売
第34条 商品券・類似の販促活動
第35条 顧客ロイヤルティプログラム
第36条 景品付き販売促進
第37条 代替労働制度
第38条 紹介販売
第39条 法的能力を欠く者との契約
F部 公正かつ誠実な取引の権利
第40条 不当な行為
第41条 虚偽・誤解・欺瞞的表示
第42条 詐欺的スキームと申出
第43条 ピラミッド方式等のスキーム
第44条 供給者が販売権限を有するとの前提
第45条 競売
第46条 変更、延期、放棄および代替品の提供
第47条 過剰販売および過剰予約の禁止
G部 公正・妥当・合理的な契約条件の権利
第48条 不当・不合理または不公正な契約条件
第49条 特定条件に対する通知義務
第50条 書面による消費者契約
第51条 禁止される取引・契約・条件
第52条 裁判所の公平・公正確保権限
H部 公正な価値、良質、安全性に関する権利
第53条 本部に適用される定義
第54条 良質なサービス提供を受ける消費者の権利
第55条 安全で良質な商品についての消費者の権利
第56条 品質の黙示保証
第57条 修理済商品に対する保証
第58条 リスクの事実と性質に関する警告
第59条 特定製品・部品の回収および安全な廃棄
第60条 安全監視およびリコール
第61条 商品に起因する損害の責任
I部 供給者の説明責任
第62条 取り置き販売
第63条 前払証書・クレジット・バウチャー
第64条 前払サービスおよび施設利用権
第65条 消費者の財産の保管および説明責任
第66条 容器・パレット等に関する保証金
第67条 部品・材料の返却
第3章 消費者の権利保護および意見表明
A部 消費者の権利
第68条 消費者の権利の保護
第69条 消費者による権利の行使
第70条 代替的紛争解決手続
第71条 委員会への苦情申立て
B部 委員会による調査
第72条 委員会による調査
第73条 調査結果
第74条 同意命令
第75条 審判所への付託
C部 裁判所による救済
第76条 裁判所による消費者権利の執行権限
D部 市民社会による支援
第77条 消費者保護団体に対する支援
第78条 認定消費者保護団体による訴訟の提起
第4章 商号および業界行動規範
A部 商号
第79条 供給者の識別義務
第80条 商号の登録
第81条 商号に関する基準
B部 業界行動規範
第82条 業界規範
第5章 国家消費者保護機関
A部 国家および州の連携
第83条 共同管轄権の協力的行使
第84条 州消費者保護機関
B部 国家消費者委員会の設立
第85条 国家消費者委員会の設立
第86条 大臣による政策指示および調査命令
第87条 委員長の任命
第88条 検査官および調査官の任命
第89条 利益相反
第90条 財務
第91条 大臣への報告および監査
C部 委員会の機能
第92条 委員会の一般的権限
第93条 本法に関する実務基準の策定
第94条 立法改革の促進
第95条 行政機関における消費者保護の推進
第96条 調査および広報活動
第97条 他の規制当局との関係
第98条 大臣への助言および勧告
第6章 本法の執行
A部 委員会による執行
第99条 委員会の執行機能
第100条 遵守通知
第101条 通知に対する異議申立て
B部 調査支援のための権限
第102条 召喚
第103条 令状に基づく立入・捜索の権限
第104条 立入・捜索の実施
第105条 立入・捜索の手続
第106条 機密情報に関する主張
C部 違反および罰則
第107条 機密保持違反
第108条 本法の執行妨害
第109条 委員会および審判所に関する違反行為
第110条 禁止行為に関する違反
第111条 刑罰
第112条 行政罰金
第113条 使用者責任
D部 その他の事項
第114条 仮の救済措置
第115条 民事訴訟および管轄
第116条 訴訟提起の制限
第117条 証明基準
第118条 書類の送達
第119条 事実の証明
第7章 一般規定
第120条 規則
第121条 関連法の改正・廃止および経過措置
第122条 法の題名および施行日
附属書1 法律の改正履歴
附属書2 経過規定
-
定義
-
本法の段階的施行
-
既存の取引および契約への適用
-
第11条4項(b)(ii)の施行の延期
-
商号登録義務の免除
-
規則、権利、義務、通知その他の措置の継続適用
-
州の規制能力
-
廃止法の継続適用
-
旧法に基づく国家職員の取扱い
-
特定法の除外
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 2008年消費者保護法 |
| 公布日 | 2009年4月29日 |
| 所管当局 | 貿易・産業・競争省 |
作成者