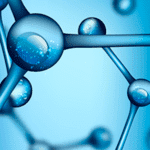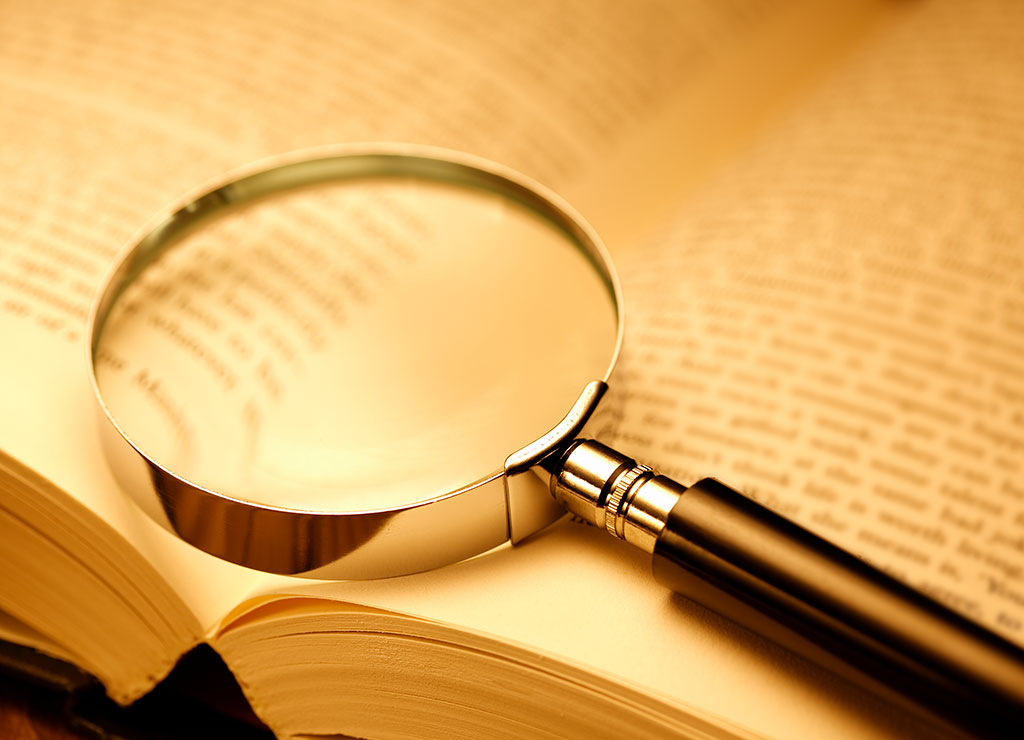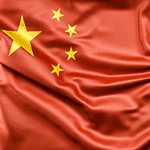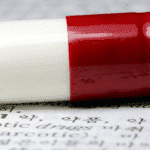| 法令の情報時期:2023年08月 版 | ページ作成時期:2025年06月 |
目的

本法は、電気・電子製品および自動車のリサイクル促進のため、有害物質の使用を抑制し、再資源化しやすい形態で製造し、廃棄物を適正に再資源化することにより、資源を効率的に利用する資源循環体制を構築し、環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
概要

本法は、電気・電子製品・自動車の有害物質抑制、リサイクルしやすい設計、廃棄物の回収・リサイクルのため、国家・地方自治体・事業者・国民の責務や国際協力促進等について規定し、資源循環へ向けた基本的な枠組みを構築している。
主な規制として、製造段階での有害物質含有基準の遵守とその公表、材質・構造改善指針と年次リサイクル可能率の設定、製造・販売業者には製品群別の回収・リサイクル義務量と賦課金制度が課され、廃自動車については再資源化比率、費用充当、残渣・誘発物質の回収処理などが定められている。
リサイクル関連事業者は登録制とされ、帳簿記録・報告・検査、情報体系の運用といった監督措置も設けられている。
国はリサイクル事業者や自治体への行政・技術・財政支援、廃資源収集センターの設置運営など促進策を講じる一方、義務違反に対しては懲役・罰金などの罰則が定められている。
注目定義
■ 「電気・電子製品」(전기ㆍ전자제품)
| 「電気・電子製品」(전기ㆍ전자제품)とは、電流と電磁場を生成・移動・伝送または測定、または電流および電磁場によって作動する機械・器具(部分品・付属品を含む)をいう。 |
■ 「自動車」(자동차)
| 「自動車」(자동차)とは、「自動車管理法」第2条第1号に定義される自動車(部分品・付属品を含む)をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外は特に明記されていない。電気・電子製品・自動車のリサイクル促進に関しては、他の法律に優先して本法が適用される。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

【国・自治体・事業者・国民の責務】
- 国はリサイクル促進の資源循環施策を設け、廃棄物リサイクルの技術開発、普及に努める。自治体はこれに基づき運営・支援など必要な措置を講じる。(第4条)
- 製造・輸入事業者は、リサイクル技術の開発、リサイクル容易化、有害物質の使用抑制、廃棄物化の抑制と回収・再資源化、製品廃棄物の回収体制構築に努めなければならない。(第5条)
- 電気・電子製品の販売業者は、廃製品回収への積極的な取り組みと資源循環の効率化を図る。リサイクル事業者は、リサイクル可能な資源を最大限リサイクルし資源節約に努める。廃製品の処理業者は、環境への影響を最小化して処理を行わなければならない。(第5条)
- 国民は、電気・電子製品や自動車の廃棄物を適切に排出するなど、国および地方自治体が本法の目的達成のために行う措置に協力するよう努めなければならない。(第6条)
- 環境部長官と産業通商資源部長官は、有害物質分析結果やリサイクル可能率評価結果の各国相互認証を推進するなど、国際協力施策を講じる。(第7条)

【有害物質の使用制限】
- 日常的に流通量が多い指定電気・電子製品および指定自動車の製造・輸入事業者は、製造段階で環境に影響の大きい重金属や難燃剤など指定有害物質の含有基準を遵守しなければならない(除外:技術的に除去不可・代替物質なし、研究開発・輸出目的の場合)。(第9条)
- 電気・電子製品の製造・輸入事業者は、「材質・構造改善指針」に従い、これに基づく評価書を作成し提出しなければならない。自動車の製造・輸入事業者は、材質簡素化や分解容易化などの改善活動を通じて、規定の年次リサイクル可能率を達成しなければならない。(第10条)
- 電気・電子製品・自動車の製造・輸入事業者は、有害物質の含有基準や年次リサイクル可能率の遵守状況を自ら確認・評価し、政令で定める方法で公表しなければならない。(第11条)
- 製造・輸入事業者は、リサイクル事業者などが求めた場合、営業秘密を害さない範囲で製品の構成材質やリサイクル方法等の情報を提供する義務がある。(第12条)
- 製造・輸入事業者・リサイクル事業者等は、廃製品を再使用可能な状態にする場合、有害物質を削減し、リサイクルしやすくするよう努力しなければならない。(第14条)

【廃電気・廃電子製品のリサイクル】
- 指定電気・電子製品を製造・輸入するリサイクル義務生産者は、自社が出荷した製品の廃棄物を回収し、許可を受けた廃棄物リサイクル業者へ引き渡して再資源化するか、またはリサイクル事業共済組合に加入して共同で回収・引渡し・リサイクルを行わなければならない。回収・再資源化に要する費用は義務生産者が負担する。(第15条)
- 環境部長官は人口一人当たりのリサイクル目標量を設定・告示し、これに基づき義務生産者ごとの「リサイクル義務量」を算定する。再資源価値の高い特定製品については、製品別の年間リサイクル量を別途告示できる。義務生産者は定められた方法・基準に従い、製品群別に廃棄物をリサイクルし、気候・生態系変化誘発物質を基準どおり回収・分別・保管・処理しなければならない。(第16条〜16条の3)
- 指定電気・電子製品を一定規模で販売する販売業者は、廃製品を回収する義務がある。共済組合に加入し回収を代行させることもできる。回収後は収集所へ搬送・引渡しし(再使用する場合を除く)、購入者が新品を購入した際には同種の旧製品と包装材を無償回収しなければならない。(第16条の4)
- リサイクル義務生産者・販売業者(共済組合に委任していない者)は、リサイクル義務履行計画書または回収義務履行計画書を提出・承認を受け、履行結果報告書を提出しなければならない。義務未達成の場合、リサイクル・回収できなかった量のリサイクル・回収に要する費用+その100分の30の範囲で賦課金が徴収される。(第17条〜18条の2)
- 国は廃製品を回収・再資源化する事業者や地方自治体に行政・技術・財政支援を行うことができ、電気自動車用廃バッテリー、太陽光廃パネル等を対象とした「未来廃資源拠点収集センター」を設置し、回収・保管・リサイクル業務・性能評価・研究を行わせることができる。(第20条、第20条の4)
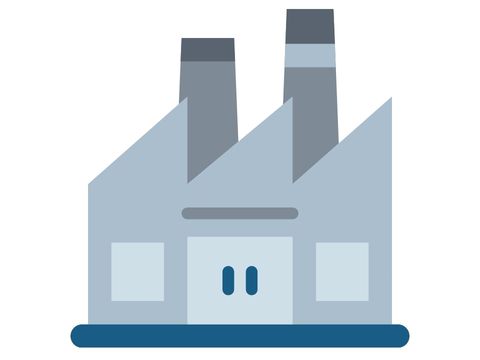
【廃自動車のリサイクル】
- 自動車製造・輸入事業者、解体リサイクル業者、破砕リサイクル業者、破砕残渣リサイクル業者、廃ガス類処理業者は、大統領令で定めるリサイクル比率を遵守しなければならない。処理・リサイクル費用が廃自動車価格を超える場合、製造・輸入業者は廃車希望者から当該車両を無償回収しリサイクルしなければならず、その車両についてもリサイクル比率を遵守する。(第25条)
- 各事業者は廃自動車のリサイクル方法・基準に従ってリサイクルまたはリサイクル容易化を行わなければならない。(第26条)
- 解体・破砕・残渣リサイクル業者および廃ガス処理業者は、廃自動車価格が処理・リサイクル費用を上回る場合、費用を車両価格から控除して充当できる。(第28条)
- 解体業者、破砕業者、残渣リサイクル業者、廃ガス処理業者、および無償回収した製造・輸入業者は、四半期ごとにリサイクル実績等を報告しなければならない。(第31条)
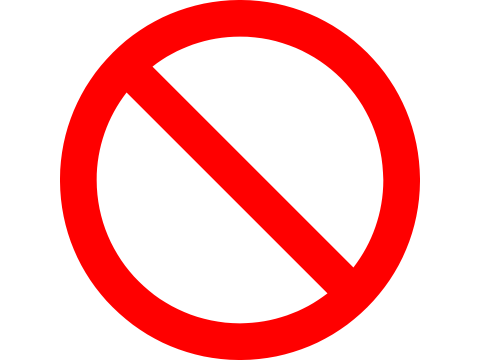
【その他】
- 廃自動車リサイクル業を行う者は、大統領令で定める施設・装備基準を備え、環境部長官に登録しなければならない。気候・生態系変化誘発物質の処理業(廃ガス類処理業)も同様の登録制度・変更手続が適用される。(第32条、第32条の2)
- 義務生産者・販売業者・リサイクル事業者・共済組合・運搬者などは、大統領令の様式で帳簿を備え記録・保存しなければならない。(第36条)
目次
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 他法との関係
第4条 国家と地方自治体の責務
第5条 事業者の責務
第6条 国民の責務
第7条 国際協力の促進
第2章 電気・電子製品と自動車の有害物質使用制限等
第9条 有害物質の使用制限対象・含有基準等
第10条 材質・構造の改善指針等
第11条 有害物質使用制限等の遵守公表
第12条 リサイクル情報の提供と材質・構造等の改善提案等
第13条 リサイクル促進のための勧告の履行状況等の報告
第14条 材質・構造改善に伴う安全性及び耐久性等の確保努力
第3章 廃電気・廃電子製品と廃自動車のリサイクル
第1節 廃電気・廃電子製品
第15条 電気・電子製品リサイクル義務生産者の回収・引渡し・リサイクル義務
第16条 リサイクル目標管理および電気・電子製品リサイクル義務生産者のリサイクル義務量
第16条の2 電気・電子製品リサイクル義務生産者のリサイクル方法と基準
第16条の3 電気・電子製品リサイクル義務生産者の気候・生態系変化誘発物質の回収等
第16条の4 電気・電子製品販売業者の回収及び引渡し義務等
第17条 リサイクルおよび回収義務履行計画書の提出等
第18条 電気・電子製品のリサイクル賦課金の徴収
第18条の2 電気・電子製品の回収賦課金の徴収
第18条の3 電気・電子製品のリサイクル賦課金と回収賦課金等の処理
第18条の4 クレジットカード等による賦課金等の納付
第18条の5 電気・電子製品のリサイクル賦課金等の徴収猶予・分割納付等
第19条 電気・電子製品のリサイクル賦課金等の用途
第20条 廃電気・廃電子製品のリサイクル促進等に対する支援
第20条の4 未来廃資源拠点収集センターの設置・運営
第21条 電気・電子製品リサイクル事業共済協会の設立
第22条 共済協会設立の認可等
第22条の2 是正命令等
第22条の3 認可の取消し
第23条 分担金等
第24条 「民法」の準用
第2節 廃自動車
第25条 廃自動車リサイクル比率の遵守等
第26条 廃自動車のリサイクル方法等
第27条 気候・生態系変化誘発物質等の回収・保管等
第28条 廃自動車の処理・リサイクル費用の充当
第29条 事業者団体の設立
第30条 事業者団体の認可手続等
第31条 廃自動車リサイクル結果の報告等
第4章 リサイクル業の登録等
第32条 廃自動車リサイクル業の登録
第32条の2 廃ガス類処理業の登録
第33条 欠格事由
第33条の2 登録証の発給等
第33条の3 休業・廃業及び再開業の届出
第34条 登録取消し等
第34条の2 過料の賦課・徴収等
第34条の3 廃棄物処理命令
第35条 廃自動車リサイクル業者及び廃ガス類処理業者の地位承継等
第5章 補則
第36条 帳簿の記録・保存
第37条 報告と検査等
第38条 運営管理情報体系の構築・運営
第39条 運搬又はリサイクル者の管理票作成・提出義務
第40条 関係機関の協力
第41条 聴聞
第42条 権限の委任・委託
第6章 罰則
第43条 罰則
第44条 両罰規定
第45条 過料
第46条 過料の賦課・徴収
附則
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 電気・電子製品および自動車の資源循環に関する法律(電子製品等資源循環法) |
| 公布日 | 2023年08月16日 版 |
| 所管当局 | 環境部 |
作成者

株式会社先読