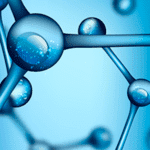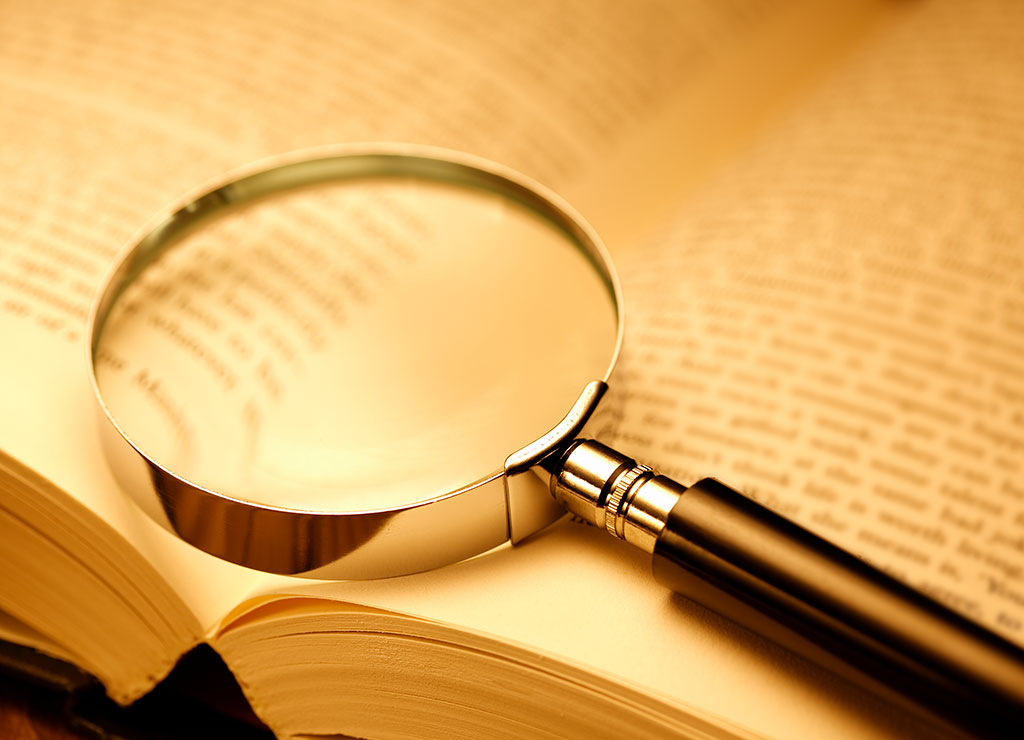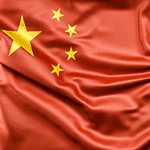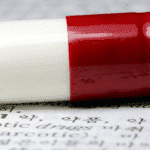| 法令の情報時期:2024年2月 公布版 | ページ作成時期:2025年3月 |
目的

本法は、化学物質の登録・申告および有害性・危害性を有する化学物質の審査・評価・指定に関して規定し、化学物質に関する情報を生成・活用することにより、国民の健康および環境を保護することを目的とする。
概要

本法は化学物質の登録・評価・管理等について規定しており、新しい化学物質や一定量以上の既存の化学物質を製造・輸入する事業者に、事前にその情報を登録または申告する義務を課している。
有害性や危害性の高い化学物質は製造・輸入・使用に許可が必要であり、使用制限や使用禁止についても定められている。また、人や動物への危険性が懸念される重点管理物質を規定量以上含む製品を生産・輸入する場合、事前申告が必要である。
環境部長官は5年ごとに、化学物質の登録・申告、有害性・危害性の審査・評価、製品含有重点管理物質の申告などに関する方法と基本計画を定める。また、化学物質の有害性・危害性を審査・評価する組織として化学物質評価委員会が設置されている。
本法に違反した場合、製造・輸入・使用・販売の中止命令、回収命令などの措置が講じられ、違反内容によって懲役、罰金、課徴金が科される。
注目定義
■ 「화학물질」(化学物質)
| 「化学物質」とは、元素、化合物、及びそれらに人為的な反応を起こして得られた物質と、自然状態で存在する物質を化学的に変形させたり、抽出または精製したものをいう。 |
■ 「혼합물」(混合物)
| 「混合物」とは、二つ以上の物質で構成された物質または溶液をいう。 |
■ 「기존화학물질」(既存化学物質)
| 「既存化学物質」とは、1991年2月2日以前に国内で商業用として流通した化学物質で環境部長官が雇用労働部長官と協議の上で告示した化学物質、または1991年2月2日以降に従来の「有害化学物質管理法」に基づき有害性審査を受けた化学物質で、環境部長官が告示した化学物質をいう。 |
■ 「신규화학물질」(新規化学物質)
| 「新規化学物質」とは、既存化学物質を除く全ての化学物質をいう。 |
■ 「인체급성유해성물질」(人体急性有害性物質)
| 「人体急性有害性物質」とは、単回または短時間の暴露により、短期間内に人の健康に好ましくない影響を及ぼす可能性がある化学物質で、大統領令で定める基準に従い環境部長官が指定・告示したものをいう。 |
■ 「인체만성유해성물질」(人体慢性有害性物質)
| 「人体慢性有害性物質」とは、反復的に曝露される場合や曝露後に潜伏期間を経て人の健康に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質で、大統領令で定める基準に従い環境部長官が指定し告示したものをいう。 |
■ 「생태유해성물질」(生態有害性物質)
| 「生態有害性物質」とは、短期間または長期間の曝露により水生生物など環境に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質で、大統領令で定める基準に従い環境部長官が指定し告示したものをいう。 |
■ 「허가물질」(許可物質)
| 「許可物質」とは、危害性が懸念される化学物質で、環境部長官の許可を得て製造・輸入・使用できるよう、第25条に基づき環境部長官が関係中央行政機関の長と協議し、第7条による化学物質評価委員会の審議を経て告示したものをいう。 |
■ 「제한물질」(制限物質)
| 「制限物質」とは、特定の用途で使用される場合に危害性が高いと認められる化学物質で、その用途での製造・輸入・販売・保管・貯蔵・運搬または使用を禁止するため、第27条に基づき環境部長官が関係中央行政機関の長と協議し、第7条による化学物質評価委員会の審議を経て告示したものをいう。 |
■ 「금지물질」(禁止物質)
| 「禁止物質」とは、危害性が高いと認められる化学物質で、すべての用途での製造・輸入・販売・保管・貯蔵・運搬または使用を禁止するため、第27条に基づき環境部長官が関係中央行政機関の長と協議し、第7条による化学物質評価委員会の審議を経て告示したものをいう。 |
■ 「중점관리물질」(重点管理物質)
| 「重点管理物質」とは、次のいずれかに該当する化学物質のうち、危害性が懸念され、第7条に基づく化学物質評価委員会の審議を経て環境部長官が定め告示するものをいう。人または動物にがん、突然変異、生殖機能異常または内分泌系障害を引き起こす、またはそのおそれがある物質、人または動植物の体内に高い蓄積性があり、環境中に長期間残留する物質、人に曝露された場合、肺、肝臓、腎臓などの臓器に損傷を引き起こすおそれのある物質、人または動植物に対して、上記の物質と同等またはそれ以上の深刻な危害を与えるおそれのある物質。 |
■ 「유해성미확인물질」(有害性未確認物質)
| 「有害性未確認物質」とは、第10条に基づき環境部長官に登録・届出されたものの、有害性に関する資料が存在しないなどの理由により当該化学物質の有害性を確認することが困難な物質で、環境部令で定める基準に該当する物質をいう。 |
■ 「유해성」(有害性)
| 「有害性」とは、化学物質の毒性などにより、人の健康や環境に悪影響を及ぼす化学物質固有の性質をいう。 |
■ 「위해성」(危害性)
| 「危害性」とは、有害性のある化学物質が曝露された場合に、人の健康や環境に被害を及ぼすおそれの程度をいう。 |
■ 「사업자」(事業者)
| 「事業者」とは、営業を目的として化学物質を製造・輸入・使用・販売する者をいう。 |
■ 「제품」(製品)
| 「製品」とは、「消費者基本法」第2条第1号に定める消費者が使用する物品またはその部品や付属品で、消費者に化学物質の曝露を引き起こす可能性のある製品として、混合物で構成された製品、または化学物質が使用過程で流出せず特定の固体形態で一定の機能を果たす製品をいう。 |
■ 「하위사용자」(川下使用者)
| 「川下使用者」とは、営業活動の過程で化学物質または混合物を使用する者(法人の場合は国内に設立されたものに限る)をいう。ただし、化学物質または混合物を製造・輸入・販売する者および消費者は除く。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
「原子力安全法」第2条第5号に定める放射性物質
「薬事法」第2条第4号および第7号に定める医薬品および医薬部外品
「麻薬類管理に関する法律」第2条第1号に定める麻薬類
「化粧品法」第2条第1号に定める化粧品および化粧品に使用する原料
「農薬管理法」第2条第1号および第3号に定める農薬および原剤
「肥料管理法」第2条第1号に定める肥料
「食品衛生法」第2条第1号・第2号・第4号・第5号に定める食品、食品添加物、器具および容器・包装
「飼料管理法」第2条第1号に定める飼料
「銃砲・刀剣・火薬類等取締法」第2条第3項に定める火薬類
「軍需品管理法」第2条および「防衛事業法」第3条第2号に定める軍需品(「軍需品管理法」第3条に定める通常品は除く)
「健康機能食品に関する法律」第3条第1号に定める健康機能食品
「医療機器法」第2条第1項に定める医療機器
「衛生用品管理法」第2条第1号に定める衛生用品
「生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律」第3条第7号・第8号に定める殺生物物質および殺生物製品
「環境にやさしい農漁業の育成および有機食品等の管理・支援に関する法律」第2条第4号・第5号・第5号の2・第6号および第7号に定める有機食品、非食用有機加工品、無農薬原料加工食品、有機農漁業資材および許容物質
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

事業者は、製造・輸入する化学物質の有害性・危害性に関する情報を積極的に生産・交換・活用し、国の施策に協力する義務を負う。また、これらの化学物質の使用を減らし、代替物質や新技術の開発に努めなければならない。
年間1トン以上の新規化学物質または既存化学物質を製造・輸入する場合、事前に環境部長官に登録しなければならない。(第10条第1項)これに該当しない場合でも、人の健康や環境に深刻な被害を及ぼすおそれが大きいと認められる、または年間国内総製造・輸入量が大統領令で定める基準を超え評価委員会の審議を経て環境部長官が指定・告示した化学物質を製造・輸入しようとする場合は、事前登録が必要である。(第10条第5項)
既存化学物質については、製造・輸入量や有害性に応じて登録の猶予期間が設けられているが、猶予期間中に製造・輸入する場合は、事前に環境部長官に申告する必要がある 。(第10条第2項、第3項)
年間1トン未満の新規化学物質を製造・輸入する場合や、特定の条件を満たす新規化学物質については申告が必要である。 (第10条第4項)
機械に内蔵されて輸入される化学物質、試験運転用の機械または装置類とともに輸入される化学物質、特定の固体形態で一定の機能を果たす製品に含まれており、その使用過程で流出しない化学物質、その他、環境部長官が指定・告示する化学物質は、第10条に定められた登録・届出を行わずに製造・輸入することができる。(第11条)
登録または申告した内容に変更があった場合は、環境省令で定められた範囲に応じて変更登録または変更申告を行う必要がある 。(第12条)
登録・申告を行っていない、または登録等免除確認を受けていない化学物質は、製造・輸入・使用・販売が禁止されている。 (第13条)

登録・申告を行う際には、製造者・輸入者の情報、化学物質情報、有害性に関するデータなど、環境省令で定められた資料を提出する必要がある。 有害性に関するデータは、原則として指定された試験機関で実施された試験結果を提出する 。(第14条)
既存化学物質の登録においては、資料を共同で提出することが原則であるが、登録猶予期間内に登録しようとする場合、営業秘密などの正当な理由がある場合は、環境部長官の確認を得て個別に提出することができる。(第15条)
脊椎動物実験を最小限に抑えるため、既存の脊椎動物試験データが存在する場合は、所有者の同意を得てそのデータを利用する。(第17条)

重点管理物質および有害性審査・危害性評価により危害性があると懸念される化学物質は、製造・輸入・使用前に許可が必要な「許可物質」に指定される。ただし、危害性が低く許可なしで製造・輸入・使用できる用途が併せて指定されることがある。(第25条)
審査・評価の結果、危害性があると認められる場合や国際機関等が危害性を認める場合などに、当該化学物質は制限物質または禁止物質として指定される。これらの化学物質の名称および指定予定時期などは、官報またはホームページを通じて予告される。(第27条)
特に危害性が懸念される重点管理物質が一定量以上(製品1個あたり0.1重量パーセント超かつ製品全体の年間使用量が1トン超)含まれる製品を生産または輸入する場合は、事前に環境部長官に申告する必要がある。(第32条)

登録・申告された化学物質、登録猶予期間中の有害性物質、許可・制限・禁止物質、有害性未確認物質に該当する化学物質や混合物を他の事業者に譲渡する際には、その登録番号、名称、有害性・危害性に関する情報などを提供しなければならない。(第29条)
重点管理物質を含む製品を譲渡する際にも、重点管理物質の名称、用途、条件などの情報を提供する必要がある。(第35条)

化学物質や混合物を製造・輸入する者は、下位ユーザーや販売者から使用・販売している化学物質の用途・暴露情報、使用量・販売量・安全使用状況などの情報提供を求められた場合、これに応じなければならない。(第30条)
環境部長官から必要な報告や資料の提出を求められた場合、また関係公務員が施設や事業場に立ち入り化学物質を採取したり、書類や設備を検査したりする場合には、これに応じなければならない。(第43条)
化学物質の登録・申告、登録等免除確認に関する書類、製造・輸入・販売・使用に関する情報は、環境省令で定められた規定に従って記録・保管しなければならない。(第44条)
提出する情報の中に秘密にしたい成分等がある場合は、環境部長官に資料保護を申請することができる。 (第45条)
登録・申告を行った事業者、登録等免除確認を受けた事業者の地位を相続・譲渡・合併により承継した場合、承継した日から1ヶ月以内にその事実を環境部長官に届け出なければならない。(第45条の2)
目次
第一章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 適用範囲
第4条 国家の責務
第5条 事業者の責務
第6条 化学物質の評価等に関する基本計画
第7条 化学物質評価委員会
第二章 化学物質の登録
第10条 化学物質の登録等
第11条 化学物質の登録等免除
第12条 変更登録・変更申告等
第13条 登録義務等不履行に対する措置等
第14条 化学物質の登録等申請時提出資料
第15条 既存化学物質の登録申請時資料提出方法
第16条 既存登録申請資料の共同活用
第16条の2 脊椎動物試験の最小化原則
第17条 脊椎動物試験資料に関する特例
第17条の2 課徴金の賦課
第17条の3 課徴金の徴収および滞納処分等
第三章 化学物質の有害性審査および危害性評価
第18条 有害性審査
第19条 有害性評価等
第19条の2 使用料
第19条の3 申告時提出された化学物質資料の検討等
第20条 人体急性有害性物質等の指定
第21条 有害性審査結果の公開
第22条 試験機関の指定等
第23条 試験機関の指定取消等
第24条 危害性評価
第四章 許可物質等の指定及び変更
第25条 許可物質の指定
第26条 許可物質指定の解除等
第27条 制限物質または禁止物質の指定等
第28条 制限物質または禁止物質指定の解除等
第五章 化学物質の情報提供
第29条 化学物質の情報提供
第30条 川下使用者等の情報提供
第31条 化学物質の情報提供のための通知等
第六章 化学物質含有製品の管理
第32条 製品に含まれる重点管理物質の申告
第33条 製品に含まれる重点管理物質の変更申告等
第35条 製品に含まれる化学物質の情報提供
第七章 補則
第38条 国外製造・生産者が選任した者による登録申請等
第39条 化学物質情報処理システムの構築・運営
第40条 グリーンケミカルセンターの指定・運営
第41条 グリーンケミカルセンターの指定取消等
第42条 化学物質情報の公開
第42条の2 中小企業の化学物質登録・評価等に関する支援
第43条 報告と検査等
第43条の2 資料提供の要請
第44条 書類の記録及び保存
第45条 資料の保護
第45条の2 権利・義務の承継
第45条の3 資料流出事故
第46条 手数料
第47条 聴聞
第48条 権限の委任・委託
第48条の2 罰則適用における公務員擬制
第八章 罰則
第50条 罰則
第51条 罰則
第52条 罰則
第53条 両罰規定
第54条 過料
附則
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法、K-REACH) |
| 公布日 | 2024年2月 |
| 所管当局 | 環境部 |
作成者