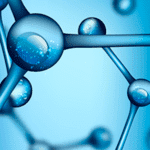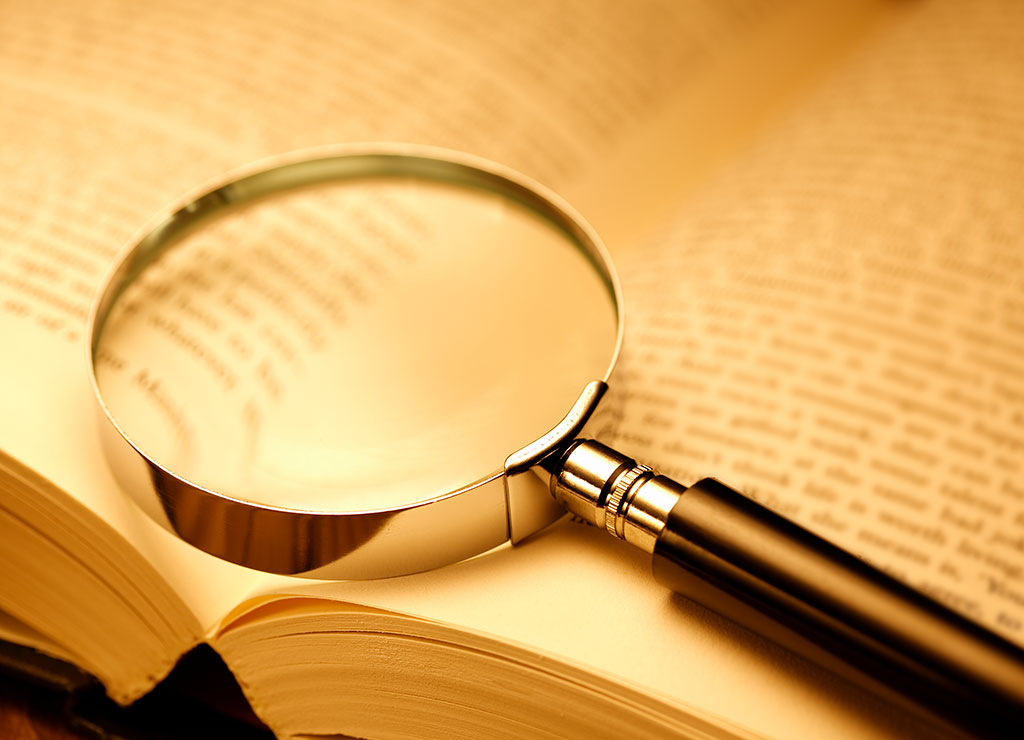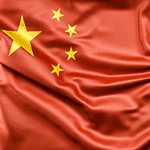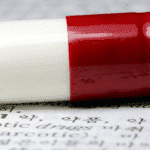| 法令の情報時期:2023年03月 版 | ページ作成時期:2025年06月 |
目的

本法は、廃棄物の発生を抑制しリサイクルを促進するなど、資源を循環的に利用することにより、環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
概要

本法は廃棄物発生抑制とリサイクル促進のため、製品の製造・輸入・販売事業者から消費者、自治体、リサイクル事業者まで、廃棄物の発生源や資源循環に関わる主体を網羅しながら、必要な規制や支援について定めている。
包装材の素材・構造について発生抑制のための規制や基準を定め、使い捨て用品の使用抑制に関する事項や、無包装販売、リユース容器事業には国家や自治体が資金支援できるとしている。
廃棄物排出者や自治体に対する分別保管・分別収集の義務、リサイクルセンター・特別会計を設ける仕組み、製造・輸入事業者に対する回収・リサイクル義務などが定められている。固形燃料については別途、輸入・製造申告、品質検査、使用許可、定期検査などの規制や遵守事項がある。
製造者等は製品・包装材ごとの共済組合、組合による流通支援センターを設立することができ、これによるリサイクルへの費用補填制度を整備している。
リサイクル産業への資金支援、リサイクル製品の規格・品質基準設定、再生原料使用比率の表示・確認・義務化や、リサイクル団地の造成支援やリサイクル施設の設置などの促進基盤を構築している。
固形燃料の不正な輸入・販売等には3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金、その他の違反についても懲役、罰金、過料などの罰則が定められている。
注目定義
■ 「リサイクル可能資源」(재활용가능자원)
| 「リサイクル可能資源」(재활용가능자원)とは、使用済み、または使用されずに廃棄された後に回収された物品および副産物のうち、再使用・再生利用が可能なもの(回収可能なエネルギーおよび廃熱を含むが、放射性物質および放射性物質によって汚染された物質は除く)をいう。 |
■ 「指定副産物」(지정부산물)
| 「指定副産物」(지정부산물)とは、副産物のうち、その全部または一部をリサイクルすることが資源の効率的な利用に特に必要とされ、大統領令で定める副産物をいう。 |
■ 「再生利用」(재생이용)
| 「再生利用」(재생이용)とは、リサイクル可能資源の全部または一部を原料として再び使用すること、または再使用できるようにすることをいう。 |
■ 「再生原料」(재생원료)
| 「再生原料」(재생원료)とは、リサイクル可能資源の全部または一部を再生利用した原料で、環境部令で定めるものをいう。 |
■ 「リサイクル製品」(재활용제품)
| 「リサイクル製品」(재활용제품)とは、リサイクル可能資源を利用して製造された製品で、環境部令で定める製品をいう。 |
■ 「リサイクル施設」(재활용시설)
| 「リサイクル施設」(재활용시설)とは、リサイクル可能資源またはリサイクル製品を製造・加工・組立・整備・収集・運搬・保管するために使用される装置・機器・設備などで、環境部令で定めるものをいう。 |
■ 「リサイクル産業」(재활용산업)
| 「リサイクル産業」(재활용산업)とは、リサイクル可能資源またはリサイクル製品を製造・加工・組立・整備・収集・運搬・保管する、またはリサイクル技術を研究・開発する産業で、大統領令で定める業種をいう。 |
■ 「生分解性樹脂製品」(생분해성수지제품)
| 「生分解性樹脂製品」(생분해성수지제품)とは、「環境技術および環境産業支援法」第17条に基づき環境ラベルの認証を受けた、または対象製品別の認証基準に合致する製品であり、環境部令で定める製品をいう。 |
■ 「材質・構造改善対象製品」(재질ㆍ구조개선 대상제품)
| 「材質・構造改善対象製品」(재질ㆍ구조개선 대상제품)とは、使用済み、または使用されずに廃棄された後に回収され、その全部または一部をリサイクルすることが資源の効率的利用に特に必要であり、容易にリサイクルできるよう製品の構造や材質を改善する必要がある製品であって、大統領令で定める製品をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外は特に明記されていないが、資源の節約、廃棄物発生抑制およびリサイクルに関して本法に定めのない事項については、「循環型経済社会への転換促進法」および「廃棄物管理法」が適用される。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

【資源節約・発生抑制】
- 指定製品の製造・輸入・販売者は、包装材質・包装方法基準および合成樹脂包装材の年次削減基準を遵守しなければならない。(第9条)
- 第16条第1項の再利用義務生産者は、包装材の材質・色・リサイクル容易性などの材質・構造基準を遵守しなければならない。また、包装材の材質・構造評価を受け、その評価結果を包装材に表示する義務がある。(第9条2〜4)
- 集団給食所・食品接客業、特定の食品製造・加工業、大規模宿泊業など指定の業種・施設を営む事業者は、生分解性樹脂製以外の使い捨て用品の無償提供が禁止されている。ただし、集団給食所や食品接客業者以外の場所で消費する目的の場合や、自動販売機での販売などは例外とされている。(第10条)
- 使い捨て袋や紙袋の販売事業者は、その販売代金を、顧客が使用済みの使い捨て袋・紙袋を返却した際の現金返金、マイバッグ利用時の現金値引き、マイバッグの製作・配布等の用途に充てるよう努めなければならない。(第10条の2)
- 国家や自治体は、無包装販売の事業者、リユース容器を回収・洗浄し再供給する事業者には資金融資等の支援を行う。(第10条の3)

【廃棄物負担金】
- 特定大気有害物質・特定水質有害物質・急性/慢性人体有害性物質・生態有害性物質のいずれかを含む、またはリサイクル困難で廃棄物管理上の問題を生じ得る製品・材料・容器を製造・輸入する者(受託製造の場合は発注者)は、毎年「廃棄物負担金」を賦課・徴収される。(第12条①)
- 次に該当すると立証できる場合は負担金の対象外となる。第16条に規定する回収・リサイクル義務対象製品・包装材および生分解性樹脂製品、プラスチック製品等で一定比率以上を回収・リサイクル可能とし、かつ環境部長官との自主協約(最長5年)を締結・履行したもの、その他大統領令で定める製品等。(第12条②)
- 負担金額の算定・納付は品目ごとに種類・規格によって、大統領令で定める基準で規定する。(第12条③)
- 負担金および加算金は「環境政策基本法」による環境改善特別会計の歳入となる。徴収業務を韓国環境公団等に委託する場合、徴収額の一部を徴収費用として交付できる。(第12条⑥⑦)
- 負担金納付者は、製品・材料・容器の出庫または輸入実績資料を環境部長官へ提出しなければならない。(第12条⑧)
- 天災地変や災害で損失が発生した場合、事業に損失を被った場合などで環境部長官が認めた場合は徴収が猶予される。(第12条の2)
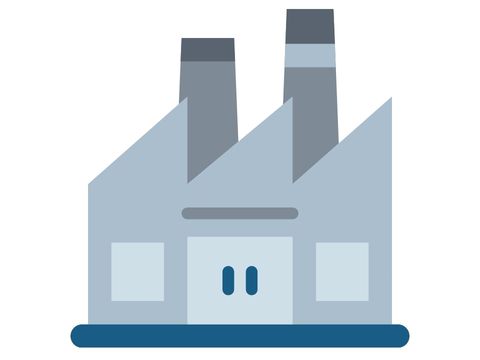
【廃棄物の分別・収集・資源循環促進】
- 指定された土地、建物の所有者・占有者・管理者は、廃棄物のうちリサイクル可能なものを環境部令で定める基準に従って再資源化するか、種類・性状・状態ごとに分別保管しリサイクル可能な状態を確保しなければならない。(第12条の3①)
- 環境部長官はリサイクル可能な資源の分類・保管・収集など、分別回収に関する指針を定めることができる。自治体は分別回収を支援し、指針に従い毎年、リサイクル可能資源の発生量・分別回収量を調査し公表しなければならない。(第13条)
- 自治体は中古品の交換や大型廃棄物のリサイクル促進のため、区域ごとに少なくとも一箇所のリサイクルセンターを設置・運営しなければならない。環境部長官はリサイクルセンターの主体に対し財政的・技術的支援を行うことができる。(第13条の2)
- 自治体では、リサイクル資源の回収資金を確保と効率的運用のため「リサイクル可能資源管理特別会計」を設置することができる。特別会計は回収資源の流通支援センターへの売却収益、リサイクルセンターの販売収益、過料やその他の収益で構成される。(第13条の3)
- 分別排出表示が必要と指定された製品・包装材を製造・輸入・販売する者は、指針に従い、当該製品・包装材に分別排出表示を行わなければならない。(第14条)
- 製造者等は、流通済み製品が廃棄物となった場合に、部品を回収し新たな製品の製造に活用または再使用できるよう努めなければならない。政府はそのための技術支援や必要な措置を講ずる。(第15条)
- リユース可能な容器を用いて指定製品を製造・輸入する場合、または使い捨てカップを大量に排出する事業者が使い捨てカップで指定製品を販売する場合、出庫・輸入・販売価格とは別に「資源循環保証金」を製品価格に上乗せしなければならない(リユース容器の場合、保証金を付すかどうかは製造者・輸入者が選択可)。また容器等には保証金返還についての文言や再使用・再資源化表示を行わなければならない。(第15条の2)
- 保証金対象事業者は、回収・選別・保管・リサイクル・再資源化に要する「取扱手数料」または「処理支援金」を負担する義務がある。(第15条の2)

【廃棄物のリサイクル促進】
- 製造・輸入・販売段階で多量に廃棄物が発生しうる、または材質・構造・回収体制の改良によりリサイクル促進が期待できる製品・包装材について、その製造・輸入・販売を行うリサイクル義務生産者は、流通させた製品・包装材から生じた廃棄物を回収しリサイクルしなければならない。業種や規模によっては義務対象の免除となる。(第16条)
- リサイクル義務生産者の製品・包装材について、年間出庫量、リサイクル可能資源の分別収集量、回収・再資源化実績等から、製品・包装材ごとにリサイクル義務率が定められ、リサイクル義務量は算出基準に従い決定される。(第17条)
- 第16条の分担金控除を受けようとするリサイクル義務生産者、リサイクル事業共済組合、保証金対象事業者は、回収・リサイクル義務履行計画書を環境部長官へ提出し、承認を受けなければならない。(第18条)
- 第16条のリサイクル義務不履行者や、組合員の義務を代行しないリサイクル事業共済組合には、未リサイクル量のリサイクル費用にその100分の30以下の金額を上乗せした額が「リサイクル賦課金」として徴収される。天災・経営危機等で期限内納付が困難と認められる場合は徴収猶予や分割納付が許可される。(第19条)
- リサイクル指定事業者は、製品種別リサイクル資源の利用目標と促進措置、2.資源利用計画の策定とリサイクル法案事項、3.資源利用に関する記録・管理、4.エネルギー回収と廃熱利用促進の4指針に従わなければならない。(第23条)
- 指定副産物の排出事業者は、用途別リサイクル方法、2.利用促進計画の策定・実施、3.分別・破砕等の処理、4.環境配慮型管理の4指針に従わなければならない。(第25条)
- 廃棄物由来の固形燃料製品を輸入する者は、環境部長官へ届出を行う義務がある。製造を行うことができるのは、「廃棄物管理法」第25条第5項第6号の最終リサイクル業許可、又は同項第7号の総合リサイクル業許可を受けた者に限られる。また、輸入・製造しようとする固形燃料製品は品質基準検査、製品への品質表示が必要である。(第25条の4〜6)
- 固形燃料製品の輸入・製造・使用者は、保管や製造・使用施設の運転時に生じる粉じん飛散防止などの環境管理に関する基準を遵守しなければならない。また使用者は、ダイオキシン排出許容基準を遵守しなければならない。(第25条の9)
- 環境部長官は、廃資源エネルギーの生産・使用量、固形燃料製品の輸入・使用量、関連施設、品質検査・表示結果等を総合管理するシステムを設置・運営する。固形燃料製品の輸入・製造・使用、また埋立ガス・バイオガス・焼却余熱回収・ガス化発電施設などを運営する者は、所定情報をシステムへ入力しなければならない。(第25条の14)
- 環境部長官は、固形燃料製品の品質検査・格付け、表示適正確認、製造・使用施設の定期検査や利用実態・輸入動向調査、技術支援・研究開発など、廃資源エネルギー活性化に必要な業務を担う廃資源エネルギーセンターを設置・運営できる。センター運営は韓国環境公団への委託が可能である。(第25条の15)

【リサイクル事業共済組合・リサイクル可能資源流通支援センター】
- リサイクル義務生産者は、リサイクル義務履行のため、環境部長官の認可を受け、製品別および包装材リサイクル事業共済組合を設立することができる。(第27,28条)
- 組合は、製品・包装材の廃棄物を回収・リサイクルするために、環境部長官の認可を受け、リサイクル可能資源流通支援センターを共同で設立することができる。(第28条の2)
- 組合および流通支援センターは、回収・リサイクル義務の代行と分担金徴収、当該義務遂行費用の支援、技術研究開発と情報収集、広報・教育、関連システム運用、国・自治体受託業務、市況悪化時の公益的需給安定事業など、回収・リサイクル促進事業を実施できる。(第28条の7)
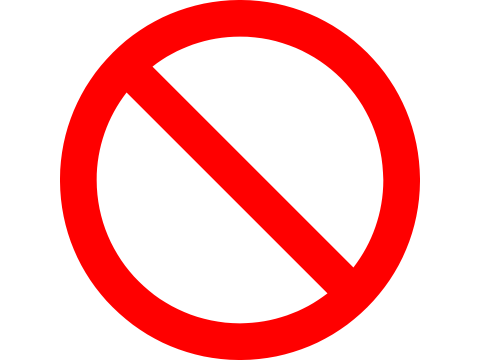
【その他】
- 一定比率以上の再生原料を使用した製品・容器について、その比率を表示したい製造者等は、環境部令で定める手続により環境部長官へ使用比率確認を申請し、確認を得た後にのみ当該比率を表示できる。(第33条の2 ※25年9月施行)
- 指定製品・容器の製造者等は、規定比率以上のプラスチック再生原料を当該製品・容器に使用する義務を負う。(第33条の3 ※25年9月施行)
- 国家・地方自治団体又は大統領令で定める者は、リサイクル産業の育成と競争力向上のためにリサイクル団地を造成することができ、国または地方自治体が供給する工場用地にリサイクル事業者が優先的に入居できるよう、必要な措置を講ずることができる。(第34条)
- 環境部長官は、リサイクル市場の安定と促進のため、リサイクル可能資源等の市場情報を収集・分析し、適正な安定化措置を遂行するリサイクル市場管理センターを設置・運営することができる。(第34条の10)
- リサイクル義務生産者、組合、リサイクル製品の製造者、リサイクル可能資源の収集業者など大統領令で定める者は、環境部長官の許可を得てリサイクル促進のための「資源リサイクル協会」を設立することができる。(第35条)
目次
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 他法との関係
第2章 資源の節約とリサイクルの促進等
第1節 資源の節約と廃棄物の発生抑制等
第8条 資源の節約等
第9条 包装廃棄物の発生抑制
第9条の2 包装材の素材・構造基準等
第9条の3 中断命令に代わる課徴金
第9条の4 包装材の素材・構造評価等
第10条 使い捨て用品の使用抑制等
第10条の2 使い捨て袋・紙袋の販売代金の用途
第10条の3 財政的支援等
第11条 開発事業における資源循環性の考慮等
第12条 廃棄物負担金
第12条の2 廃棄物負担金の徴収猶予・分割納付等
第2節 廃棄物の分別・回収および資源の循環促進等
第12条の3 廃棄物排出者の分別保管等
第13条 リサイクル可能資源の分別回収
第13条の2 リサイクルセンターの設置・運営等
第13条の3 リサイクル可能資源管理特別会計の設置
第14条 分別排出表示
第15条 部品等の再使用促進
第15条の2 空容器・使い捨てカップの資源循環促進
第15条の3 資源循環保証金残額の用途
第15条の4 資源循環保証金未払い小売業者等の通報・報償
第15条の5 資源循環保証金管理委員会
第15条の6 資源循環保証金管理センターの設立
第3節 廃棄物のリサイクル促進等
第16条 製造業者等のリサイクル義務
第17条 リサイクル義務率
第17条の2 リサイクル義務履行認証
第18条 回収およびリサイクル義務履行計画書の提出等
第19条 リサイクル賦課金の徴収等
第19条の2 クレジットカード等による負担金等の納付
第20条 廃棄物負担金とリサイクル賦課金の用途
第23条 リサイクル指定事業者の遵守事項
第25条 指定副産物排出事業者の遵守事項
第25条の2 リサイクルの勧告および措置命令
第25条の3 エネルギー回収施設の設置・運営等
第25条の4 固形燃料製品の輸入・製造申告等
第25条の5 固形燃料製品の品質検査
第25条の6 固形燃料製品の品質表示
第25条の7 固形燃料製品の使用許可等
第25条の8 固形燃料製品製造・使用施設の定期検査
第25条の9 固形燃料製品の輸入者・製造者および使用者の遵守事項
第25条の10 固形燃料製品の輸入・製造禁止命令等
第25条の11 禁止命令に代わる課徴金
第25条の12 固形燃料製品の処理等
第25条の13 権利・義務の承継等
第25条の14 廃資源エネルギー総合情報管理システムの構築・運営等
第25条の15 廃資源エネルギーセンター
第26条 韓国廃資源エネルギー協会
第3章 リサイクル事業共済組合およびリサイクル可能資源流通支援センター
第27条 リサイクル事業共済組合の設立
第28条 組合設立の認可手続等
第28条の2 リサイクル可能資源流通支援センターの設立等
第28条の3 流通支援センター設立の認可手続等
第28条の4 是正命令等
第28条の5 認可の取消し
第28条の6 組合および流通支援センターの経営公開
第28条の7 組合および流通支援センターの事業
第28条の8 組合および流通支援センターの定款記載事項
第28条の9 組合および流通支援センターの事業予算および決算等
第29条 分担金等
第30条 「民法」の準用
第4章 資源の節約およびリサイクル促進のための基盤整備
第31条 リサイクル産業育成のための資金等の支援
第33条 リサイクル製品の規格・品質基準
第33条の2 再生原料使用比率の確認および表示(25年9月施行)
第33条の3 プラスチック再生原料使用義務(25年9月施行)
第33条の4 再生原料使用製品・容器の購買促進(25年9月施行)
第34条 リサイクル団地の造成等
第34条の2 リサイクル団地の造成支援
第34条の3 国・公有財産の貸与・使用等
第34条の4 公共リサイクル基盤施設の設置
第34条の5 リサイクル促進のための施設の設置等
第34条の6 資源の節約およびリサイクル促進に関する評価基準と指標等
第34条の7 資源の節約およびリサイクル促進情報の提供等
第34条の8 自主協約の締結
第34条の10 リサイクル市場管理センターの設置・運営
第5章 附則
第35条 資源リサイクル協会
第36条 報告および検査等
第36条の2 運営管理情報体系の構築・運営
第36条の3 リサイクル義務生産者等の管理表作成・提出義務
第37条 関係機関の協力
第38条 権限の委任・委託
第38条の2 聴聞
第6章 罰則
第39条 罰則
第39条の2 罰則
第40条 両罰規定
第41条 過料
附則
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 資源の節約とリサイクル促進に関する法律(資源リサイクル法) |
| 公布日 | 2023年03月28日 版 |
| 所管当局 | 環境部 |
作成者

株式会社先読