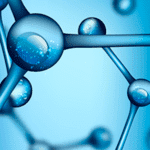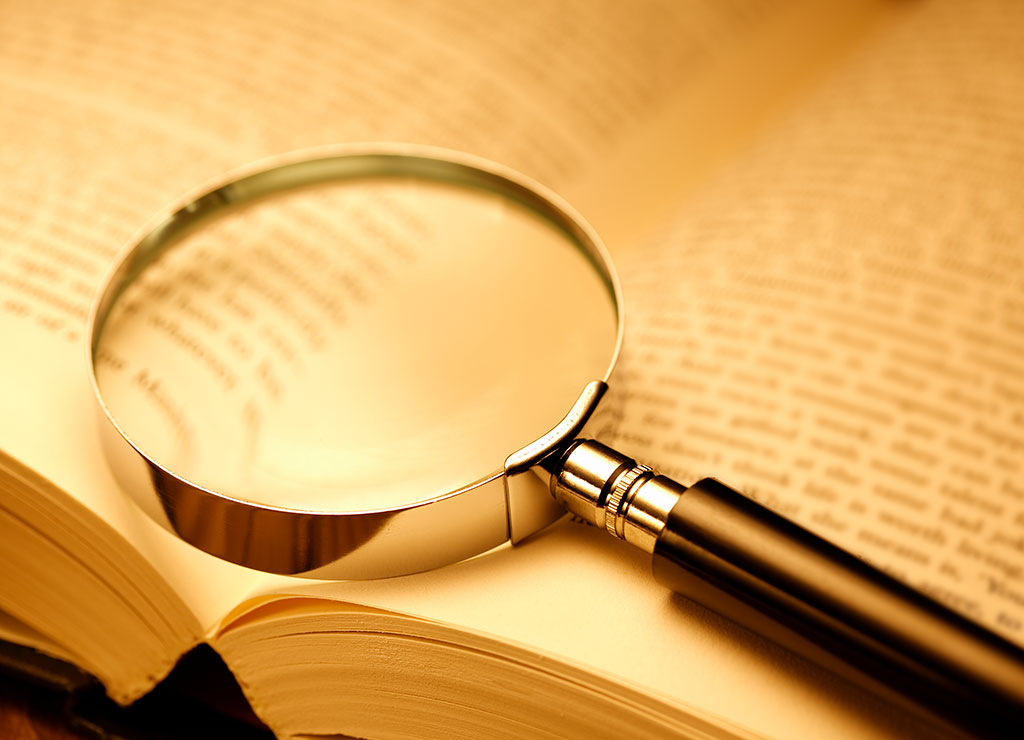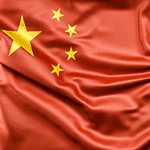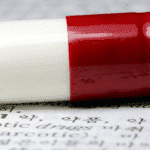| 法令の情報時期:2025年03月 版 | ページ作成時期:2025年06月 |
目的

本法は、廃棄物の発生を最大限抑制し、発生した廃棄物を環境に配慮して処理することにより、環境の保全と国民生活の質の向上に寄与することを目的としている。
概要

本法は、廃棄物発生抑制、リサイクル、環境保全と国民の健康保護、汚染者責任などの原則を掲げ、適正に管理・処理されるよう国・地方自治体・事業者・国民それぞれの責務を明確にしている。
生活環境や生態系に害を及ぼさないことなど、廃棄物のリサイクルに関する遵守事項、禁止事項を定めている。
廃棄物の適切な管理に必要な規定が設けられており、廃棄物の処理業者、排出事業者、処理施設の設置、分析、リサイクル評価など、排出から処理までに関与する者は定められた許可、登録、届出、記録、報告等の義務を負う。
特定の廃棄物については、排出、保管、収集・運搬、リサイクル、処分の方法と基準が詳細に定められている。
廃棄物の不適正処理や違反行為に対しては、行政措置や懲役、罰金などの罰則が定められている。
注目定義
■ 「廃棄物」(폐기물)
| 「廃棄物」(폐기물)とは、ごみ、焼却残渣、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリおよび動物の死体など、人の生活または事業活動において必要でなくなった物質をいう。 |
■ 「生活廃棄物」(생활폐기물)
| 「生活廃棄物」(생활폐기물)とは、事業場廃棄物以外の廃棄物をいう。 |
■ 「事業場廃棄物」(사업장폐기물)
| 「事業場廃棄物」(사업장폐기물)とは、「大気環境保全法」、「水環境保全法」または「騒音・振動管理法」により排出施設を設置・運営する事業場や、その他大統領令で定める事業場から発生する廃棄物をいう。 |
■ 「指定廃棄物」(지정폐기물)
| 「指定廃棄物」(지정폐기물)とは、事業場廃棄物のうち、廃油・廃酸など周辺環境を汚染するおそれがある、または医療廃棄物など人体に危害を及ぼすおそれのある有害な物質で、大統領令で定める廃棄物をいう。 |
■ 「医療廃棄物」(의료폐기물)
| 「医療廃棄物」(의료폐기물)とは、保健・医療機関、動物病院、試験・検査機関等から排出される廃棄物のうち、人体への感染等の危害を及ぼすおそれのある廃棄物および人体組織などの摘出物、実験動物の死体など、保健・環境保護上特別な管理が必要と認められる廃棄物で、大統領令で定める廃棄物をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

■ 次に該当する物質については本法が適用されない。
- 「原子力安全法」に基づく放射性物質、これにより汚染された物質
- 容器に入っていない気体状の物質
- 「水環境保全法」に基づく水質汚染防止施設に流入または公的水域に排出される廃水
- 「家畜ふん尿の管理および利用に関する法律」に基づく家畜ふん尿
- 「下水道法」に基づく下水およびふん尿
- 「家畜伝染病予防法」第22条第2項、第23条、第33条および第44条が適用される家畜の死体、汚染された物品、輸入禁止物品および検疫不合格品
- 「水産生物疾病管理法」第17条第2項、第18条、第25条第1項各号、第34条第1項が適用される水産動物の死体、汚染された施設または物品、輸入禁止物品および検疫不合格品
- 「軍需品管理法」第13条の2により廃棄される弾薬
- 「動物保護法」第69条第1項に基づく動物葬祭業の許可を受けた者が設置・運営する動物葬祭施設で処理される動物の死体
※本法に基づく廃棄物の海域投棄については、「海洋廃棄物および海洋汚染堆積物管理法」に従う。
※「水産副産物再利用促進に関する法律」に基づく水産副産物が他の廃棄物と混合された場合にはこの法律を適用し、他の廃棄物と混合されず水産副産物のみを排出・収集・運搬・再利用する場合にはこの法律を適用しない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

【廃棄物管理の基本原則】
- 事業者は製品の生産方法等を改善し、廃棄物発生抑制、リサイクル、排出の最小化に努めなければならない。
- 廃棄物を排出する場合には、周辺環境や住民の健康に害を及ぼさないよう、事前に適切な措置を講じる。
- 廃棄物処理過程では、量や有害性を減少させるなど、環境保全、国民の健康保護に適した方法で処理しなければならない。
- 廃棄物によって環境汚染を引き起こした者は、汚染された環境を復元し、被害の救済費用を負担しなければならない。
- 国内で発生した廃棄物は可能な限り国内で処理し、廃棄物の輸入は極力抑制しなければならない。
- 廃棄物は、焼却や埋立などの処分を行う前に優先的にリサイクルし、資源生産性の向上に努めなければならない。(第3条の2)

【廃棄物の排出・処理】
- すべての国民は環境の清潔保持、廃棄物の削減・資源化に努める義務があり、土地や建物の所有者・管理者はその場所の清掃維持に努め、自治体が定める計画に従って大掃除を行わなければならない。(第7条)
- 特別自治市場、特別自治道知事、市長・郡守・区庁長または公園・道路等施設の管理者が廃棄物の収集のために設けた場所や設備以外の場所に生活廃棄物を廃棄してはならない。(第8条)
- 廃棄物を処理しようとする者は、大統領令で定める基準と方法に従わなければならない。ただし、リサイクルしやすい形に加工された「中間加工廃棄物」については、第13条の2のリサイクルに関する原則および遵守事項に従い緩和された処理基準・方法が大統領令で定められる。医療廃棄物については、第25条の2第6項に定める検査に合格した専用容器を使用し処理しなければならない。(第13条)

【廃棄物のリサイクル】
- リサイクルの原則および遵守事項は以下のとおり。(第13条の2)
① 何人も、次の各号に違反しない場合には廃棄物を再利用することができる。
- 飛散性粉塵や悪臭の発生、揮発性有機化合物や大気汚染物質などが排出されて生活環境に害を及ぼさないこと
- 浸出水や重金属などの有害物質が流出して土壌、水生生態系または地下水を汚染しないこと
- 騒音または振動が発生して人に被害を与えないこと
- 重金属などの有害物質を除去、安定化してリサイクル製品や原料として使用する過程で、人や環境に害を与えないようにするなど、大統領令で定める事項を遵守すること
- その他、環境部令で定める再利用の基準を遵守すること
- 廃石綿、ポリ塩化ビフェニル(PCBs)が環境部令で定める濃度以上含まれる廃棄物、医療廃棄物(胎盤は除く)、廃有毒物など人体や環境に対する危険が非常に高いと懸念される廃棄物で、大統領令で定める廃棄物は、リサイクルが禁止または制限されている。
- 一定規模以上の廃棄物、または廃棄物を土壌等と混合した物質を、土壌・地下水・地表水等に接触させ、覆土材・盛土材・道路基層材その他環境部令で定める用途又は方法でリサイクルしようとする者、第13条の2の原則・遵守事項が定められていない廃棄物をリサイクルする者は、再利用環境性評価を受け、環境部長官の承認を得なければならない。(第13条の3)
- 有害性基準に適合しない廃棄物を再利用して製造した製品または物質を製造したり流通させてはならない。(第13条の5)
- セメントを製造する者は、廃棄物を使用したセメントについて、その製造に使用された廃棄物の種類、原産地および構成成分を含む情報を公開しなければならない。(第13条の6)
- 登録された廃棄物処理届出者は、特定の生活廃棄物(廃紙、スクラップ、廃食用油など)を収集・運搬またはリサイクルできる。またこれらの廃棄物は、認定されたリサイクル業者や製造業者など、環境部令で指定された者に運搬できる。(第14条)
- 食品類廃棄物を大量に廃棄する者のうち大統領令で定める排出者は、発生抑制と処理計画を自治体の長に届け出る必要があり、発生した食品類廃棄物を収集・運搬またはリサイクルしなければならない。(第15条の2)
- 事業場廃棄物排出者は、環境部令で定める有害物質を含む可能性のある廃棄物について分析機関に依頼し、指定廃棄物に該当するか事前に確認しなければならない。また、すべての廃棄物は、第13条・第13条の2の処理基準・再利用の原則に基づき、適正に処理しなければならない。生産工程においては、減量化施設の設置、技術開発、再利用など廃棄物の発生を抑制しなければならない。(第17条)
- 事業場廃棄物は、排出者が自ら、または処理業者等に委託して処理しなければならない。有害性のある廃棄物については排出者が「有害性情報資料」を作成・更新し、処理委託時に提供する義務がある。(第18条)
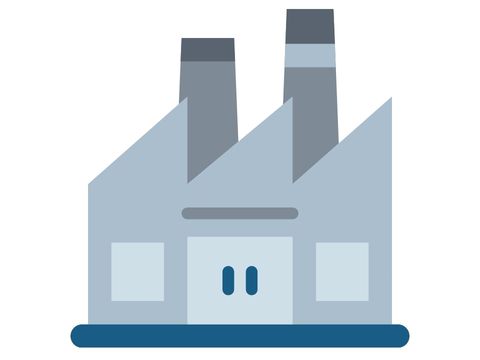
【廃棄物処理業】
- 廃棄物処理業を行う場合には環境部長官に、その他の廃棄物を対象とする場合には市道知事に廃棄物処理事業計画書を提出しなければならない。また、医療廃棄物の収集・運搬または処分を業とする者は、他の廃棄物と分離して別途の施設・装備・事業場を設置・運営しなければならない。(第25条)
- 廃棄物処理施設は環境部令で定める基準に従って設置しなければならず、小規模の焼却施設であっても基準未満のものは設置・運営できない。処理業の許可を受けていない者が処理施設を設置するには、環境部長官の承認を受ける必要がある。(第29条)
- 一定の廃棄物処理施設の設置者は、施設完成後に検査機関による検査を受けなければならない。(第30条)

【指導監督・罰則】
- 製品の製造・加工・輸入または販売などを行う事業者は、その材料・容器などが廃棄物になる場合、回収・処理しやすいようにしなければならない。さらに、環境部令で定める有害物質を含む、または大量に流通して廃棄物となる製品については、環境部長官が告示する方法に従って回収・処理しなければならない。(第47条)
- 不適切に処理された廃棄物に対しては、責任者に処理方法の変更や搬入、処理の中止などの措置命令がなされる。(第48条)
- 無許可での廃棄物処理業、無承認でのリサイクル環境性評価、基準に適合しない廃棄物処理、処理命令・措置命令の不履行などには懲役または罰金が科される。(第63〜68条)
目次
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第2条の2 廃棄物の細分類
第3条 適用範囲
第3条の2 廃棄物管理の基本原則
第4条 国家および地方自治体の責務
第5条 廃棄物の広域管理
第5条の2 生活廃棄物の発生地処理
第5条の3 搬入協力金の徴収
第6条 廃棄物処理施設の搬入手数料
第7条 国民の責務
第8条 廃棄物の投棄禁止等
第2章 廃棄物の排出および処理
第13条 廃棄物の処理基準等
第13条の2 廃棄物のリサイクル原則及び遵守事項
第13条の3 廃棄物リサイクル時の環境性評価
第13条の4 リサイクル環境性評価機関の指定等
第13条の5 リサイクル製品又は物質に関する有害性基準
第13条の6 廃棄物使用セメントに関する情報公開
第14条 生活廃棄物の処理等
第14条の2 生活廃棄物収集・運搬代行者に対する課徴金処分
第14条の3 食品廃棄物発生抑制計画の策定等
第14条の4 生活系有害廃棄物処理計画の策定等
第14条の5 生活廃棄物収集・運搬関連の安全基準等
第14条の6 生活廃棄物中の特定品目の代行
第14条の7 罰金刑の分離宣告
第15条 生活廃棄物排出者の処理協力等
第15条の2 食品廃棄物排出者の義務等
第16条 協約の締結
第17条 事業場廃棄物排出者の義務等
第17条の2 廃棄物分析専門機関の指定
第17条の3 廃棄物分析専門機関の遵守事項
第17条の4 廃棄物分析専門機関に対する評価
第17条の5 廃棄物分析専門機関の指定取消し等
第18条 事業場廃棄物の処理
第18条の2 有害性情報資料の作成・提供義務
第19条 事業場廃棄物処理者の義務
第4章 廃棄物処理業 等
第25条 廃棄物処理業
第25条の2 専用容器製造業
第25条の3 廃棄物処理業の適合性確認
第25条の4 医療廃棄物処理に関する特例
第26条 欠格事由
第26条の2 罰金刑の分離宣告
第27条 許可の取消し等
第27条の2 専用容器製造業登録の取消し等
第28条 廃棄物処理業者に対する課徴金処分
第29条 廃棄物処理施設の設置
第30条 廃棄物処理施設の検査
第30条の2 廃棄物処理施設検査機関の指定等
第31条 廃棄物処理施設の管理
第32条 他の法令による許可・届出等の擬制
第33条 権利・義務の承継 等
第5章 廃棄物処理業者等に対する指導・監督等
第34条 技術管理人
第35条 廃棄物処理担当者等に対する教育
第36条 帳簿等の記録と保存
第37条 休業と廃業等の届出
第38条 報告書の提出
第39条 報告・検査等
第39条の2 排出者に対する廃棄物処理命令
第39条の3 廃棄物処理業者等に対する廃棄物処理命令
第40条 廃棄物処理業者等の放置廃棄物処理
第41条 廃棄物処理共済組合の設立
第42条 組合の業務
第43条 分担金
第44条 民法の準用第6章 補則
第45条 廃棄物の引渡・引受内容等の電算処理
第46条 廃棄物処理の届出
第46条の2 廃棄物処理届出者に対する課徴金処分
第47条 廃棄物の回収措置
第47条の2 廃棄物の搬入停止命令
第48条 廃棄物処理に関する措置命令等
第48条の2 意見提出
第48条の3 廃棄物処理諮問委員会
第48条の4 廃棄物適正処理推進センター
第48条の5 課徴金
第49条 代執行
第50条 廃棄物処理施設の事後管理等
第50条の2 廃棄物処理施設の事後管理義務の承継
第51条 廃棄物処理施設の事後管理履行保証金
第52条 事後管理履行保証金の事前積立
第53条 事後管理履行保証金の用途等
第54条 使用終了又は閉鎖後の土地利用制限等
第55条 廃棄物処理事業の調整
第56条 国庫補助等
第57条 廃棄物処理施設設置費用の支援
第58条 廃棄物処理実績の報告
第58条の2 韓国廃棄物協会
第59条 手数料
第60条 行政処分の基準
第61条 聴聞
第62条 権限又は業務の委任と委託
第62条の2 罰則適用における公務員擬制
第62条の3 規制の再検討
第7章 罰則
第63条 罰則
第64条 罰則
第65条 罰則
第66条 罰則
第67条 両罰規定
第68条 過料
附則
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 廃棄物管理法 |
| 公布日 | 2025年03月25日 版 |
| 所管当局 | 環境部 |
作成者

株式会社先読