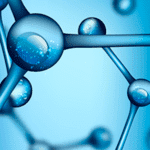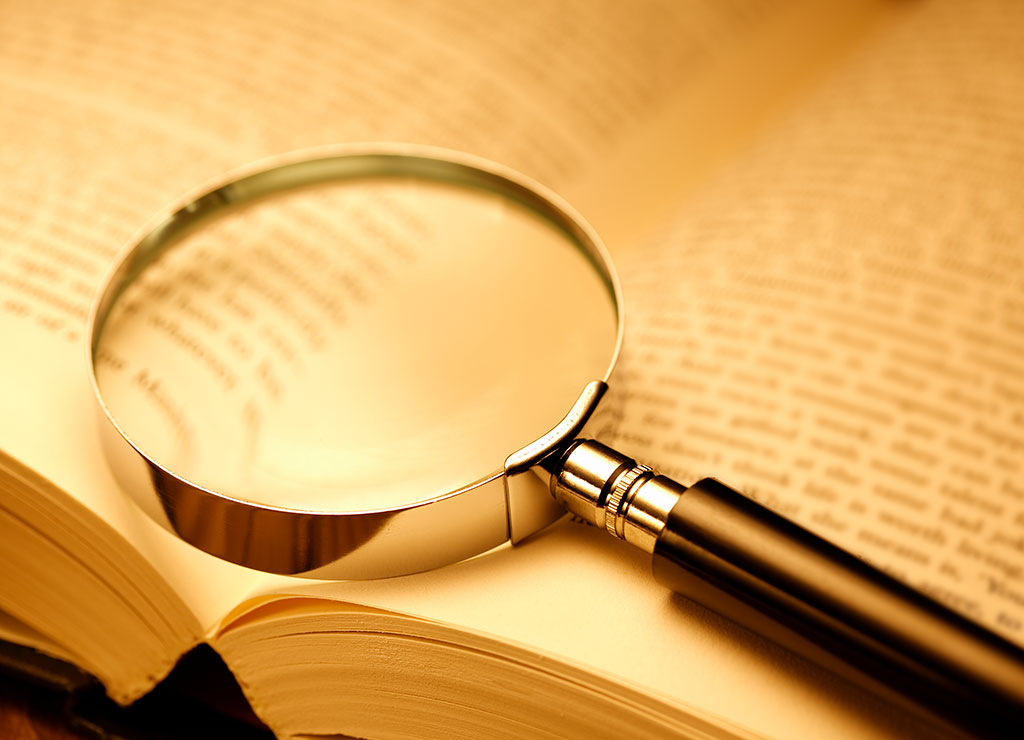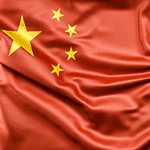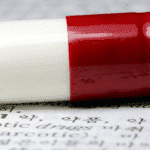| 法令の情報時期:1967年10月 | ページ作成時期:2024年09月 |
目的

目的は、医薬品の製造、販売、輸入、流通に関する規制を定め、国民の健康と安全を守るために、品質、効能、安全性を確保すること。
概要

医薬品の製造、販売、輸入、流通に関する規制を定め、国民の健康と安全を守るために、品質、効能、安全性を確保するために制定された。
医薬品委員会の設立、現代的および伝統的医薬品の許可申請・発行、医薬品事業者や医療従事者の義務、偽造や不良医薬品の規制、広告、罰則などを定め、医薬品の品質と安全性を確保するための規範を提供している。
違反した場合、罰則は違反内容に応じて懲役刑や罰金が科され、特に医薬品の製造や販売に関連する違反は、数千バーツの罰金や最大で終身刑に至る懲役が課される可能性がある。
注目定義
■ 「医療事業者」
| 「医療事業者」とは、医療に関して法律に従った事業を行うものをいう。(第4条) |
■ 「現代的医療事業者」
| 「現代的医療事業者」とは、医療事業に関する法律の下で歯科、薬局、助産、または看護の分野も含め現代的医療を提供する事業者をいう。(第4条) |
■ 「伝統的な医療事業者」
| 「伝統的な医療事業者」とは、伝統医学分野に関する法律の下で医療、医薬品を提供する事業者をいう。(第4条) |
■ 「医薬品」
|
「医薬品」とは、以下を意味する。 (1)大臣が通達した医薬品仕様書によって医薬品と認定された物質。 (2)人間または動物の病気の診断、緩和、治療または予防に使用することを目的とした物体。 (3)医療用化学物質または半製品医薬化学物質。 (4)ヒトまたは動物などの健康、構造、行動に影響を与える物質。 (1)(2)または(4)に以下は含まれない。 (a)農業、または大臣が通達した産業での使用を目的とした物質。 (b)食糧、スポーツ用品、健康増進用品、化粧品、医療機器の製造のために使用される物質。 (c)人体に直接使用されることなく研究室で研究、分析、または剖検のために使用される物質。 (第4条) |
■ 「現代的医薬品」
| 「現代的医薬品」とは、現代医学の臨床、または獣医学によって使用することを目的とした医薬品をいう。(第4条) |
■ 「伝統的医薬品」
| 「伝統的医薬品」とは、大臣から通達された伝統的医薬品仕様書に記載されている、または大臣によって伝統的医薬品として通達された伝統医療の実践、または獣医療で病気の治療のために使用することを目的とした医薬品をいう。(第4条) |
■ 「危険薬物」
| 「危険薬物」とは、大臣が危険な薬物として通達した現代的医薬品または伝統的医薬品をいう。(第4条) |
■ 「特別管理指定薬物」
| 「特別管理指定薬物」とは、大臣が特別管理指定薬物として通達した現代的医薬品または伝統的医薬品をいう。(第4条) |
■ 「外用薬」
| 「外用薬」とは、外用を目的とした現代的医薬品または伝統的医薬品をいう。(第4条) |
■ 「局所使用薬」
| 「局所使用薬」とは、耳、目、鼻、口、肛門、膣、または尿道での使用を特に意図した現代的医薬品または伝統的医薬品をいう。(第4条) |
■ 「家庭用一般薬」
| 「家庭用一般薬」とは、大臣が家庭用一般薬として通達した現代的医薬品または伝統的医薬品をいう。(第4条) |
■ 「包装済み薬品」
| 「包装済み薬品」とは、箱やそのほかの容器に充填され附表が貼付けされている現代的医薬品または伝統的医薬品をいう。(第4条) |
■ 「医療用化学物質」
| 「医療用化学物質」とは、医薬品の製造段階で調製、混合するために使用される有機または無機の化学物質をいう。(第4条) |
■ 「半製品医薬化学物質」
| 「半製品医薬化学物質」とは、単一の物質であろうと既製の混合物であろうと、医薬品の製造に使用される有機または無機の化学物質をいう。(第4条) |
■ 「製造」
| 「製造」とは、作成、混合、調整、または変形させることを意味し、医薬品を容器に充填し附表の貼付け包装を行い、製品を作成する意図して行われる行動をいう。(第4条) |
■ 「有効成分」
| 「有効成分」とは、ヒトや動物の病気の診断、治療、緩和または予防に効果を有する医薬品の重要な成分をいう。(第4条) |
■ 「有効成分の強さ」
| 「有効成分の強さ」とは、有効成分を重量対体積として示される薬物の濃度、または単位あたりの有効成分の量、または十分な治療のために実験室で試験された医薬品の濃度をいう。(第4条) |
■ 「医薬品仕様書」
| 「医薬品仕様書」とは、形態に関わらずヒトまたは動物に対して使用できる完成した医薬品に含まれる成分の表示をいう。(第4条) |
■ 「許諾者」
|
「許諾者」とは、以下をいう。 (1)事業者がタイ王国で許可された医薬品を生産、輸入、注文を行うための許可を与える権威を持つ食品医薬品委員会の事務局長または食品医薬品委員会の事務局長から委託された者。 (2)事業者がバンコクで医薬品販売を行うための許可を与える権威を持つ食品医薬品委員会の事務局長または食品医薬品委員会の事務局長から委託された者。 (3)事業者がバンコクで医薬品販売を行うための許可を与える権威を持つ県知事または県から委託された者。 (第4条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

タイ王国内で現代的医薬品を製造、販売、発注、輸入するには、許可が必要であり、省令による規則と手続きに従う必要がある。
ただし、第12条の規定は、タイ赤十字社や疾病予防・治療を担当する政府機関が製造・販売する医薬品、医師や獣医の処方による医薬品、危険性のないハーブや一般家庭薬の販売、個人使用のために持ち込まれる少量の医薬品などには適用されない。
これらの場合も、省令に従った規則と手続きを守る必要がある。(第12条、第13条)

許可申請者が以下の条件を満たす場合、タイ王国内で現代的医薬品の製造、販売、発注、輸入に関する許可が発行される。申請者は事業の所有者であり、運営に十分な資産や地位を有し、20歳以上でタイ国内に居住していることが求められる。
また、向精神薬関連の違法行為で懲役刑を受けたことがないか、刑罰が2年以上前に完了している者であることが条件となる。
加えて、能力に問題がなく、大臣が通達した病気に罹っておらず、適切な設備を有し、医薬品の品質管理ができることも必要である。
さらに、許可証が取消された場合は1年以内に同様の医薬品名を使用することはできない。法人の場合、経営者または代表者もこれらの条件を満たさなければならない。(第14条)

タイ国内で現代的医薬品の製造、販売、輸入を許可するための許可証は、申請者が事業の所有者であり運営に必要な資産や地位を持ち、20歳以上でタイに居住していることが求められる。
また、向精神薬関連の違法行為による懲役刑を受けたことがない、または刑罰が2年以上前に完了していること、特定の病気にかかっていないこと、適切な医薬品管理施設を持っていることなどの条件も必要となる。
法人の場合、その経営者や代表者も同様の条件を満たす必要がある。
許可証は発行年の12月31日まで有効で、更新申請は期限切れ前に行う必要があり、期限が切れると1か月以内に更新申請をしなければならない。
期限を過ぎると更新ができない場合もある。(第15条、第17条)
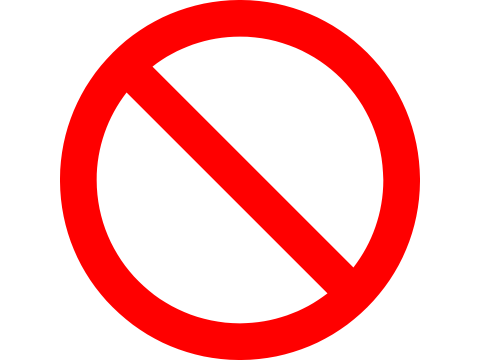
第19条では、許可証保持者が遵守すべき禁止事項が定められている。
まず、許可証で指定された場所以外での現代的医薬品の製造や販売は許可されず、卸売りを除いて行ってはならない。
また、許可証の種類に適合しない医薬品の製造や販売も禁止されている。
さらに、危険薬物や特別管理指定薬物とされる現代的医薬品を他の許可証保持者に販売することも禁じられている。(第19条)

製造事業には、最低2名の一級薬剤師が必要で、営業時間中は常に1名が駐在しなければならない。
販売や卸売り事業でも、営業時間中に薬剤師を常駐させる必要があり、特に一級薬剤師が求められる。
獣医療用医薬品の場合も、一級薬剤師や獣医師の駐在が義務付けられている。
輸入事業においても、一級薬剤師が輸入医薬品の保管施設に常駐することが求められている。(第20条、第21条、第21/2条、第23条、第24条)

製造者は、医薬品製造所の外に看板を設置し、原材料や製造された医薬品の検査、記録の保管、附表の表示、帳簿の作成などを行わなければならない。
特に医薬品の附表には、薬名や製造日、成分、製造者の情報などが明記されなければならず、医薬品の種類に応じた表示も必要である。
販売者も同様に、看板の設置や医薬品の種類別の保管、帳簿の作成を行い、医薬品の取り扱いについて厳密な基準に従わなければならない。
また、獣医療用医薬品や危険薬物、特別管理指定薬物は他の医薬品とは分けて保管する義務がある。(第25条、第26条)

タイ王国に医薬品を発注・輸入する者は、事業施設外に看板を設置し、運営者の情報や営業時間を表示しなければならない。
また、輸入医薬品の検査証明書を提供し、5年以上保管する必要があり、証明書が外国語の場合はタイ語に翻訳する義務がある。
医薬品の容器や外箱には、製造場所や輸入業者の情報を表示し、附表や添付文書もタイ語で判読可能であることが求められる。
附表やコモン・テクニカル・ドキュメントに警告を明示し、医薬品の情報が外国語の場合もタイ語に翻訳されなければならない。
さらに、医薬品の発注・輸入記録を帳簿に残し、規定された医薬品サンプルを収集することが求められる。
医薬品容器が小さく表示が困難な場合は、特定の表示義務が免除される場合もあるが、輸入医薬品は必ず管轄官庁による検査を受け、規定に従って輸入されなければならない。(第27条、第27/1条)

薬剤師、歯科医、助産師、看護師または獣医師で医薬品許可証保持者は自分の取得している許可証を医薬品製造施設、医薬品販売施設、医薬品輸入品保管施設内の目立つ場所にそれらを掲示しなければならない。(第29条)

一級薬剤師は医薬品製造施設での勤務中に、生産管理や医薬品附表・技術文書の監督、包装や表示の管理、販売管理、サンプルの管理などを行う義務がある。
第39条では、医薬品販売施設に配置される一級薬剤師が、医薬品の保管や附表の管理、販売・調剤の監督、処方に基づく医薬品のパッケージ管理、帳簿の監督などを行う責任を負う。
どちらも、省令に基づく業務を遂行する必要がある。二級薬剤師は、一級薬剤師と同様に第39条に準拠する。
しかし医薬品の変更、特別管理指定医薬品の販売および移動は禁止されている。(第38条、第39条、第40条)
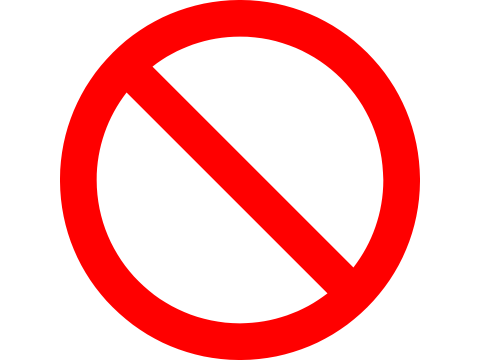
いかなる者も、許可なくタイ国内で伝統医薬品の製造、販売、または輸入を行うことは禁じられている。
許可は省令に従って申請しなければならない。
しかし、これは特定の例外に適用されない。これには、タイ赤十字社や疾病予防関連の政府機関による医薬品の製造、患者や小売店向けの伝統医薬品の調合と販売、危険薬物でないハーブや家庭用一般薬の販売、個人使用の範囲内で持ち込まれる医薬品などが含まれる。(第46条、第47条)

伝統的医薬品の生産、販売、輸出入を行うための許可証は、申請者が以下の条件を満たす場合に発行される。
申請者は事業の所有者であり、資産や資格を有していること、20歳以上でタイ国内に居住していること、違法行為で有罪判決を受けたことがなく、身体的・精神的に業務が可能であることが求められる。
また、事業に必要な施設や設備を備えており、品質管理の基準を遵守できることが条件である。
法人の場合は、経営者や代表者がこれらの条件を満たさなければならない。許可証は、製造、販売、輸入の3種類があり、それぞれ特定の要件に基づいて発行される。
許可証は発行年の12月31日まで有効で、更新を希望する場合は期限前に申請が必要である。期限切れ後1ヶ月以内に申請がない場合、更新はできなくなる可能性がある。(第48条、第49条、第51条)

許可証保持者は、許可証で指定された場所以外で伝統的医薬品を製造または販売することが禁止されている。
また、伝統的医薬品を製造する許可証保持者は、営業時間中に伝統的医薬品事業者を配置し、第68条を遵守する必要がある。
特に50以上の伝統的医薬品を製造する場合は、複数の事業者を配置し、それぞれが第68条に基づいた職務を遂行する義務がある。(第53条、第54条)

伝統的医薬品の製造許可証保持者は、指定された製造所の外に看板を掲示し、医薬品が製造されていることや実務担当者の情報を明示しなければならない。
医薬品の容器や外箱には、薬名や成分量、製造会社名、製造日などの情報を記載した附表を貼付し、外国語の場合はタイ語訳も必要である。医薬品の帳簿作成やその他の省令に規定された義務も負う。
一方、伝統的医薬品の販売許可証保持者も、販売所の外に看板を掲示し、医薬品の販売場所であることや運営担当者の情報を明示する必要がある。
販売される医薬品の容器や包装には傷がないことを確認し、省令に従った業務を行う義務がある。(第57条、第58条)

伝統的医薬品事業者は、各施設の営業時間中に滞在し、医薬品製造、販売、輸入に関連する業務を管理する責任を負う。
製造施設では、医薬品の生産が登録された仕様書に準拠しているか確認し、附表やコモン・テクニカル・ドキュメント、医薬品の容器や帳簿の管理を行う。
販売施設では、附表の管理や医薬品販売に従事し、輸入や輸送施設では、輸入医薬品の管理や帳簿、保管施設の管理を行う。
これらの業務は本法および省令に規定された義務に基づいて遂行される。(第68条、第69条、第70条)

偽造、不良、劣化した医薬品、登録されていない医薬品、または登録が取り消された医薬品の生産、販売、タイ国内への発注による輸入は禁止されている。
偽造医薬品とは、模倣、偽りの表示、製造業者名の虚偽、または成分量が基準に達していないものを指す。
不良医薬品は、成分や強度が不足しているか、品質が基準に適合しない医薬品であり、劣化医薬品は有効期限切れや品質劣化が確認されるものとされる。(第72条、第73条、第74条、第75条)

タイ王国内の現代的医薬品の製造、輸入、タイ王国内の伝統的医薬品の輸入を行うことを計画している許可証保持者は管轄官庁へ医薬品仕様書の提出と共に登録を申請しなければならない。
医薬品仕様書登録証明書を受領した後、医薬品の生産、タイ王国内への発注による輸入が行われるものとする。(第79条)
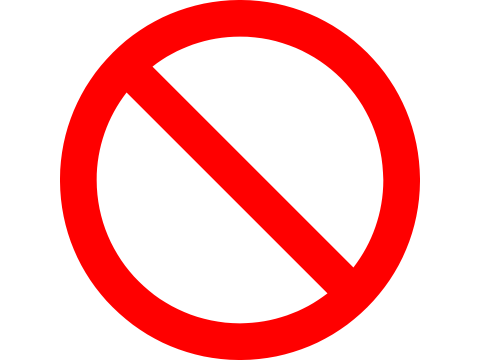
医薬品の販売広告では、治療や予防効果を誇張せず、虚偽の情報を含めてはならない。
また、特定の物質が有効であると消費者に誤解させる文言や、中絶や強力な月経薬、性的興奮剤、避妊薬としての効果を示すことも禁じられている。
危険薬物や特別管理指定薬物の効果を強調したり、他者による称賛や保証を用いることも禁止されており、指定された病気に対して薬効を示すことも許されない。(第88条)
目次
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第1章 医薬品委員会
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第2章 現代的医薬品の許可申請と許可の抹消
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第3章 現代医薬品に関する許可証保持者の義務
第19条
第20条
第21条
第21/2条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第26/2条
第27条
第27/1条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第33/1条
第34条
第35条
第36条
第37条
第4章 薬剤師、医療事業者、歯科医、助産師、看護師、獣医の義務
第38条
第39条
第40条
第40/1条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第5章 伝統医薬品の許可申請と許可証の発行
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第6章 伝統的医薬品許可証保持者の義務
第53条
第54条
第54/1条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第59/1条
第60条
第61条
第62条
第63条
第63/1条
第64条
第65条
第66条
第67条
第7章 伝統的医薬品事業者の義務
第68条
第69条
第70条
第71条
第8章 偽造医薬品、不良医薬品、劣化医薬品
第72条
第73条
第74条
第75条
第75/1条
第9章 医薬品関連通達
第76条
第77条
第77/1条
第77/2条
第78条
第10章 医薬品仕様書登録
第79条
第79/1条
第80条
第81条
第82条
第83条
第84条
第85条
第86条
第86/1条
第87条
第11章 広告
第88条
第88/1条
第89条
第90条
第90/1条
第12章 担当官
第91条
第92条
第93条
第94条
第13章 許可の一時停止と取消
第95条
第96条
第97条
第98条
第99条
第100条
第14章 罰則
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第105/1条
第106条
第107条
第107/2条
第108条
第109条
第110条
第111条
第112条
第113条
第113/1条
第114条
第114/1条
第115条
第116条
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
第122条
第122/1条
第123条
第123/1条
第124条
第124/1条
第125条
第125/1条
第126条
第126/1条
暫定規則
第127条
第128条
第129条
手数料
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 薬事法 仏暦2510年(西暦1967年) |
| 公布日 | 1967年10月15日 |
| 所管当局 | 保健省 |
作成者

株式会社先読