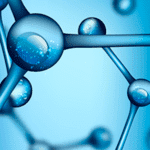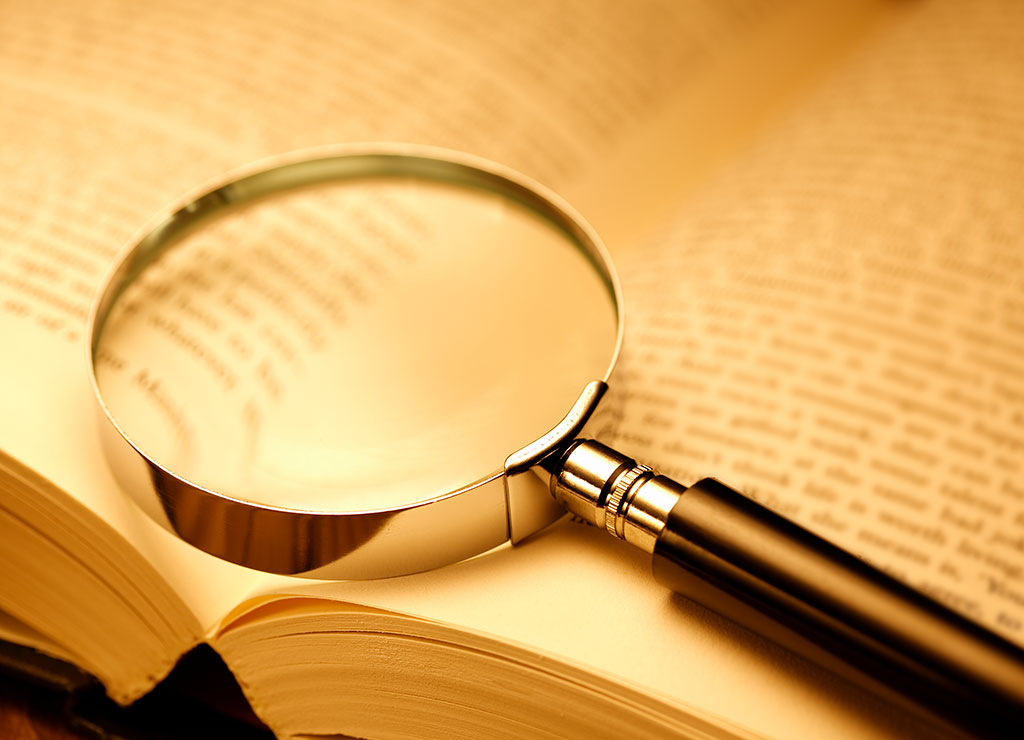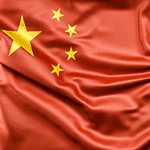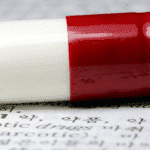| 法令の情報時期:2024年3月 U.S.C.確認 | ページ作成時期:2024年3月 |
目的

本法の目的は、米国の各州に対し安全で健康的な労働条件を保障するしまた奨励すること、国家として労働安全衛生の分野における研究、情報、教育及び訓練を行うことで、働く男女のための安全で健康的な労働条件を保障することとなっている(651条)。
この法律に基づいて、雇用主が被雇用者(労働者)に対して、具体的には有害化学物質への暴露、過度の騒音レベル、機械的危険、暑さや寒さのストレス、不衛生な環境などの危険がない環境を提供することを保証している。
概要

本法に基づいて、労働省(Department of Labor)の労働安全衛生局(Occupational Safety & Health Administration、OSHA)は、ほぼ全ての職場環境を対象とし、雇用主もしくは被雇用者に対し、血液媒介病原体や有害化学物質への曝露、転倒/転落、または結核などに適用される基準や命令を制定している。
具体的には、雇用主は本法に基づいた基準への理解が求められ、被雇用者に対し「OSHA基準に関する情報の提供や通知」、「職場の適切な慣例や手順などの確立」、「安全や衛生基準の点検と危険事項のからの保護」、「定期的な健康診断」など、そしてOSHAに対し「職業上のケガや病気の記録や報告」、「OSHAからの査察」などの義務を負う。
本法では、上記への違反に関しても定められている。
注目定義
■ 「長官」(Secretary)
| 「長官」(Secretary)とは、労働省長官をいう。(652条(1)) |
■ 「コミッション」(Commission)
| 「コミッション」(Commission)とは、労働安全衛生再調査委員会(Occupational Safety and Health Review Commission)をいう。(652条(2)) |
■ 「人物」(Person)
| 「人物」(Person)とは、個人または複数の個人、パートナーシップ、団体、法人、企業信託、法定代理人、または組織化された個人の集団をいう。(652条(4)) |
■ 「雇用主」(Employer)
| 「雇用主」(Employer)とは、商業に影響を与える事業に従事する者で、被雇用者を有する者をいう。米国(米国郵便公社(United States Postal Service)は含まない)、州、または州の政治的下部組織は含まれない。をいう。(652条(5)) |
■ 「被雇用者」(Employee)
| 「被雇用者」(Employee)とは、雇用主の被雇用者であって、その雇用主の商業に影響を及ぼす事業に使用される者をいう。(652条(6)) |
■ 「委員会」(Committee)
| 「委員会」(Committee)とは、本章に基づき設置された労働安全衛生国家諮問委員会(National Advisory Committee on Occupational Safety and Health)をいう。(652条(11)) |
■ 「所長」(Director)
| 「所長」(Director)とは、国立労働安全衛生研究所所長(Director of the National Institute for Occupational Safety and Health)をいう。(652条(12)) |
■ 「労働者災害補償委員会」(Workmen’s Compensation Commission)
| 「労働者災害補償委員会」(Workmen’s Compensation Commission)とは、本章に基づき設立された国家労働者災害補償法委員会(National Commission on State Workmen’s Compensation Laws)をいう。(652条(14)) |
■ 「研究所」(Institute)
| 「研究所」(Institute)とは、本章に基づき設立された国立労働安全衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health)をいう。(652条(13)) |
■ 「労働安全衛生基準」(occupational safety and health standard)
| 「労働安全衛生基準」(occupational safety and health standard)とは、安全で健康的な雇用および職場を提供するために合理的に必要または適切な条件、そして慣行、手段、方法、作業、または工程の採用または使用を要求する基準をいう。(652条(8)) |
■ 「国家コンセンサス規格」(national consensus standard)
|
「国家コンセンサス規格」(national consensus standard)とは、以下のような労働安全衛生規格またはその修正版をいう。(652条(9)) (1) 全国的に認知された規格団体により、その規格の範囲または条項の影響を受ける利害関係者が、その規格の採択について実質的な合意に達したと長官が判断できる手続きの下で採択、その後公布されたもの (2) 多様な意見を考慮する機会を与える方法で策定されたもの (3) 他の適切な連邦機関と協議の上、長官により規格として指定されたもの |
■ 「確立された連邦基準」(established Federal standard)
| 「確立された連邦基準」(established Federal standard)とは、米国の機関によって確立され、現在施行されている、または 1970年12月29日に施行されていた議会法に含まれる、運用可能な労働安全衛生基準をいう。(652条(10)) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法に基づき、査察(657条)または手続き(659条)が規定されている。しかし、これらの過程で長官等が入手した情報のうち、企業秘密もしくはその可能性あるものすべてを企業秘密(trade secret)とみなし、その内容は合衆国法典の「一般的な機密情報の開示(18 U.S.C.§1905)」項に従って、保護されている。(664条)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

雇用主、被雇用者それぞれの義務条項がある。(654条)
雇用者は、
(1)被雇用者に死亡または重大な身体的危害をもたらす、またはもたらす可能性のある危険が存在しない安全な雇用および就業場所を与えなければならない、
(2)本法に基づき公布された労働安全衛生基準などを遵守しなければならない。
被雇用者(労働者)は、および本法に従って発行され、自らの行動や行為に適用される労働安全衛生基準などのすべての基準を遵守しなければならない。

本法に基づいて、「有毒物質または有害な物理的事象(例えば、電気的危険、落下の危険、感染症、火災・爆発など)を扱う基準」が、「入手可能な最善の証拠に基づき、被雇用者が当該基準で扱われる危険性に就労期間中に定期的にさらされたとしても、健康または機能能力に重大な障害を受けないことを、最も適切に保証する基準」として設定されている。(655条(b)(5))

本法に基づいた基準の中には、上記「有毒物質または有害な物理的事象を扱う基準」以外に、「血液媒介病原体(B型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルスなど)への職業曝露に関する基準(Standard concerning occupational exposure to bloodborne pathogens)」も含まれる。(655条注記)

本法に基づいて、雇用主は使用する、または使用することを提案する条件、慣行、手段、方法、業務、または工程が、安全かつ衛生的な雇用および雇用場所を被雇用者に提供するものとする。
本法に基づいた基準において、雇用主が維持しなければならない条件、および雇用主が採用し利用しなければならない慣行、手段、方法、業務、および工程などが規定されている。(655条(b)(7)、(d))

具体的には、本法に基づいて、有害廃棄物作業に従事する被雇用者の安全衛生保護基準は、雇用主に対して以下の要件を求めている。(655条注記)
(1)現場の分析:現場の正式な危険性分析、および被雇用者保護のための現場固有の計画の策定
(2)訓練:被雇用者が有害物質にさらされるような廃棄物の作業に従事する前に、初期および定期的な訓練を提供
(3)健康診断:有害物質にさらされる危険な廃棄物の作業に従事する被雇用者の定期的な健康診断、監視、査察のプログラム策定と実施
(4)保護具:有害廃棄物の作業における適切な呼吸器や皮膚を保護する個人用保護具や衣服の提供
(5)工学的管理:有害廃棄物の作業に従事する被雇用者の機器の使用および暴露に関する科学・工学的管理
(6)最大暴露限度:有害廃棄物の作業に従事する被雇用者の最大暴露限度に関する要求の実施(必要な監視および評価手順を含む)
(7)情報提供プログラム:有害廃棄物の作業に従事する被雇用者に、当該作業の結果として起こりうる有害物質への暴露の性質と程度を通知するプログラムの策定と実施
(8)取り扱い:有害廃棄物の取り扱い、運搬、ラベル付け、廃棄の実施
(9)新技術プログラム:被雇用の保護を維持する新しい設備または技術の導入プログラムを実施
(10)汚染除去手順:汚染除去の手順の策定と実施
(11)緊急対応:有害廃棄物の作業に従事する被雇用者の緊急対応および保護に関する要件
(12)現場外での指導:40時間の初期指導と最低3日間の実地現場体験を行うことを義務付ける訓練の実施
(13)監督者の訓練:有害廃棄物の作業を直接行う現場の管理者および監督者に少なくとも8時間の専門訓練の実施
(14)認証:一般現場作業員、現場管理者、および監督者が上記(12)(13)の研修を受けたことを認証するための規定の所持
(15)緊急対応要員の訓練の実施

さらに、職場における危険性の高い化学物質の偶発的な放出に関連する危険から被雇用者を保護するための化学工程安全基準(Chemical Process Safety Standard)も本法に基づいて、規定されている。この基準では、雇用主に対して以下を求めている。(655条注記)
(1)職場の化学物質および工程の危険性、工程で使用される機器、工程で使用される技術を特定する安全情報を文書化し、維持する。
(2)必要に応じて、偶発的な放出の発生源の特定、職場において壊滅的な結果をもたらす可能性が高い、施設内での過去の放出の特定、放出の範囲による職場への影響の推定、被雇用者に対する当該範囲の健康および安全への影響の推定を含む、職場の危険への客観的評価(ハザードアセスメント)を実施する。
(3)ハザードアセスメントの開発および実施、化学事故防止計画の開発について、被雇用者およびその代表者と協議し、これらの記録および本基準で義務付けられているその他の記録の被雇用者への提供を行う。
(4)職場の危険有害性評価の結果に対応するシステムを確立し、予防、緩和、緊急時の対応に取り組む。
(5)職場の危険性評価および対応システムを定期的に見直す。
(6)各作業段階の手順、作業制限、安全衛生上の配慮を含む、化学工程の作業手順書を作成し、実施する。
(7)被雇用者に対し、安全および作業に関する情報を文書で提供し、作業手順について、危険と安全な実施方法に重点を置いて被雇用者を訓練する。
(8)請負業者に、適切な情報と訓練が提供する。
(9)被雇用者および請負業者に対し、緊急時対応に関する訓練および教育を行う。
(10)初期工程関連機器、保守材料、予備部品が設計仕様と一致して製造され、設置されることを保証する品質保証プログラムを確立する。
(11)使用する機器のメンテナンスのための手順書、使用する者への研修、および機器の適切な検査を含む、重要な関連機器のメンテナンスシステムを確立する。
(12)新たに設置された、あるいは変更されたすべての機器について、稼動前に安全性の確認を実施する。
(13)生産もしくは廃棄過程で使用される化学物質、技術、機器及び設備の変更を管理するための文書化された手順を確立し、実施する。
(14)職場で重大な事故が発生した、または発生した可能性のあるすべての事故について調査し、その結果については操業要員で検討し、適切であれば修正を加える。

長官(もしくは査察官)は、適切な証明書を提示した上で、(1)就業場所に立ち入り、(2)雇用主または被雇用者などに質問するなどを行って条件、構造、機械、器具、装置、機器、および資材について査察、調査することができる。(657条(a))
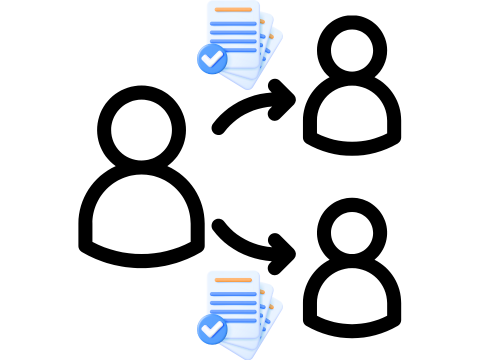
雇用主は、治療、意識喪失、作業や動作の制限、他職種への異動を伴わない軽傷を除き、業務上の死亡、負傷、疾病について正確な記録を保持し、定期的に報告しなければならない。(657条(c)(2))

本法に基づいて策定された規則では、雇用主に関して以下のことが求められる(670条(4))
(A)本法に基づいて実施される現地コンサルティング訪問を要請し、これを受ける
(B)訪問中に特定された危険を、国が定めた期間内に是正し、さらに労働条件または作業工程に大きな変化が生じたために新たな危険が明らかになった場合、次回の査察訪問を同意する
(C)本法に基づいて規制される危険を定期的に特定し、予防するための手順を実施し、安全で健康的な労働条件の達成に向け、管理職および非管理職の被雇用者の適切な関与と訓練を維持する訪問査察は、協議訪問の終了から1年間とし(ただし本法657条(f)に基づき要請された査察、または1人以上の被雇用者の死亡または3人以上の被雇用者の入院をもたらした労働災害の原因を特定するための査察を除く)、免除される場合がある。

本法において、雇用主の中で、特に中小企業を経営する雇用主は以下の点で比較的優遇されている。
(1)査察、調査、記録管理における負担を最小限とする。(657条(d))
(2)雇用主は、コンプライアンス支援プログラムの要請を行うことができ、その一環で州に対し職場相談を要請できる。
この中では、「労働安全衛生要件の適用の確認」「安全で健康的な雇用および職場を確立し維持するための雇用主の自主努力の確認」「雇用主に対する事業場等の現場でのコンサルティング」が行われる。これらのプログラムは、中小企業の中で、危険な状態が問題となっている企業からの要請が優先される。(670条(d))

本法において「労働者の家族保護(671a条)」、別名「労働者家族保護法(Workers’ Family Protection Act)」が別に項目立てされており、労働者(被雇用者)が汚染物質を運んで放出する可能性があることから、雇用主は被雇用者だけでなくその家族への汚染事故を防止する対策も調査される。
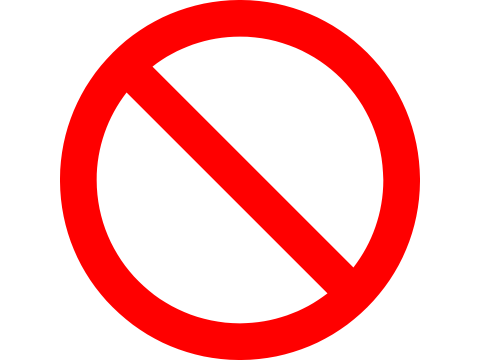
被雇用者が本法に関連して権利を行使したことなどを理由に、雇用主がこの者を解雇、差別することを禁止している。 (660条(c))

本法に基づいて公布された基準、規程、もしくは命令、または規定された規則の要件において、以下のような違反を行った雇用主に対して、民事罰等を課される場合がある
70,000ドルを上限とした民事罰
(a)故意または繰り返しの違反
(b)重大な違反に対する警告(違反が重大な場合は1件につき7,000ドル)
(c)重大でないと判断された違反に対する警告
(d)違反を是正しない場合(1日につき7,000ドル) (i)ラベル義務違反
10,000ドル以下の罰金、または6カ月以下の禁固刑、あるいはその両方の処罰(ただし、その違反が初犯の場合、20,000ドル以下の罰金または1年以下の禁固刑、あるいはその両方)
(e)(有罪判決を受けた場合、)故意の違反による従業員の死亡
1,000ドル以下の罰金、または6ヶ月以下の禁固刑、あるいはその両方の処罰
(g)虚偽の陳述、表明、証明
目次
29 U.S.C. 第15章 労働安全衛生
651. 議会の所信表明、目的と方針の宣言
652. 定義
653. 地理的適用可能性、司法執行や既存基準への適用可能性、連邦法の重複と調整に関する議会への報告、ただし労災法、一般法、もしくは雇用者と被雇用者の法的権利、義務、責務は影響を受けない
654. 雇用者と被雇用者の義務
655. 基準
656. 行政
657. 査察、調査、記録管理
658. 召喚(citations)
659. 施行手続き
660. 司法審査
661. 労働安全衛生再調査委員会
662. 差し止め手続き
663. 民事訴訟の陳述
664. 企業秘密の開示、保護命令
665. 必要とされる規定の変化、許容範囲や免除、そして手続きや期間
666. 民事および刑事罰
667. 州の管轄と計画
668. 連邦機関のプログラム
669. 研究および関連活動
669a. 被雇用者の健康と安全に関する研究の拡大
670. ト レーニングと被雇用者教育
671. 国立労働安全衛生研究所
671a. 労働者の家族保護
672. 州への補助金
673. 統計
674. 補助金受領者の監査、記録の保持、記録の内容、帳簿へのアクセスなど
675. 労働長官と保健福祉長官の年次報告書、内容
676. 省略
677. 分離可能性
678. 予算計上の承認
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 労働安全衛生法 |
| 公布日 | 1970年12月29日 (本稿執筆時点の最終改正:2019年12月20日) |
| 所管当局 |
作成者

株式会社先読