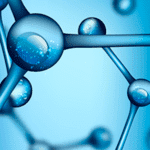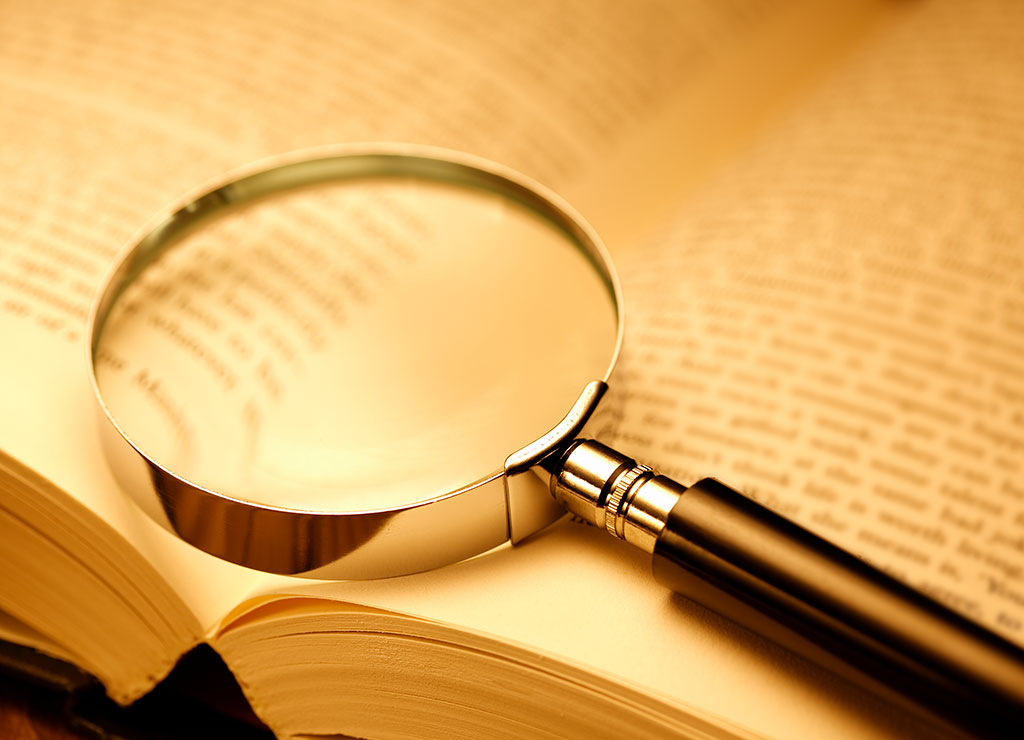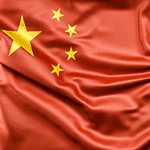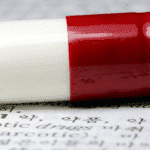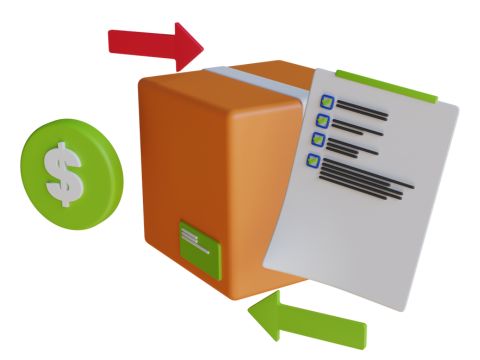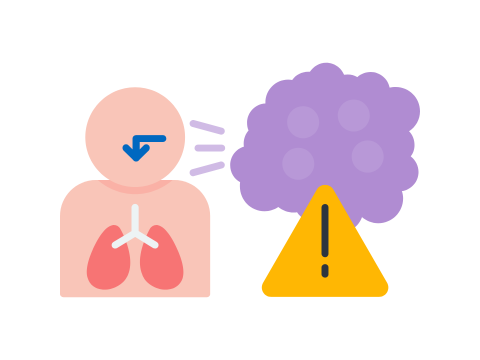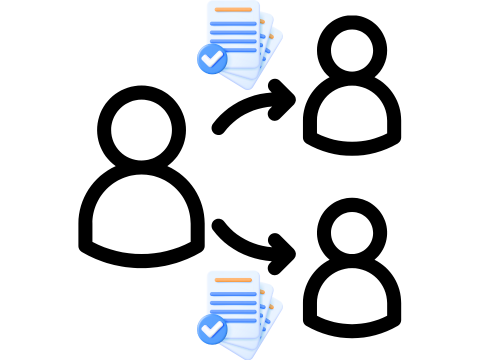雇用者は下記の事項を実施/考慮しなければならない。
-
事業場を常に安全かつ衛生的な状態に維持し、欠陥は速やかに是正し、適切な方法で清掃する。
-
避難経路・非常口を常時支障なく使用できるよう確保・標示し、必要に応じて非常照明を備える。
-
火災探知・警報・消火、換気・照明などの安全関連設備の機能を確保し、定期的に点検・保守する。
-
事業場の性質・規模・作業内容に応じ、避難・救助計画を作成し、掲示のうえ、適切な避難/初期消火等の訓練を実施する。
-
応急手当体制を整え、救急資機材・救急室や連絡手段を確保し、必要数の実施者を指名する。
-
設備の機能に支障が生じた場合は、復旧までの間、代替措置を講じて労働者の安全・健康を確保する。
(詳しくは第4条「事業場の運用に関する特別要件」参照)