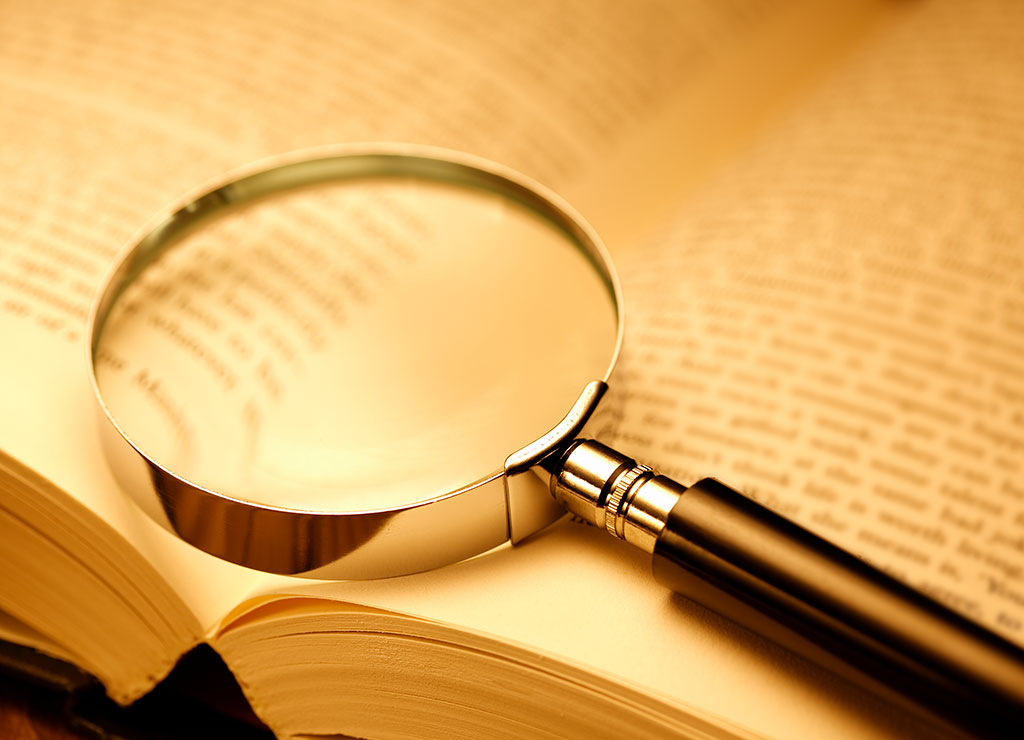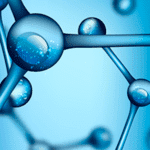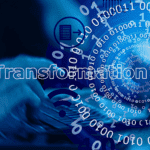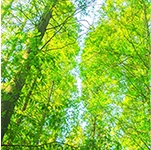| 法令の情報時期:2024年03月 暫定合意版 | ページ作成時期:2024年10月 |
※本ページの内容は規制化過程の情報となります。
目的
■ 本法令の目的は、環境持続可能性とラベル表示に関して、包装のライフサイクル全体に対する要求事項を定めることである。
概要
■ 本規則は、環境持続可能性とラベル表示に関して、包装のライフサイクル全体に対する要求事項を定め、包装の上市に関する規制を定めている。また、拡大生産者責任、不必要な包装の削減、包装の再使用や再充填などの包装廃棄物防止、包装廃棄物の回収と処理(リサイクルを含む)の要件も定めている。
■ 本規則は、高いレベルの環境保護に基づき、包装及び包装廃棄物が環境及び人の健康に及ぼす悪影響を防止又は低減しつつ、域内における貿易の障害、競争の歪曲及び制限を回避するため、包装及び包装廃棄物に関する各国の措置を調和させることにより、域内市場の効率的な機能に寄与するものである。
■ 本規則は、指令2008/98/ECの第4条に基づき、廃棄物ヒエラルキーに沿った措置を定めることにより、循環型経済への移行と、規則(EU) 2021/1119に規定されるように、遅くとも2050年までの気候中立性の達成に寄与するものである。
■ 本規則は、産業、その他の製造業、小売業、流通業、オフィス、サービス業、家庭のいずれで使用され、またはそれらに由来する廃棄物であるかを問わず、さらに、使用される材料にかかわらず、すべての包装、およびすべての包装廃棄物に適用される。
■ 本規則に違反した場合、特に第21条から第26条の要件に従わない場合、罰則として行政罰の罰金が科され、加盟国の法制度に行政罰の罰金がない場合は、関係当局による罰金手続が開始され、管轄の国内裁判所によって課されることとなり、課される罰金は効果的、比例的、かつ抑制的でなければならない。
>>和訳/解説書の案内ページはこちら<<
対象
<対象者>
■ 「製造者」(manufacturer)
| 「製造者」とは、包装または包装製品を製造する自然人または法人をいう。自然人または法人が、包装または包装製品に他の商標が表示されているか否かにかかわらず、自己の名称または商標の下で設計または製造された包装または包装製品を有する場合、包装または包装製品を製造する者の代わりに「製造者」とみなされるが、以下の段落でいう場合を除く。 (第3条) |
■ 「生産者」(producer)
| 「生産者」とは、指令2011/83/EUの第2条(7)に定義される遠隔契約によるものを含め、使用される販売手法に関係なく、以下のいずれかに該当する製造者、輸入者もしくは流通業者を意味する。
(i) 加盟国に設立され、その加盟国の領域内及び同じ領域内で初めて輸送用包装、再使用可能なサービス包装を含むサービス包装又は一次生産包装を利用可能にする者;または、 (ii) 加盟国に設立され、当該加盟国の領域内及び同一領域内で、(i)に掲げる包装以外の包装で包装された製品を初めて利用可能とする者;または、 (iii) 加盟国又は第三国に設立され、輸送用包装、再使用可能なサービス包装を含むサービス包装、一次生産包装又は上記以外の包装で包装された製品を、他の加盟国の領域内で初めてエンドユーザーに直接利用可能とする者;または (iv) 他の者が(i)から(iii)に従って生産者である場合を除き、加盟国に設立され、エンドユーザーとならずに包装製品を開梱する者。 (第3条) |
■ 「供給業者」(supplier)
| 「供給業者」とは、製造者に包装又は包装材料を供給する自然人又は法人をいう。(第3条) |
■ 「輸入者」(importer)
| 「輸入者」とは、EU域内に設立された自然人又は法人で、包装又は包装製品を第三国からEU 市場に上市する者をいう。(第3条) |
■ 「流通業者」(distributor)
| 「流通業者」とは、サプライチェーンの中で、包装又は包装製品を市場で利用可能にする、製造者または輸入者以外の自然人または法人をいう。(第3条) |
■ 「認定代理人」(authorised representative)
| 「認定代理人」とは、本規則のもとでの製造者の義務に関して、特定の業務に関連して製造者に代わって行動するために、製造者から書面による委任を受けたEU内に設立された自然人または法人をいう。(第3条) |
■ 「EPRに関する認定代理人」(authorised representative for the extended producer responsibility)
| 「EPRに関する認定代理人」とは、生産者が初めて包装又は包装製品を加盟国の市場で利用可能にする加盟国において、生産者が設立された加盟国又は第三国以外に設立された自然人又は法人であって、本規則の第7章に基づくその生産者の義務を果たすために指令2008/98/ECの第8a条(5)の第3副段落に従って当該生産者によって指名される者をいう。(第3条) |
■ 「最終流通業者」(final distributor)
| 「最終流通業者」とは、再使用を含む包装製品または再充填により購入可能な製品をエンドユーザーに引き渡す、サプライチェーンにおける自然人または法人をいう。(第3条) |
<対象製品>
■ 「包装」(packaging)
| 「包装」とは、それが作られる材料に関係なく、経済事業者が他の経済事業者又はエンドユーザーに対する製品の封じ込め、保護、取扱い、引渡し又は提示のために使用することを意図する物品であって、その機能、材料及びデザインに基づいて包装フォーマットに区別することができるものを意味し、次のものを含む:
(a) 製品とともに使用、消費または廃棄されることを意図され、製品の不可欠な部分ではなく、製品の寿命を通じて製品を収容、支持または保存するために必要な物品; (第3条) |
■ 「持ち帰り用包装」(take-away packaging)
| 「持ち帰り用包装」とは、飲料または調理済み食品を有人販売ポイントで充填したサービス包装であって、輸送および他の場所での即時消費のために包装され、それ以上の準備を必要とせず、通常、包装から消費されるものをいう。(第3条) |
■ 「一次生産包装」(primary production packaging)
| 「一次生産包装」とは、規則(EC)No 178/2002に定義される一次生産による未加工製品の包装として設計および使用されることを意図した物品をいう。(第3条) |
■ 「販売用包装」(sales packaging)
| 「販売用包装」とは、エンドユーザーに対して販売時点において、製品と包装からなる販売単位を構成するように考案された包装をいう。(第3条) |
■ 「グループ包装」(grouped packaging)
| 「グループ包装」とは、販売時点で一定数の販売単位のグループを構成するように考案された包装であって、その販売単位のグループがエンドユーザーにそのように販売されるか、販売時点における棚の補充を容易にするための手段としての役割を果たすか、又は在庫管理若しくは流通単位を作成するための手段としての役割を果たすかにかかわらず、その特性に影響を与えることなく製品から取り除くことができるものをいう。(第3条) |
■ 「輸送用包装」(transport packaging)
| 「輸送用包装」とは、物理的な取扱い及び輸送による製品の損傷を防止するために、1つ以上の販売単位又は販売単位のグループの取扱い及び輸送を容易にするように考案された包装を意味し、道路、鉄道、船舶及び航空コンテナは除く。(第3条) |
■ 「電子商取引用包装」(e-commerce packaging)
| 「電子商取引用包装」とは、オンライン販売またはその他の遠隔販売手段を通じて、製品をエンドユー ザーに配送するために使用される輸送用包装をいう。(第3条) |
■ 「複合包装」(composite packaging)
| 「複合包装」とは、2 種類以上の異なる材料で作られた包装単位であって、主包装材料の重量の一部であり、マニュアルで分離することができず、したがって1つの一体的な単位を形成するものをいうが、ある材料が包装単位の重要でない部分を構成し、且つ、いかなる場合にも包装単位の総質量の5%を超えない場合はこの限りではなく、ラベル、ワニス、塗料、インク、接着剤、ラッカーを除く。これは指令2019/904を妨げるものではない。(第3条) |
<その他>
■ 「市場で利用可能にすること」(making available on the market)
| 「市場で利用可能にすること」とは、商業活動の過程でEU市場での流通、消費または使用のために包装を供給することを意味し、それが支払の見返りであるか無償であるかを問わない。(第3条) |
■ 「上市」(placing on the market)
| 「上市」とは、EU市場で包装を最初に利用可能にすることをいう。(第3条) |
■ 「経済事業者」(economic operator)
| 「経済事業者」とは、製造者、包装の供給業者、輸入者、流通業者、認定代理人、最終流通業者およびフルフィルメント・サービスプロバイダーをいう。(第3条) |
■ 「消費者」(consumer)
| 「消費者」とは、取引、事業または職業(profession)以外の目的のために行動する自然人をいう。(第3条) |
■ 「エンドユーザー」(end user)
| 「エンドユーザー」とは、EU域内に居住又は設立された自然人又は法人であって、その産業上又は職業上の活動の過程において、消費者として又は職業上のエンドユーザーとして製品が利用可能とされる者であって、当該製品が供給された形態で、製品を市場でさらに利用可能としない者をいう。(第3条) |
■ 「包装廃棄物」(packaging waste)
| 「包装廃棄物」とは、指令2008/98/ECの第3条に規定される廃棄物の定義に該当する包装又は包装材料をいい、製造残渣は例外とする。(第3条) |
■ 「包装廃棄物防止」(packaging waste prevention)
| 「包装廃棄物防止」とは、包装又は包装材料が包装廃棄物となる前に講じられ、包装廃棄物の量を減少させる措置であって、製品を収容、保護、取扱い、引渡し又は提示するために包装がより少ないか又は全く必要とされないようにするものをいい、包装の再使用に関する措置及び包装が廃棄物となる前に包装の寿命を延ばす措置を含む。 (第3条) |
■ 「再使用」(re-use)
| 「再使用」とは、再使用可能な包装を、それが考案された際と同じ目的のために、再び複数回使用する操作をいう。(第3条) |
■ 「使い捨て包装」(single-use packaging)
| 「使い捨て包装」とは、再使用可能な包装ではない包装をいう。(第3条) |
■ 「ローテーション」(rotation)
| 「ローテーション」とは、再使用可能な包装が、それを収容、保護、取扱い、配送又は提示することを意図する製品とともに上市されてから、別の製品とともにエンドユーザーに再供給することを視野に入れた再使用のためのシステムにおいて再使用する準備が整うまでの間に達成するサイクルをいう。(第3条) |
■ 「トリップ」(trip)
| 「トリップ」とは、ローテーションの一部として、または単独で、充填または積み込みから空荷または荷降ろしまでの包装の移動をいう。(第3条) |
■ 「再使用のためのシステム」(systems for re-use)
| 「再使用のためのシステム」とは、クローズド・ループまたはオープン・ループ・システムでの再使用を可能にする、インセンティブとともに、組織的、技術的または財政的な取り決めを意味する。再使用のために包装を確実に回収する場合は、デポジット及び返却システムも含まれる。(第3条) |
■ 「再調整」(reconditioning)
| 「再調整」とは、再使用可能な包装を、その再使用を目的として機能的な状態に回復するために必要な、附属書6のPart Bに列挙されているすべての作業をいう。(第3条) |
■ 「再充填」(refill)
| 「再充填」とは、包装機能を果たすエンドユーザー所有の容器又はエンドユーザーが最終流通業者の販売時点で購入した容器に、エンドユーザー又は最終流通業者が、エンドユーザーが最終流通業者から購入した製品又は複数の製品を充填する作業をいう。(第3条) |
■ 「再充填場所」(refill station)
| 「再充填場所」とは、最終流通業者が、再充填によって購入できる製品をエンドユーザーに提 供する場所をいう。(第3条) |
■ 「HORECAセクター」(HORECA sector)
| 「HORECAセクター」とは、NACE Rev.2「経済活動の統計的分類」による宿泊及び飲食サービス業をいう。(第3条) |
■ 「売場」(sales area)
| 「売場」とは、販売のために提供される商品の陳列、その支払い、および客の滞留と回遊のために与えられる区域をいう。これには、保管エリアなど一般に公開されていない場所や、駐車場など商品が陳列されていない場所は含まれない。eコマース包装の文脈では、保管及び発送エリアは売場とみなされる。(第3条) |
■ 「リサイクルのための設計」(design for recycling)
| 「リサイクルのための設計」とは、包装の個々の構成要素を含む包装の設計であって、運用環境において証明される確立された回収、分別及びリサイクル工程により、包装のリサイクル性を確保するものをいう。(第3条) |
■ 「リサイクル性」(recyclability)
| 「リサイクル性」とは、分別回収、分流分別、規模に応じたリサイクル、一次原材料に代わるリサイクル材料の使用に基づく、設計による廃棄物の管理および加工に対する包装の適合性をいう。(第3条) |
■ 「大規模にリサイクルされる包装廃棄物」(packaging waste recycled at scale)
| 「大規模にリサイクルされる包装廃棄物」とは、設置されたインフラで分別回収され、リサイクルされる包装廃棄物であって、EUレベルで、表1a附属書2に記載される各包装区分のリサイクル材料の年間量が、木材については30%以上、その他の材料については55%以上であることを保証する運用環境で証明される確立された工程を使用するものをいう。 これには、廃棄物管理の目的でEUから輸出される包装廃棄物で、第47条(12)の要件を満たすとみなされるものも含まれる。(第3条) |
■ 「材料リサイクル」(material recycling)
| 「材料リサイクル」とは、廃棄物の生物学的処理、有機材料の再処理、エネルギーリカバリー、燃料または埋め戻し作業に使用される材料への再処理を除き、廃棄物を元の目的または他の目的のために材料または物質に再処理する、あらゆるリカバリー作業をいう。(第3条) |
■ 「高品質リサイクル」(high-quality recycling)
| 「高品質リサイクル」とは、保存される技術的特性に基づき、元の材料と同等の品質のリサイクル材料を生産し、リサイクル材料の品質が保持される包装またはその他の用途の一次原材料の代替として使用されるリサイクルプロセスをいう。(第3条) |
■ 「包装区分」(packaging category)
| 「包装区分」とは、、材料と特定の包装設計の組み合わせであって、確立された最新の回収、分別、リサイクル工程を参照してリサイクル性を決定し、運用環境で証明され、リサイクル設計基準の定義に関連するものをいう。(第3条) |
■ 「一体型コンポーネント」(integrated component)
| 「一体型コンポーネント」とは、、包装単位本体とは別個のものであってもよく、異なる材料であってもよいが、包装単位及びその機能と一体であり、その機能を確保するために主な包装単位から分離する必要がなく、必ずしも同じ廃棄経路で廃棄される必要はないが、通常、包装単位と同時に廃棄される包装コンポーネントをいう。(第3条) |
■ 「別個のコンポーネント」(separate component)
| 「別個のコンポーネント」とは、包装単位の本体とは別個であり、異なる材料であり、包装単位本体から完全かつ恒久的に分離する必要があり、通常、包装単位の前に、包装単位とは別個に廃棄される包装コンポーネントを意味し、輸送中または分別中に機械的圧力によって単に互いに分離できる包装コンポーネントを対象とする。(第3条) |
■ 「包装単位」(unit of packaging)
| 「包装単位」とは、製品の封じ込め、保護、取扱い、引渡し、保管、輸送及び提示などの包装機能を一体として果たす、一体化された又は別個のコンポーネントを含む全体としての単位をいい、販売前に廃棄される場合には、グループ包装又は輸送用包装の独立した単位を含む。(第3条) |
■ 「革新的な包装」(innovative packaging)
| 「革新的な包装」とは、製品の封じ込め、保護、取扱い、または引渡しなどの包装の機能に著しい改善をもたらし、全体として実証可能な環境上の利益をもたらす、新しい材料を用いて製造される包装の形態をいうが、製品の陳列や販売を改善することを主目的として既存の包装に手を加えた結果の包装は例外とする。 (第3条) |
■ 「二次原材料」(secondary raw materials)
| 「二次原材料」とは、必要な確認および選別を経て、リサイクル工程により得られ、一次原材料の代替となり得る原材料をいう。(第3条) |
■ 「ポストコンシューマー・プラスチック廃棄物」(post-consumer plastic waste)
| 「ポストコンシューマー・プラスチック廃棄物」とは、指令2008/98/ECの第3条(1)に定義されるとおり、プラスチックであり、流通、消費又は使用のために供給され、加盟国又は第三国の上市されたプラスチック製品から発生した廃棄物をいう。(第3条) |
■ 「接触に敏感な包装」(contact sensitive packaging)
| 「接触に敏感な包装」とは、以下の規則の適用範囲内の製品に適用することを意図した包装をいう。(EC) No 1831/2003、(EC) No 1935/2004、(EC) No 767/2009、(EC) No 2009/1223、(EU) 2017/745、(EU) 2017/746、(EU) 2019/4、(EU) 2019/6、指令2001/83/EC、指令2008/68/EC、または欧州委員会決定 (EU)2023/1809の第1条および第2条に定義される製品、欧州議会および理事会指令2002/46/EC、または指令2008/68/EC。(第3条) |
■ 「堆肥化可能な包装」(compostable packaging)
| 「堆肥化可能な包装」とは、嫌気性消化を含む工業的に管理された条件下でのみ、生分解するか、必要であれば物理的処理と組み合わせて生物学的分解を受けることが可能であり、最終的に二酸化炭素に転換するか、酸素、メタン、ミネラル塩、バイオマス、水がない状態で分解し、分別回収や堆肥化および嫌気性消化のプロセスを妨げたり危うくしたりしない包装をいう。(第3条) |
■ 「家庭で堆肥化可能な包装」(home compostable packaging)
| 「家庭で堆肥化可能な包装」とは、工業規模の堆肥化施設ではない非管理条件下で生分解可能な包装であって、その堆肥化工程が、個人によって、自らが使用するための堆肥を生産する目的で行われるものをいう。(第3条) |
■ 「バイオベース・プラスチック」(biobased plastics)
| 「バイオベース・プラスチック」とは、バイオマス原料、有機廃棄物、または副産物などの生物学的資源から作られるプラスチックをいう。バイオベース・プラスチックには、生分解性と非生分解性の両方がある。(第3条) |
■ 「使い捨てプラスチック飲料ボトル」(single use plastic beverage bottles)
| 「使い捨てプラスチック飲料ボトル」とは、指令(EU)2019/904の附属書 Part F に記載されている飲料ボトルをいう。(第3条) |
■ 「プラスチック」(plastic)
| 「プラスチック」とは、規則(EC)No 1907/2006 の第3条第5項の意味におけるポリマーから構成される材料で、 添加物またはその他の物質が添加されている可能性があり、包装の主要コンポーネントとして機能することができるものをいうが、化学修飾されていない天然ポリマーを除く。(第3条) |
■ 「プラスチック製キャリーバッグ」(plastic carrier bags)
| 「プラスチック製キャリーバッグ」とは、プラスチック製の持ち手付きまたは持ち手なしのキャリーバッグで、製品の販売時に消費者に供給されるものをいう。(第3条) |
■ 「軽量プラスチック製キャリーバッグ」(lightweight plastic carrier bags)
| 「軽量プラスチック製キャリーバッグ」とは、、肉厚が50ミクロン未満のプラスチック製キャリーバッグをいう。(第3条) |
■ 「超軽量プラスチック製キャリーバッグ」(very lightweight plastic carrier bags)
| 「超軽量プラスチック製キャリーバッグ」とは、肉厚が15ミクロン未満のプラスチック製キャリーバッグをいう。(第3条) |
■ 「厚手のプラスチック製キャリーバッグ」(thick plastic carrier bags)
| 「厚手のプラスチック製キャリーバッグ」とは、肉厚が50~99ミクロンのプラスチック製キャリーバッグをいう。(第3条) |
■ 「極厚プラスチック製キャリーバッグ」(very thick plastic carrier bags)
| 「極厚プラスチック製キャリーバッグ」とは、99ミクロンを超える厚さのプラスチック製キャリーバッグをいう。(第3条) |
■ 「廃棄物容器」(waste receptacles)
| 「廃棄物容器」とは、、廃棄物を保管および回収するために使用される容器で、例えばコンテナ、瓶、袋をいう。(第3条) |
■ 「デポジット」(deposit)
| 「デポジット」とは、包装又は充填された製品を購入する際にエンドユーザーから徴収される、包装又は 充填された製品の価格の一部ではない金額であって、所定の加盟国におけるデポジット及び返却制度の対象であり、エンドユーザー又は何人かがその目的のために設置される回収ポイントにデポジット付包装を返却する際に償還可能な金額をいう。(第3条) |
■ 「デポジットおよび返却システム」(deposit and return system)
| 「デポジットおよび返却システム」とは、その制度の対象となる包装製品又は充填製品を購入する際にエンドユーザーにデポジットが課され、デポジット付包装が国家当局によってその目的のために認可された回収経路の一つを通じて返却されたときに償還される制度をいう。(第3条) |
■ 「技術仕様書」(technical specification)
| 「技術仕様書」とは、製品、プロセスまたはサービスが満たすべき技術的要件を記載する文書をいう。(第3条) |
■ 「整合規格」(harmonised standard)
| 「整合規格」とは、規則 (EU) No 1025/2012の第2条(1)(c)に定義される規格をいう。(第3条) |
■ 「適合性評価」(conformity assessment)
| 「適合性評価」とは、包装に関する本規則の持続可能性、安全性、表示及び情報要件が満たされているかどうかを実証するプロセスをいう。(第3条) |
■ 「生産者責任組織」(producer responsibility organisation)
| 「生産者責任組織」とは、複数の生産者に代わって拡大生産者責任の義務の履行を財政的、または財政的及び運営的に組織する法人をいう。(第3条) |
■ 「ライフサイクル」(life-cycle)
| 「ライフサイクル」とは、天然資源からの原材料の入手又は生成、前処理、製造、保管、流通、使用、 修理、再使用、及び使用終了(end-of-life)からなる包装の一生の連続した相互に結びついた段階をいう。(第3条) |
■ 「リスクを呈する包装」(packaging presenting a risk)
| 「リスクを呈する包装」とは、第56条(1)に列挙された要件以外の本規則で定める又は本規則に従って定める要件に適合しないことにより、その要件によって保護される環境、健康又はその他の公共の利益に悪影響を及ぼすおそれのある包装をいう。(第3条) |
■ 「重大なリスクを呈する包装」(packaging presenting a serious risk)
| 「重大なリスクを呈する包装」とは、評価に基づき、関連する不遵守の程度又は関連する危害が市場監視当局による迅速な介入を必要とすると考えられるリスクを呈する包装を意味し、不適合の影響が即時的でない場合を含む。(第3条) |
■ 「オンラインプラットフォーム」(online platform)
| 「オンラインプラットフォーム」とは、規則(EU) 2022/2065の第3条(i)に定義されるオンラインプラットフォームをいう。(第3条) |
■ 「廃棄物」(waste)
| 「廃棄物」とは、指令2008/98/ECの第3条(1)に定義される廃棄物をいう。再調整に送られる再利用可能な包装は、廃棄物とはみなされない。(第3条) |
■ 「公的契約」(public contracts)
| 「公的契約」とは、指令2014/24/EUの第2条(5)に定義される公的契約、または指令 2014/25/EUで言及される公的契約をいう。(第3条) |
適用除外/対象外/免除
本規則が指令2008/68/ECと抵触する場合は、指令2008/68/ECが優先されるものとする。
※適用除外は、主に各要件に対して、個別にそれぞれの条項の中で規定されている。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
■ 包装は、本規則に適合する場合にのみ上市されなければならない。(第4条)
■ 上市される包装は、排出物や、二次原材料、灰、その他の最終処分材料などの廃棄物管理の結果生じるもの、およびマイクロプラスチックによる環境への悪影響を含め、包装または包装コンポーネントの成分として懸念物質の存在と濃度を最小化するように製造されなければならない。(第5条)
■ 上市されるすべての包装はリサイクル可能である必要があり、リサイクル可能とみなされるためには、材料リサイクルに適しており、元の原材料と同等の品質を持つ二次原材料として利用できることが条件となる。また、廃棄物となった場合には適切に分別され、他の廃棄物のリサイクル性に悪影響を与えずに大規模にリサイクルできることが求められる。これらの条件は、2030年から段階的に適用され、2038年までには、AまたはB等級のリサイクル性能を持つ包装のみが上市可能となる。製造者は、リサイクル性を評価し、その性能等級をA、B、Cのいずれかで表さなければならない。(第6条)
■ 2030年までに、上市される包装のプラスチック部分は、使用済みプラスチック廃棄物から回収されたリサイクル材料を一定割合含む必要があり、PETを主成分とする包装は30%、その他のプラスチック包装は35%を達成しなければならない。2040年には、この割合はPETで50%、その他の包装で65%に引き上げられる。リサイクル材料は、適切な規定に従い回収・リサイクルされたポストコンシューマープラスチック廃棄物から得られたものである必要がある。医療機器や堆肥化可能な包装、危険物輸送用の包装など、一部の包装はこれらの規定から除外される。製造者はリサイクル材料の使用割合を技術文書で証明し、生産者の責任に基づく拠出金は、使用されるリサイクル材料の割合に応じて調整可能となる。(第7条)
■ 上市される包装や青果物に貼付される粘着ラベルは、本規則発効から36ヵ月以内に、工業的に管理された条件下での堆肥化基準に適合しなければならず、必要に応じて家庭での堆肥化基準にも従う必要がある。堆肥化可能な包装に関して、加盟国は、生分解性の廃棄物がバイオ廃棄物と共に回収される適切なシステムが存在する場合、特定の包装に対して堆肥化可能であることを求めることができる。これには、超軽量および軽量プラスチック製キャリーバッグが含まれる。その他の生分解性プラスチックや材料で作られた包装は、リサイクル可能であり、他の廃棄物の流れに悪影響を与えないことが求められる。これらの要件への適合は、包装に関する技術文書で証明されなければならない。(第9条)
■ 2030年1月1日までに、製造者や輸入者は、上市される包装がその機能を保ちながら、形状や材質を考慮して最小限の重量と体積で設計されていることを保証しなければならない。さらに、性能基準に適合しない包装や、二重壁や偽底など不必要に体積を増加させる包装が市場に出ないようにする必要がある。ただし、保護されている意匠権や商標、または地理的表示に属する製品の包装は、この要件の一部から免除される。欧州委員会は本規則発効24か月後までに、包装の最小化に関する要件への適合方法を定める規格を作成するよう指示し、最大重量や容積、厚さなどの基準を設定する必要がある。要件への適合は、技術文書で実証される必要があり、包装の性能基準や重量・体積の削減の限界に関する試験結果や研究を含む。再使用可能な包装については、再使用可能性の要件も考慮に入れた評価が求められる。(第10条)
■ 包装には材料組成を示すラベルを表示し、消費者が容易に理解できるものでなければならない。特に堆肥化可能な包装については、適切な表示が義務付けられるが、輸送用包装や一部の返却システムには適用されない。また、QRコードなどのデジタル情報提供も奨励されており、再使用可能な包装には再使用可能であることを明示するラベルが必要となる。さらに、リサイクル材料やバイオベース・プラスチックに関する情報を含むラベルも、規定された方法論に基づく必要がある。ラベルやQRコードは消去できない形で包装にしっかりと表示され、オンライン販売でも消費者に提供されることが求められる。消費者が誤解しないよう、包装の持続可能性に関する誤解を招くラベルの表示は禁止されており、欧州委員会が必要に応じてガイドラインを策定する。また、拡大生産者責任制度に基づく包装には、QRコードなどを通じて生産者の義務履行を示す識別可能なシンボルが表示されることができる。(第11条)
■ 製造者は、第5条から第11条の要件に適合する包装のみを市場に出さなければならず、上市前に適合性評価を実施し、技術文書を作成する義務がある。適合性が証明された場合は、EU適合宣言を作成し、関連書類を使い捨て包装は5年間、再使用可能な包装は10年間保管しなければならない。製造者は、シリーズ生産における適合性を維持し、変更があれば適合性を再評価する必要がある。包装には識別情報を付し、名称や連絡先を明示する義務があり、これらの情報は消費者にわかりやすく表示されなければならない。適合しない包装が発覚した場合、製造者は是正措置を講じ、市場から撤退させるかリコールしなければならない。技術文書は、国家当局の要請に応じて提供されるべきであり、不遵守の是正に協力する義務がある。特定の輸送用包装や再使用可能な包装は例外として扱われ、零細企業が提供する包装については、包装提供業者が製造者とみなされる場合がある。(第13条)
■ 包装又は包装材料の供給業者は、製造者が容易に理解できる言語またはその複数の言語で、附属書7で言及され、第5条から第10条の下で要求される技術文書を含め、包装及び包装材料が本規則に適合していることを実証するために必要なすべての情報及び文書を製造者に提供しなければならない。当該情報および文書は、紙または電子形式で提供されなければならない。(第14条)
■ 輸入者は、第5条から第11条に定められた要件に適合する包装のみを市場に出す責任を負い、包装が適合性評価を受け、必要な技術文書が製造者によって作成されていること、ラベル表示が適切に行われ、必要な書類が添付されていることを確認する義務がある。また、輸入者は、製品に自身の名称や連絡先を明示し、情報が明確かつ読みやすいものであることを保証しなければならない。包装が適合していない場合、是正措置を講じる必要があり、場合によっては市場から撤退させるかリコールを実施する義務がある。輸入者は、EU適合宣言の写しや技術文書を保管し、市場監視当局の要請に応じて提供する責任も負う。また、輸入者は、包装が規定に適合しない場合、適切な是正措置を行い、国家当局の要請に応じて迅速に対応することが求められる。(第16条)
■ 流通業者は、包装を市場に出す際に、本規則に基づく要件に十分な注意を払い行動する責任がある。包装を市場で利用可能とする前に、流通業者は生産者が登録されていることや、包装のラベル表示が適切であること、また製造者と輸入者が関連する要件を遵守しているかを検証しなければならない。流通業者は、包装が適合しないと考えた場合、その包装を市場に出すことは許されず、保管や輸送中も規定への準拠を確保する義務がある。また、生産者からの情報は確認以外の目的で使用してはならず、商用目的での悪用は禁止されている。流通業者は、包装が不適合である場合に是正措置や撤回、リコールが適切に行われることを確認し、必要に応じて市場監視当局に不遵守の疑いを報告しなければならない。さらに、国家当局からの合理的な要請があった場合、流通業者は適切な言語で包装の適合性に関する情報を提供し、不遵守を是正するための措置について国家当局に協力する責任がある。(第17条)
■ EU域内の消費者に包装を提供する生産者は、フルフィルメント・サービスプロバイダーとの契約締結時に、規則(EU) 2019/1020の第40条(3)(a)および(b)に基づく情報を提供する義務がある。フルフィルメント・サービスプロバイダーは、生産者から受け取った情報が信頼できるかどうかを評価するために最善の努力を払う必要があり、情報の正確性については生産者が責任を負う。もし情報に不備や不正確さがある場合、プロバイダーは生産者に改善を求め、改善がなければサービス提供を停止し、その理由を生産者に通知する必要がある。また、生産者はプロバイダーのサービス停止に異議を申し立てる権利を持つ。さらに、フルフィルメント・サービスプロバイダーは、取り扱う包装が規定に適合するよう、倉庫保管や発送の条件を維持する責任がある。(第18条)
■ 2030年1月1日または委任法令発効36ヶ月後のいずれか遅い日までに、グループ包装、輸送用包装、または電子商取引用包装に包装を充填する経済事業者は、空きスペース比率を最大50%に抑えることを保証する必要がある。この空きスペース比率の計算方法は、欧州委員会が発効から3年以内に策定する権限を持ち、特に不規則な形状の包装製品や内容物が破損しやすい包装に関する特性を考慮しなければならない。「空きスペース」とは、包装の総容積から販売用包装の容積を引いたもので、「空きスペース比率」はその空きスペースと総容積の比率を指す。エアクッションや気泡緩衝材などの充填材料で満たされたスペースも空きスペースとしてカウントされる。さらに、販売用包装を充填する事業者は、製品保護のために必要な最小限の空きスペースを確保しなければならず、食品を保護するためのヘッドスペースが必要な製品は、充填時の水準で評価される。販売用包装を電子商取引用として使用する事業者や再使用可能な包装を使用する事業者はこの義務から免除されるが、販売用包装が他の規定に適合することを保証する必要がある。(第21条)
■ 再使用可能な包装を使用する経済事業者は、再使用のためのシステムに参加し、その包装が附属書6のPart Aに規定される要件に適合していることを確認しなければならない。また、エンドユーザーが再利用する前に、包装が附属書6のPart Bに従って再調整されることを保証する必要がある。経済事業者は、1つ以上の相互化された再使用のためのシステムの責任を負う第三者を指名でき、指名された第三者は再使用可能な包装が要件に準拠していることを保証する。この場合、経済事業者の義務は第三者が代行することとなる。さらに、附属書6に定義されるクローズド・ループ・システムを使用する場合、経済事業者はシステム参加者が特定し、システム運営者が承認した回収ポイントに包装を返却することが求められる。(第24条)
■ 再充填による製品購入の可能性を提供する経済事業者は、エンドユーザーに対して再充填用の容器の種類、衛生基準、および容器使用に関する安全衛生の責任を通知しなければならない。この情報は定期的に更新され、施設内に明示されるかエンドユーザーに提供される必要がある。また、再充填を可能にする経済事業者は、再充填場所が附属書6のPart Cや他のEU法令に準拠していることを保証しなければならない。さらに、再充填場所で提供される包装や容器が附属書6の要件を満たしていない場合、またはデポジットおよび返却システムの一部として提供される場合には、無料で提供されないことを保証する必要がある。エンドユーザーが通知された要件に従わない場合、特に不衛生であると判断した場合や販売される飲食物に適さないと判断した場合、経済事業者は容器への再充填を拒否する権利を有し、その使用による衛生や食品安全上の問題について責任を負わない。また、2030年1月1日以降、売場面積が400m²を超える最終流通業者は、売場面積の10%を再充填場所に充てるよう努める必要がある。(第25条)
目次
第1章 一般規定
第1条 主題
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 自由な移動
第2章 持続性要件
第5条 包装に含まれる物質に関する要件
第6条 リサイクル可能な包装
第7条 プラスチック包装中の最低リサイクル材料含有
第7a条 プラスチック包装におけるバイオベース原料
第8条 堆肥化可能な包装
第9条 包装の最小化
第10条 再使用可能な包装
第3章 ラベル表示、マーキングおよび情報要件
第11条 包装のラベル表示
第12条 包装廃棄物収集用の廃棄物容器のラベル表示
第12b条 主張
第4章 第5および7章の義務以外の経済事業者の義務
第13条 製造者の義務
第14条 包装又は包装材料の供給業者の情報義務
第15条 認定代理人の義務
第16条 輸入者の義務
第17条 流通業者の義務
第18条 フルフィルメント・サービスプロバイダーの義務
第19条 製造者の義務が輸入者および流通業者に適用される場合
第20条 経済事業者の特定
第20a条 包装廃棄物管理事業者の情報提供義務
第4a章 第7章の義務以外の経済事業者の義務
第21条 過剰包装に関する義務
第22条 特定の包装フォーマットの使用制限
第23条 再使用可能な包装に関する義務
第24条 再使用のためのシステムに関する義務
第25条 再充填に関する義務
第26条 再使用目標
第27条 再使用目標の達成度の算定に関する規定
第28条 所管当局への再使用目標の報告
第28a条 持ち帰りセクターに対する再充填義務
第28b条 持ち帰りセクターへの再使用オファー
第5章 プラスチック製キャリーバッグ
第29条 プラスチック製キャリーバッグ
第6章 包装の適合性
第30条 試験、測定及び計算方法
第31条 適合性の推定
第32条 共通仕様
第33条 適合性評価手順
第34条 EU適合宣言
第7章 包装及び包装廃棄物の管理
第1節 一般規定
第35条 所管当局
第36条 早期警戒報告
第37条 廃棄物管理計画および廃棄物防止プログラム
第2節 廃棄物防止
第38条 包装廃棄物の防止
第3節 生産者登録簿と拡大生産者責任
第39条 生産者の登録簿
第40条 拡大生産者責任
第41条 生産者責任組織
第42条 拡大生産者責任の履行に関する認可
第4節 返却、回収、デポジット返還システム
第43条 返却および回収システム
第43a条 義務的な回収
第44条 デポジットおよび返却システム
第5節 再使用と再充填
第45条 再使用と再充填
第6節 リサイクル目標とリサイクル推進
第46条 リサイクル目標とリサイクル推進
第47条 リサイクル目標の達成度の算定に関する規定
第48条 再使用を含むリサイクル目標の達成度の算定に関する規定
第7節 情報と報告
第49条 包装廃棄物の防止および管理に関する情報
第50条 欧州委員会への報告
第51条 包装データベース
第8章 セーフガード手続き
第52条 国家レベルでリスクを呈する包装に対処するための手順
第53条 EUセーフガード手続き
第54条 リスクを呈する適合包装
第55条 EU市場に参入する包装の管理
第56条 形式的な不遵守事項
第9章 グリーン公共調達
第57条 グリーン公共調達
第10章 委任権限および専門委員会手続き
第58条 委任の行使
第59条 専門委員会手続き
第11章 改正
第60条 規則(EU) 2019/1020の改正
第61条 指令(EU) 2019/904の改正
第12章 最終規定
第62条 罰則
第63条 評価
第64条 廃止および移行規定
第65条 発効および適用
附属書1 第3条(1)の包装の定義の範囲に含まれる物品の例示的リスト
附属書2 包装のリサイクル性評価のための区分とパラメータ
附属書3 堆肥化可能な包装
附属書4 最小化評価の梱包方法
Part 1
Part 2
附属書5 包装フォーマットの使用に関する制限
附属書6 再使用及び再充填場所のためのシステムに固有の要件
Part 1
Part 2
Part 3
附属書7 適合性評価手順
モジュールA 内部生産管理
附属書8 EU適合宣言 No*…
附属書9 第39条に言及される登録及び登録簿への報告に関する情報
Part 1
A. 登録時に提出する情報
Part 2 報告のために提出する情報
B. 第39条(7)に基づく報告のために提出される情報
C. 第39条(7a)に基づく報告のために提出される情報
D. 第39条(7c)に基づく報告のために提出される情報
附属書10 デポジットおよび返却システムに関する最低要件
附属書11 第46条(2)(d)に従って提出される実施計画
附属書12 加盟国が包装および包装廃棄物に関するデータベースに含めるデータ
基礎情報
>>和訳/解説書の案内ページはこちら<<
作成者
■ 株式会社先読
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム
無料メールマガジンの申込み|
希望の情報分野を選択可能
登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。
「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。
★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
(不定期)
メルマガ|全般(全分野)
当社で扱う情報分野全般の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。
メルマガ|化学物質
化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。
メルマガ|環境
環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。
メルマガ|先端技術
先端技術分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社で言う先端技術分野とは、人工知能(AI)、仮想・拡張現実(VR・AR)、自動運転、エコカー、デジタルトランスフォーメーション(DX)などをいいます。
メルマガ|新領域
新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。