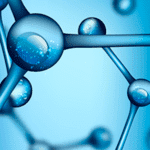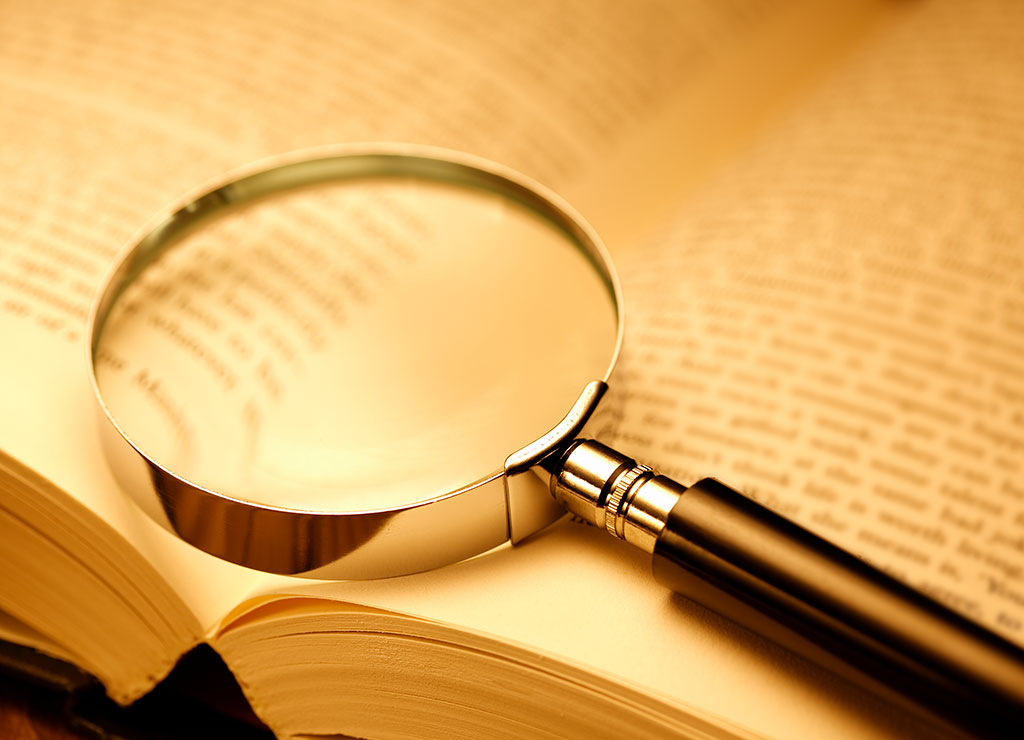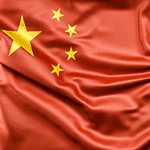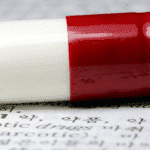| 法令の情報時期:2022年11月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

目的は、企業安全生産費の管理を強化し、安全生産投資への長期的な体制を確立し、企業、従業員及び社会公共利益を守ることである。
概要

本弁法は、企業安全生産費の管理を強化し、安全生産投資への長期的な体制を確立し、企業、従業員及び社会公共利益を守るため、「中華人民共和国安全生産法」などの関連法律法規、及び「中国共産党中央委員会 国務院 安全生産分野の改革発展に関する意見」「国務院 安全生産のさらなる強化に関する決定」(国発〔2004〕2号)、「国務院 企業安全生産のさらなる強化に関する通知」(国発〔2010〕23号)などに従い制定された。
規定は第69条で構成され、企業が安全生産費を計上し、安全生産条件の改善に向けた投資を確保するための管理基準と使用範囲について規定している。
石炭生産、非炭鉱採掘、石油天然ガス開発などの各分野ごとに、具体的な費用計上基準や資金の使用先を定めており、安全防護設備の維持管理、緊急避難施設の整備、主要リスクの評価・是正、従業員教育や報奨制度などを網羅している。
注目定義
■ 「企業安全生産費」(企业安全生产)
| 「企業安全生産費」とは、企業が規定標準に基づいて計上し、コスト(費用)に算入する企業またはプロジェクトの安全生産条件を改善、向上させるため、特別に使用される資金のことをいう。(第3条) |
■ 「石炭生産」(煤炭生产)
| 「石炭生産」とは、石炭資源採掘事業に関連する活動をいう。共同試運転が承認された基礎建設炭鉱は、本節の規定に従って企業安全生産費を計上、使用しなければならない。(第6条) |
■ 「非炭鉱採掘」(非煤矿山开采)
| 「非炭鉱採掘」とは、金属鉱石、非金属鉱石及びその他の鉱物資源の探査と生産、選鉱、閉山と尾鉱滓池の運営、再度採掘、閉鎖及びその他の関連活動石炭資源採掘事業に関連する活動をいう。(第9条) |
■ 「石油、天然ガス(シェールオイル及びシェールガスを含む)の開発」(石油天然气(包括页岩油、页岩气)开采)
| 「石油、天然ガス(シェールオイル及びシェールガスを含む)の開発」とは、陸上石油(ガス)採掘、海上石油(ガス)採掘、生産井掘削、物理探査、オイルロギング、坑内作業、オイル工事建設及びオフショアオイルエンジニアリング活動などをいう。炭層メタン(地上採掘)企業は、陸上の石油(ガス)開発標準に従って計上されるものとする。(第13条) |
■ 「建設事業」(建设工程))
| 「建設事業」とは、新設、拡張、改造工事を含み、土木工事、建築工事、パイプライン及び設備設置と内装工事をいう。(第16条) |
■ 「危険物の製造、貯蔵」(危险品生产与储存)
| 「危険物の製造、貯蔵」とは、許可を取得し、国家標準「危険貨物品名録」(GB12268)「危険化学品目録」に記載されている危険物、及び国家関連規定に記載されている危険物の直接生産と貯蔵活動をいう。(第20条) |
■ 「輸送事業」(交通运输)
| 「輸送事業」には、道路輸送、鉄道輸送、都市鉄道輸送、水面輸送、パイプライン輸送が含まれる。道路輸送とは、「中華人民共和国道路輸送条例」に規定される道路旅客輸送及び道路貨物輸送を指す。鉄道輸送とは、「中華人民共和国鉄道法」に規定される鉄道旅客輸送及び貨物輸送を指す。都市鉄道運送とは、地下鉄、ライトレール、モノレール、路面電車、リニアモーターカー、自動誘導軌道、都市高速鉄道システムなどを含み、規定に従って建設が承認され、専用軌道での都市公共旅客輸送システムを指す。水面輸送とは、船舶を使用し、商用旅客輸送及び貨物輸送、及び港での積み降ろし、移送、保管を指す。パイプライン輸送とは、パイプラインを使用し、液体及び気体物資の輸送を指す。(第23条) |
■ 「冶金」(冶金)
| 「冶金」とは、黒金属や有色金属の製錬や圧延加工などの生産活動をいう。(第26条) |
■ 「機械製造」(机械制造)
| 「機械製造」とは、各種の動力機械、鉱山機械、輸送機械、農業機械、計器、特殊設備、大型中型船舶、海洋工事設備、石油精製設備、建設施工機械及びその他の機械設備の製造活動をいう。「国民経済産業分類及びコード」(GB/T4754)により、本弁法での機械製造企業には、一般設備製造業、特殊設備製造業、自動車製造業、鉄道、船舶、航空及びその他の輸送設備製造業(第十一節の民間航空設備製造業を除く)、電気機械及び機材製造業、コンピュータ、通信及び他の電子設備製造業、計器製造業、金属製品、機械及び設備修理業等の8種類の企業を含む。(第29条) |
■ 「民用爆発物」(民用爆炸物品)
| 「民用爆発物」とは、「民用爆発物一覧表」に掲げるものをいう。(第35条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

企業の安全生産費の管理は、以下の原則に基づいて行われる。まず、資金調達は法律に従い、企業は安全生産に必要な費用を全額計上する責任を負う。
支出は実際の生産経営に応じたものであり、厳格に管理され、横領や流用は許されない。また、企業は内部外部の監督体制を整え、情報開示と社会責任の報告を行うことが求められる。
安全生産費は、安全設備の購入や保守、安全情報システムの整備、安全防護用品や応急救援機材の費用、緊急救助チームの構築、教育訓練、保険費用、検査やコンサルなど、安全生産に直接関連する支出に使用される。(第4条、第5条)

石炭生産企業は、毎月の原炭生産量に基づき、安全生産費を計上しなければならない。計上基準は鉱山の種類によって異なり、例えば、ガス突出や山はね地下鉱山では1トン当たり50元、高ガス地下鉱山では1トン当たり30元などである。これらの基準は「炭鉱安全規程」や関連規定に従う。
安全生産費は、ガス突出防止対策や山はね防止措置、換気やガス制御などの設備改造、緊急避難設備の整備、危険源のモニタリング、作業員の安全保護用品、教育訓練、新技術の導入など、炭鉱の安全性を高めるためのさまざまな支出に充てられる。(第7条、第8条)

非炭鉱採掘企業は、毎月の原鉱生産量に基づき、安全生産費を計上する必要がある。金属鉱山、核物質鉱山、非金属鉱山、小規模露天採石場など、鉱山の種類に応じて異なる基準が適用される。
尾鉱石や低品位鉱石はこの計算に含まれない。
また、地質調査ユニットはプロジェクト費用の2%を安全生産費として計上する。これらの安全生産費は、防護設備の補完やリスク対策、モニタリングシステムの構築、緊急避難設備、危険源の管理、作業員の安全用品、教育訓練、新技術の導入、安全検査、尾鉱滓池の管理、安全保険など、鉱山の安全確保に関わるさまざまな支出に使用される。(第10条、第12条)

陸上および海上の石油・ガス生産企業は、毎月の生産量に基づき、安全生産費を計上する必要がある。
原油は1トンあたり20元、天然ガスは1,000立方メートルあたり7.5元とし、さらに関連企業はプロジェクトの直接コストや工事費の2%を基準に安全生産費を計上する義務がある。
また、石油・天然ガス開発企業の安全生産費は、安全防護施設の補完や改造、事故脱出設備、緊急救助体制の構築、主要な危険源のモニタリング、安全リスクの管理、作業員の安全保護用品、新技術の導入、設備の検査、非常用設備、安全保険などの支出に充てられるべきである。(第14条、第15条)

建設事業の施工企業は、工事費用に基づき、工事進度に応じて月末に企業安全生産費を計上しなければならない。
計上基準は鉱山工事で3.5%、鉄道や住宅建設工事などで3%、水力発電工事などで2.5%などである。
入札見積書には安全生産費を個別に算入し、入札時に削除してはならない。
企業安全生産費は、安全防護施設の補完や改造、事故脱出設備、緊急救助体制の構築、主要な危険源のモニタリング、安全リスク管理、作業員の安全保護用品、新技術の導入、設備の検査、安全保険などに使われるべきである。(第17条、第19条)

危険物製造貯蔵企業は、前年度の営業収入に基づき、超額逓減方式で当年度の安全生産費を計上し、毎月平均して計上する必要がある。
例えば、営業収入が1,000万元以下の場合は4.5%、1,000万元を超え1億元までの部分は2.25%、1億元を超え10億元までの部分は0.55%、10億元を超える部分は0.2%で計算される。
計上された安全生産費は、安全防護施設の改造や維持、危険源のモニタリング、緊急救援体制の構築、安全評価、従業員の保護用品の提供、安全教育や訓練、新技術の導入、設備の検査、安全保険などに充てられるべきである。(第21条、第22条)

輸送事業者は、前年度の営業収入に基づき、一般貨物事業で1%、旅客輸送や危険物輸送事業では1.5%の割合で安全生産費を計上し、月ごとに平均して計上する必要がある。
この安全生産費は、安全防護設備の補完やメンテナンス、輸送施設や荷役工具の安全検査、ドライブレコーダーやナビゲーションシステムの導入、防災モニタリング設備の整備、緊急救援体制の構築、安全リスクの評価やモニタリング、安全保護用品の提供、安全教育や訓練、新技術の導入、設備検査、責任保険などの支出に充てられる。(第24条、第25条)

冶金企業は、前年度の営業収入に基づいて、当年度の安全生産費を超額逓減方式で計上し、月ごとに平均して計上しなければならない。
具体的には、収入が1,000万元以下の場合は3%、1億元以下の部分は1.5%、10億元以下は0.5%、50億元以下は0.2%、100億元以下は0.1%、それ以上は0.05%で計上する。
この安全生産費は、安全防護施設の補完や維持、危険源のモニタリング、緊急救援体制の構築、安全検査や教育、保護用品の提供、新技術の導入、設備検査、責任保険などに使用される。(第27条、第28条)

機械製造企業は、前年度の営業収入に基づき、超額逓減方式で安全生産費を決定し、月ごとの平均を計上する必要がある。
具体的には、収入が1,000万元以下の場合は2.35%、1億元以下の部分は1.25%、10億元以下は0.25%、50億元以下は0.1%、それ以上は0.05%で計上する。
この安全生産費は、安全防護施設の補完や維持、危険源のモニタリング、緊急救援体制の構築、安全検査や教育、保護用品の提供、新技術の導入、設備検査、責任保険などに使用される。(第30条、第31条)

花火爆竹製造企業は、前年度の営業収入に応じて、当年度の安全生産費を超額逓減方式で決定し、月ごとの平均を計上しなければならない。
具体的には、営業収入が1,000万元以下の場合は4%、1,000万元を超え2,000万元までの部分は3%、2,000万元を超える部分は2.5%で計上する。
この安全生産費は、主に安全防護施設の補完や改造、爆発防止設備の設置、緊急救援器材の設置と保守、危険源の検出とモニタリング、リスク管理、安全教育や訓練、新技術の導入、設備の検査や校正、責任保険などに充てられる。(第33条、第34条)

民用爆発物生産企業は、前年度の営業収入に基づき、当年度の安全生産費を超額逓減方式で決定し、月ごとの平均を計上する必要がある。
具体的には、前年度の営業収入が1,000万元以下の場合は4%、1,000万元を超え1億元までの部分は2%、1億元を超え10億元までの部分は0.5%、10億元を超える部分は0.2%で計上する。
この安全生産費は、安全防護施設の補完や改造、現場のモニタリング、換気、温度調整、防火・防爆設備の設置、緊急救援器材の保守とメンテナンス、緊急対応計画の策定、安全リスクの管理、情報化システムの運用、技術の普及と適用、設備の検査、責任保険などに充てられる。(第36条、第37条)

武器装備研究開発、製造及び試験企業は、前年度の営業収入に基づき、当年度の安全生産費を超額逓減方式で決定し、月ごとの平均を計上する必要がある。
この安全生産費は、安全防護施設の設置や改造、緊急救援器材の保守、主要危険源の検出やリスク管理、高度な技術や設備の安全性評価、社員の訓練、核施設の漏洩防止、軍用化学品や放射性物質の安全対策、大型武器の製造試運転の特殊作業、軍用電子部品の特別保護などに充てられる。(第39条、第41条)

発電、電力供給事業者は、前年の営業収入に基づいて当年度の安全生産費を超額逓減方式で決定し、月ごとに計上する。発電事業者は収入に応じて3%から0.2%、電力供給事業者は0.5%から0.2%の割合で計上する。
安全生産費は、安全防護設備の設置・改造、緊急救援器材の整備、危険源の管理、情報化・セキュリティ、教育・訓練、保護用品の提供、技術の普及、検査・校正、安全保険などに使用される。(第43条、第44条)

企業は、内部の安全生産費の管理体制を確立し、計上と使用の手順、責任、権限を明確にする必要がある。また、年間計画を作成し、財務予算に組み入れて資金を確保しなければならない。
計上した安全生産費はコストとして別途会計処理を行い、適切な証明書を取得することが求められる。
従業員の給与や福利厚生費は安全生産費から支払うことはできないが、リスク報告に対する奨励報酬はこの費用から支出する。未使用の安全生産費は翌年に繰り越され、不足があれば年末に追加計上する必要がある。(第45条、第46条、第47条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第二章 企業安全生産費の抽出と使用
第一節 石炭生産企業
第六条
第七条
第八条
第二節 非炭鉱業採掘企業
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第三節 石油・天然ガス開発企業
第十三条
第十四条
第十五条
第四節 建設事業の施工企業
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第五節 危険物製造・貯蔵企業
第二十条
第二十一条
第二十二条
第六節 輸送事業者
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第七節 冶金企業
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第八節 機械製造企業
第二十九条
第三十条
第三十一条
第九節 花火爆竹製造企業
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第十節 民用爆発物製造企業
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第十一節 武器装備研究開発、製造及び試験企業
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第十二節 発電・電力供給事業者
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第三章 企業安全生産費の管理及び監督
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第四章 附則
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 企業安全生産費計上及び使用管理弁法 |
| 公布日 | 2022年11月21日 |
| 所管当局 |
作成者

株式会社先読