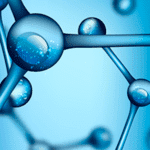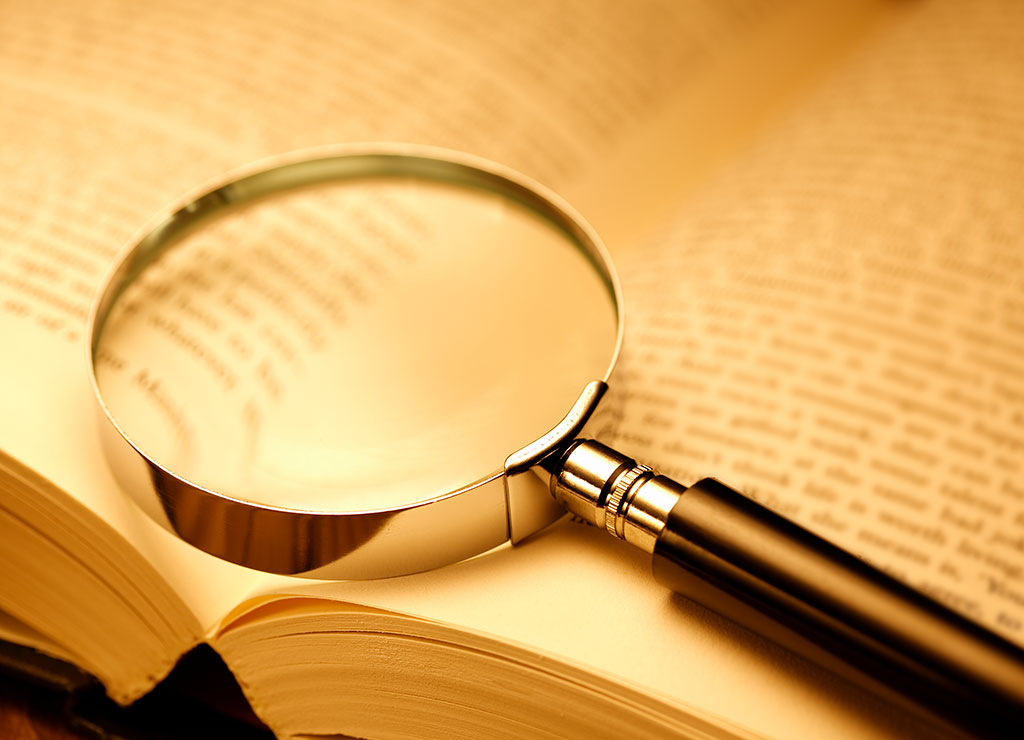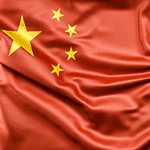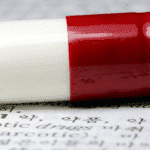| 法令の情報時期:2024年04月 公布版 | ページ作成時期:2024年11月 |
目的

「電動自転車業界規範条件」及び「電動自転車業界規範公告管理弁法」の目的は、電動自転車業界管理を強化し、電動自転車企業の規範化された生産を促進し、電動自転車製品の品質安全を強化し、業界の健全で持続可能な発展を促進すること。
※「規範条件」は原則、それ単体では強制性を持たない指針文書だが、強制力を持つ別の法令で引用されたり、別の法令に組み込まれたりする場合もあるため注意が必要
概要

「電動自転車業界規範条件」は、電動自転車産業の健全かつ持続可能な発展を促進するため、国家関連法律法規及び産業政策に基づき、合理計画、品質保証、革新とアップグレード、安全生産の原則に従い、制定された。
「電動自転車業界規範条件」は計31条で構成され、電動自転車業界の合理計画、品質保証、安全生産、環境保護、労働者および消費者権益保障を促進するため、企業の立地選定、設備要件、製品品質基準、知能製造、グリーン製造、安全管理体制など、多岐にわたる要件を包括的に定めている。
「電動自転車業界規範公告管理弁法」は「電動自転車業界規範条件」の円滑な実施、電動自転車業界の規範公告管理業務を展開し、業界の健全かつ持続可能な発展を促進するため、制定された。
「電動自転車業界規範公告管理弁法」は計17条で構成され、電動自転車業界の規範公告管理業務を円滑に実施し、業界の健全かつ持続可能な発展を促進するための手順を定めている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

《電動自転車業界規範条件》
新規の生産企業やプロジェクト(新設、改築、拡張)は、地域の国土空間計画や土地利用基準を遵守しなければならず、特別保護地域(永久基本農地、生態環境保護レッドライン、自然保護区など)での建設は禁じられる。
また、生態環境要件や環境影響評価基準、国家産業政策を順守し、技術革新や品質向上を図るべきである。
特に、単なる生産能力の拡大を抑制し、ハイエンド化やグリーン化を進めることが求められ、条件が整う地域では産業の団地化や集中化が推奨される。(第1条、第2条、第3条)

企業は、電動自転車全車の生産能力に見合った金属部品の切断、曲げ、溶接、電気泳動設備または生産ラインを備え、溶接自動化率が70%以上に達さなければならない。自動溶接ロボットの使用を推奨する。(第4条)

企業は、電動自転車の生産能力に応じたプラスチックや金属部品の自動噴霧、乾燥生産ラインを完備する必要があり、すべての噴霧および乾燥プロセスは独立した閉鎖作業場内で行われ、排出量は法規制を満たす必要がある。
自社でこれらのラインを設置できない場合は、グループ内の適切な施設で生産しなければならない。
また、企業は電動自転車の生産能力に見合った組立生産ラインも備え、規模生産要件を満たす設備とともに、組立機械や空気圧工具を使用した工程が総工程の70%を占める必要がある。(第5条、第6条)

電動自転車製造企業は、製品の安全性、技術基準、品質管理において厳格な要件を満たす必要がある。
完成車は国家標準「電動自転車安全技術規範」(GB 17761)に適合し、出荷前に強制製品認証を受ける必要があり、速度や出力の改ざん防止技術の導入が求められる。
充電器、リチウムイオン蓄電池、鉛蓄電池、モーター、コントローラー、ワイヤーハーネスなどの部品についても、それぞれ対応する国家標準や業界標準を満たし、認証を受けなければならない。(第8条〜第12条)

企業は知能製造を推進し、デジタル技術を活用して製品設計、運営、販売、アフターサービスにおける効率と管理水準を向上させる必要がある。
設計には3Dソフトウェアを使用し、ERPやMESを導入することが義務付けられており、蓄電池には情報のトレーサビリティを確保するための符号化標識が求められる。
また、企業はグリーン製造標準の改訂やグリーン工場の建設に関与し、環境管理体制を構築して第三者認証を取得することが推奨されている。
さらに、企業は拡大生産者責任制度に基づき、蓄電池の交換やリサイクルサービスを提供し、廃蓄電池の安全な回収とライフサイクル全体での安全モニタリングを強化する必要がある。(第15条、第16条、第17条)

企業は、生産安全法や消防法などの関連法規を遵守し、安全と防火に必要な条件を整える義務がある。
安全生産管理機構を設置し、安全担当者を配置し、全従業員を対象とした安全責任制度を構築し、リスク管理や調査の二重予防体制を整えなければならない。
特定の職務には資格を持つ人員を配置し、安全生産標準化において三級以上の基準を満たすことが求められる。
また、安全事故防止や緊急対応の制度を掲示し、定期的な訓練を実施し、危険作業場所には適切な警告標識を設置する必要がある。(第18条、第19条)

新設や改築プロジェクトでは安全施設を本体プロジェクトと同時に設計・建設し、使用開始までに整備しなければならない。
特にリチウムイオン電池保管倉庫は独立設置とし、火災警報器や消火装置、監視設備を備える義務がある。可燃性粉塵が発生する施設については、粉塵爆発防止規定に従い安全対策を講じなければならない。(第20条)

企業は労働法や労働契約法に基づき、合法的な雇用制度を運用し、従業員の社会保険料を全額負担する義務がある。
また、職業病予防管理法を遵守し、建設プロジェクトでは職業病防止施設を主体プロジェクトと同時に設計、建設、使用開始する「三つの同時」を実施し、職業病危険因子の濃度や強度が基準を満たすよう管理しなければならない。
さらに、労働衛生安全管理体系を構築し、第三者認証を取得することが推奨される。また、企業は操作人員の技能向上を促進し、技能等級認証を実施し、労働者が職位に適した専門技能等級証明書を取得するよう指導することが求められる。(第21条、第22条、第23条)

企業は、製品販売とアフターサービスの体制を整備し、サービス内容が国家標準に適合するようにする必要がある。
また、国際販売チャネルの構築と拡充が推奨される。
製品マニュアルには、リチウムイオン蓄電池の使用やリサイクルリスクに関する情報を明示することが求められる。
さらに、企業は販売店の管理を強化し、電池や速度制限の違法改ざんを防止するよう指導しなければならない。
消費者に対しては、安全で標準化された使用法や保守知識を提供し、リチウムイオン蓄電池の安全使用を促進する措置を講じる必要がある。
電動自転車と共に販売または贈呈されるヘルメットは、関連国家標準を満たすものとする義務がある。(第24条、第25条)

《電動自転車業界規範公告管理弁法》
電動自転車企業が規範公告を申請するには、法律に基づいて登録され、「規範条件」の要件を満たし、国家法規を遵守して重大な違法行為がないことが求められる。
また、過去3年間に重大な生産安全事故がなく、過去2年間に製品の品質上の問題による重大な火災事故が発生していないことが必要である。
さらに、グループ会社の子会社は個別に申請しなければならず、同一企業内で異なる住所にある生産工場については、それぞれ個別に申請する必要がある。(第5条、第6条)

電動自転車企業が規範公告を申請するには、地区の省級主管部門に申請書を提出し、必要な証明書類(営業許可証、CCC認証、検査設備一覧、発明特許、品質管理体制、アフターサービス体制など)を添付する必要がある。
省級主管部門は申請書類を確認し、初期認定で基準を満たしていると判断された場合、申請資料と審査意見を工業情報化部に報告する。
その後、工業情報化部が専門家による資料審査と現地検査を実施して二次審査を行い、要件を満たした企業はウェブサイトで公示される。異議がなければ、公告として正式に公表される。 (第7条、第8条、第9条)
目次
《電動自転車業界規範条件》
1.企業計画
(一)
(二)
(三)
2.工程設備
(四)
(五)
(六)
(七)
3.製品品質及び管理
(八)
(九)
(十)
(十一)
(十二)
(十三)
(十四)
4.知能製造及びグリーン製造
(十五)
(十六)
(十七)
5.安全生産
(十八)
(十九)
(二十)
6.労働者権益保障
(二十一)
(二十二)
(二十三)
7.消費者権益保障
(二十四)
(二十五)
8.監督及び管理
(二十六)
(二十七)
(二十八)
9.附則
(二十九)
(三十)
(三十一)
《電動自転車業界規範公告管理弁法》
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第二章 申請条件
第五条
第六条
第三章 申請、審査及び公告手順
第七条
第八条
第九条
第四章 監督管理
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第五章 附則
第十七条
添付:電動自転車企業規範公告申請書
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 「電動自転車業界規範条件」及び「電動自転車業界規範公告管理弁法」 |
| 公布日 | 2024年04月29日 |
| 所管当局 | 国家市場監督管理総局 |
作成者

株式会社先読