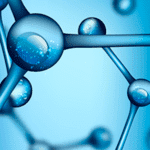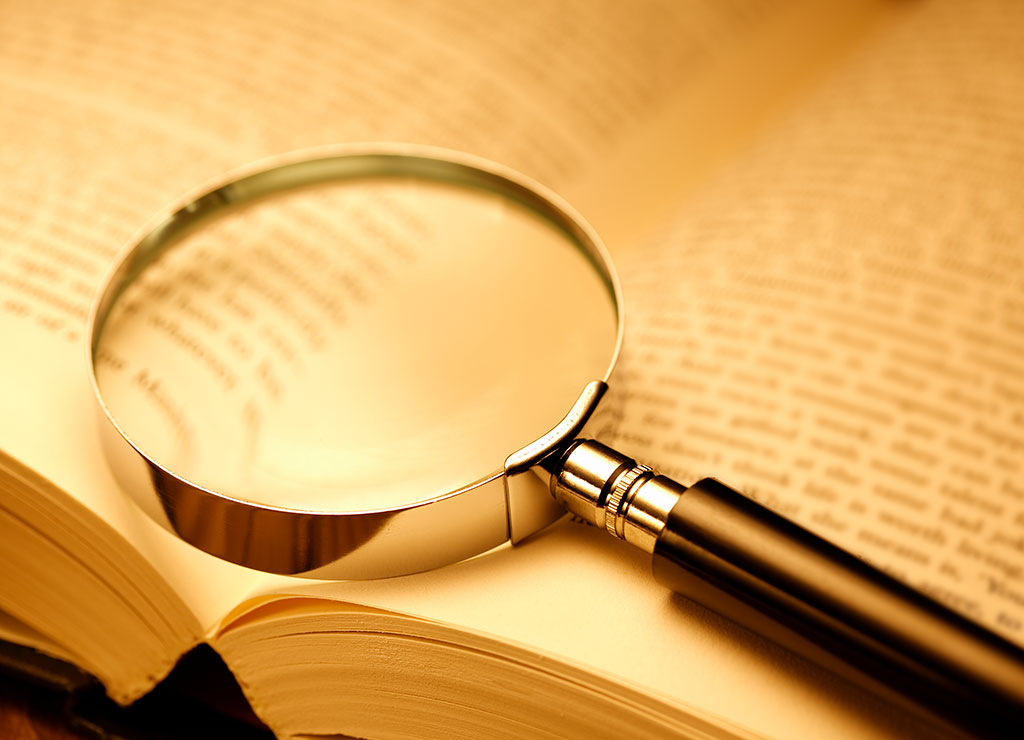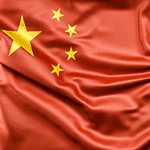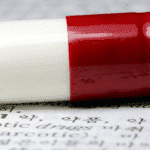| 法令の情報時期:2024年02月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

目的は、国家秘密を保護し、国家の安全と利益を守り、改革開放と社会主義現代化建設事業の円滑な実施を保障すること。
概要

本法は、国家秘密を保護し、国家の安全と利益を守り、改革開放と社会主義現代化建設事業の円滑な実施を保障するため、憲法に基づき制定されている。
本法は計65条で構成され、国家秘密の保護を目的とし、その範囲、等級、管理方法、及び秘密情報の取扱いに関する詳細なルールが定められている。
具体的には、国家秘密の範囲と等級を規定し、秘密保護業務の責任体制、秘密情報の保管・伝達・処理に関する厳格な基準、秘密保護に必要な教育と科学技術の奨励を通じて、国家の安全と利益を確保することを規定している。
本法に違反した場合、国家秘密の不正取得、無断廃棄、インターネットでの不適切な伝送などの行為に対し、違法所得の没収、罰金、警告、業務停止、資質等級の降格や取消しなどの処分が科され、情状が深刻な場合や犯罪を構成する場合には、刑事責任も追及される。
注目定義
■ 「国家秘密」(国家秘密)
| 「国家秘密」とは、国家の安全と利益に関係し、法的手続に基づいて確定し、一定期間内において一定範囲の人員のみが知りえる事項をいう。(第2条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

機関、組織が職能の履行過程において発生又は取得した国家秘密に属さないが、漏洩すると一定の悪影響を及ぼす事項に対して、業務秘密管理弁法を適用し必要な保護措置を講じる。業務秘密管理弁法は別途制定する。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

機関、組織は、秘密保護業務責任制を実施し、法に基づき秘密保護業務機構を設置するか、又は指定された専任者が秘密保護業務を担当し、秘密保護管理制度を完備し、秘密保護防護措置を拡充し、秘密保護宣伝教育を実施し、秘密保護の監督検査を強化しなければならない。(第8条)

機関、組織が秘密保護業務を実施するために必要な経費は、本機関、本組織の年度予算又は年度収支計画に組み入れなければならない。(第11条)

機関、組織の主要責任者及びその指定された人員は国家秘密の確定責任者であり、本機関、本組織の国家秘密の確定、変更及び解除業務を担当する。
機関、組織が本機関、本組織の国家秘密を確定、変更及び解除するには、担当者が具体的な意見を提起し、国家秘密の確定責任者の審査を経て承認しなければならない。(第16条)

機関や組織は上級または他機関が確定した国家秘密に関連する事項を取り扱う際、その秘密等級に基づいて派生的に確定することが求められる。
国家秘密事項が発生した際には、秘密保護事項の範囲に基づいて秘密等級、保護期間、開示範囲を確定し、条件が整えば秘密のポイントも明記することができる。(第18条、第19条)

国家秘密の秘密保護期間は、その事項の性質や特徴に基づき、国家の安全と利益を守るために必要な期間内に限定されるべきである。
期間を確定できない場合は、秘密解除の条件を設定する必要がある。通常、極秘等級は30年、機密等級は20年、秘密等級は10年を超えないが、別途規定がある場合はその限りではない。
機関や組織は業務上の必要に応じて、具体的な保護期間や解除日、解除条件を決定し、業務上公開が必要と判断した場合は、正式な公布時に秘密が解除されたとみなす。
また、国家秘密の開示範囲は最小限に限定され、具体的な人員や機関に制限する。開示範囲外の者が国家秘密を知る必要がある場合は、責任者の承認を得る必要があり、元の確定機関が定めた規定がある場合は、それに従う。(第20条、第21条)

機関や組織は確定された国家秘密を毎年審査し、秘密保護期間が満了した場合は自ら秘密解除を行う必要がある。
保護期間内であっても、秘密保護の範囲調整により国家秘密でなくなった場合や、公開しても国家の安全や利益に影響を与えない場合は、速やかに秘密を解除しなければならない。
秘密保護期間を延長する必要がある場合は、元の保護期間が終了する前に秘密等級、保護期間、開示範囲を再確認しなければならない。
秘密保護期間の事前解除や延長については、元の秘密保護機関やその上級機関が決定する。(第24条)

国家秘密の媒体の作成、送受信、伝送、使用、コピー、保存、保守、廃棄は、国家秘密保護規定に従う必要がある。
極秘等級の国家秘密媒体は、秘密保護基準に適合した施設や設備で保存し、指定された専任者が管理しなければならない。
コピーや写し書きは、元の確定機関や上級機関の承認がなければ行えない。
また、送受信や伝送、外出時の携帯は、指定された人員が責任を持ち、安全措置を講じる必要がある。
国家秘密に関連する設備や製品の研究製造、生産、輸送、使用、保存、保守、廃棄も同様に秘密保護規定に従わなければならない。(第26条、第27条)
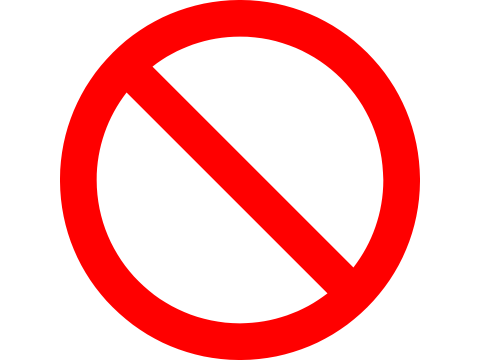
機関や組織は国家秘密媒体の管理を徹底し、不正な取得や保有、売買、転送、無断での廃棄を行ってはならない。
また、秘密保護措置のない郵便や速達での伝達や、無許可での越境配達・託送も禁止されている。
さらに、関連主管部門の承認なしに国家秘密媒体を越境させる行為や、その他の秘密保護規定に違反する行為も行ってはならない。(第28条)

機関や組織は情報システムと情報設備の秘密保護管理を強化し、リスクを迅速に発見して対応するための自主監督管理施設を整備しなければならない。
これに関連して、組織や個人が以下の行為を行うことは禁止されている。具体的には、秘密保護規定に基づかず、適切な保護措置を講じないまま、秘密情報システムや設備をインターネットや公共情報ネットワークに接続すること、これらのネットワーク間で情報交換を行うこと、非秘密情報システムや設備で国家秘密を扱うこと、無断で秘密情報システムのセキュリティ技術や管理プログラムを変更すること、セキュリティ処理をせずに使用を終了した秘密情報設備を寄贈、売却、廃棄すること、または他の用途に転用することなどが含まれる。
さらに、秘密保護に関連する製品や技術設備は、規定と標準に適合していなければならない。(第31条、第32条)

国家秘密に関わるデータの取り扱いやそのセキュリティ監督管理は、国家秘密保護規定に適合する必要がある。
国家秘密保護行政管理部門や地方の秘密保護管理部門は、関連する主管部門と連携し、セキュリティおよび秘密保護の予防・管理メカニズムを構築し、必要な防止措置を講じてデータの集約や関連付けによる秘密漏洩リスクを防止する義務がある。
また、機関や組織は、集約や関連付けによって生じた国家秘密に属するデータに対して、法に基づきセキュリティ管理を強化しなければならない。(第36条)

機関、組織は、極秘等級又は多くの機密等級、秘密等級の国家秘密に関わる機関を秘密保護重要部門と定め、国家秘密媒体を集中的に作成、保存、保管する専門場所を、秘密保護重要場所と定め、国家秘密保護規定及び標準に基づき、必要な技術防護施設、設備を配置、使用しなければならない。(第39条)

秘密に関わる人員は、業務内容に応じて核心的、重要、一般の三つに分類され、管理が行われる。
採用や雇用時には国の規定に基づく審査が必要であり、これらの人員は優れた政治的素質や品性を備え、秘密保護教育を受け、適任な技能を有し、秘密保護承諾書を締結しなければならない。
また、国家秘密保護規定を厳格に守り、秘密保護の責任を負う義務がある。
合法的権益は法律で保護され、秘密保護のために制限を受けた場合は、国の規定に基づき適切な待遇や補償が提供されるべきである。
機関や組織は、秘密に関わる人員の管理制度を確立し、彼らの権利や責任を明確にした上で、継続的な監督検査を行う必要がある。(第43条、第44条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第二章 国家秘密の範囲と秘密等級
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第三章 秘密保護制度
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四章 監督管理
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五章 法的責任
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 国家秘密保護法 |
| 公布日 | 2024年02月27日 |
| 所管当局 |
作成者

株式会社先読