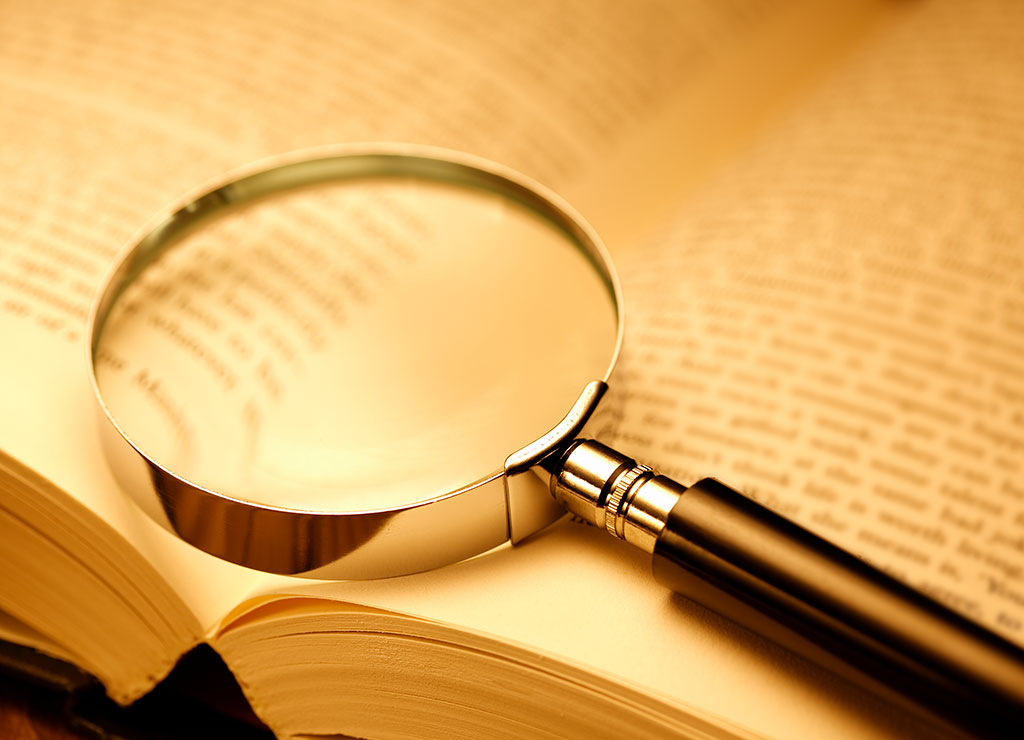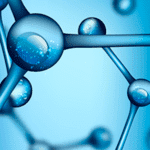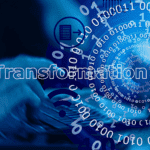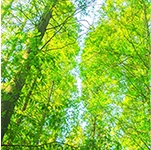| 法令の情報時期:1996年11月 統合版 | ページ作成時期:2025年4月 |
目的

この法令の目的は、労働者の健康および安全、ならびに工場および機械の使用に関連する人々の健康および安全の確保、および労働者の活動に起因する、またはそれに関連する健康および安全上の危険からの労働者以外の者の保護、および労働安全衛生諮問委員会の設置、ならびにこれらに関連する事項を規定することである。
概要

この法令は、労働安全衛生諮問委員会の設置、職場で使用する物品の製造者等の義務、雇用者および被雇用者ならびに職場の安全衛生管理者の役割および義務、およびこれらに関連する事項を規定している。
注目定義
<対象者>
■ 「最高経営責任者」(chief executive officer)
| 「最高経営責任者」とは、国が運営する法人または企業に関して、当該法人または企業の事業の全般的な管理および統制に責任を負う者をいう。 |
■ 「主任検査官」(chief inspector)
| 「主任検査官」とは、第27条に基づき任命され、主任検査官として活動する職員をいう。 |
■ 「被雇用者」(employee)
| 「被雇用者」とは、第1条(2)の規定に従い雇用者に雇用され、雇用者のために働き、報酬を受ける者、または受け取る権利を有する者、または雇用者もしくはその他の者の指示または監督の下で働く者をいう。 |
■ 「雇用者」(employer)
| 「雇用者」とは、第1条(2)の規定に従い、人を雇用し、または人に仕事を提供し、その人に報酬を支払う者、または明示的もしくは黙示的に報酬の支払いを約束する者をいう。ただし、1956年労働関係法 第1条(1)に定義される労働仲介業者は除く。 |
■ 「大臣」(Minister)
| 「大臣」とは、労働大臣をいう。 |
■ 「使用者」(user)
| 「使用者」とは、プラントまたは機械に関して、それを自己の利益のために使用する者、またはその使用に対して管理権を有する者をいう。ただし、当該プラントまたは機械の貸主、および当該プラントまたは機械に関連して雇用されている者は含まれない。 |
<対象施設>
■ 「承認検査機関」(approved inspection authority)
| 「承認検査機関」とは、主任検査官によって承認された検査機関をいう。ただし、特定のサービスに関して主任検査官によって承認された検査機関は、そのサービスに関してのみ承認された検査機関となる。 |
■ 「重大危険施設」(major hazard installation)
| 「重大危険施設」とは、次のいずれかの施設をいう。 (a)規定量を超える物質が永久的または一時的に保管されているか、保管される可能性がある施設 (b)重大事故を引き起こす可能性のある形態および量で物質が製造、加工、使用、取り扱い、または保管されている施設 |
■ 「プラント」(plant)
| 「プラント」とは、備品、器具、機器、装置、道具、器具、およびプラントに関連して何らかの目的で使用されるものすべてを含む設備をいう。 |
■ 「施設」(premises)
| 「施設」とは、建物を含む土地、車両、船舶、列車、航空機をいう。 |
■ 「重大事故」(major incident)
| 「重大事故」とは、プラントや機械の使用、または職場での活動から生じる壊滅的な規模の事故をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法は、以下に関しては適用されない。
(a) 鉱物法(1991年第50号)が別段の定めをする場合を除き、同法において定義される鉱山、鉱区、または施設
(b) 商船法(1951年第57号)第2条 第1項において定義される満載喫水線船舶(満載喫水線免除証明書を有する船舶を含む)、漁船、アザラシ猟船、捕鯨船、または浮きクレーン(これらの船舶、ボートまたはクレーンが共和国のいかなる港内または領海内であるか、または水中または水上にあるかを問わない)
または、上記のような鉱山、鉱区、施設、船舶、ボートまたはクレーンの上または内部にいる人物に関して
※ (b)の施行日は未定とされている。(第1条 第3項)
大臣は、大臣が定める条件および期間に従い、いずれかの雇用者または使用者、もしくはその分類について、一般的にまたは特定の労働者や使用者またはその分類に関して、あるいは特定の事項に関して、本法のいずれかの条項またはすべての条項、あるいは本法に基づいて発行された告示または指示の条項から免除することができる。
上記の免除は以下の方法によって行われる。
(a) 特定の雇用者または使用者を対象とする場合:その者の氏名、免除の範囲、期間および条件が記載された「免除証明書」を発行することにより行う。
(b) 雇用者または使用者のカテゴリー全体を対象とする場合:そのカテゴリーの雇用者または使用者の説明と、免除の範囲、期間および条件を記載した「官報による告示」を行うことにより行う。(詳しくは第40条参照)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
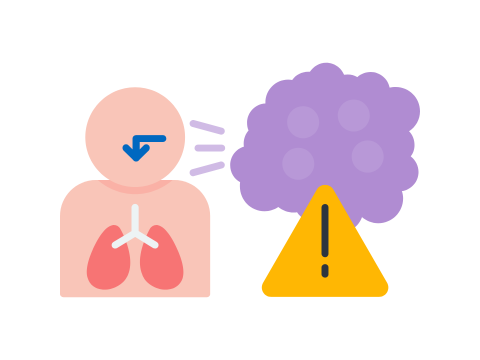
雇用者は、主任検査官が任意の雇用者に対して命じることのできる、従業員の健康および安全の保護に関する方針に関する文書を作成しなければならない。この文書には、当該雇用者の組織構成の説明および、その方針を実施・見直しするための体制に関する記述を含まなければならない。(詳しくは第7条参照)
雇用者は、その業務に従事するすべての従業員に対して、作業中における安全でリスクのない環境を、合理的に可能な範囲で確保しなければならない。
上記の義務を履行するため、雇用者は以下の措置を講じなければならない(可能な限り)。
(a) 作業環境、機械、器具、作業方法の安全性の確保と維持
(b) 労働者が機械や装置を安全に取り扱い、移動、保管、使用、輸送できるようにすること
(c) 安全衛生を確保するための情報提供、指示、訓練、監督
(d) 作業中に発生する可能性のある健康への危険を特定し、リスク評価と対策を講じること
(e) 危険物質や工程に関する情報提供と、従業員への開示
(f) 緊急事態への備え(例:火災、避難等)を含む安全衛生計画の整備
(g) 上記のいずれかに関連する従業員の要望に耳を傾け、協議する手段を設けること(詳しくは第8条参照)

職場で使用する物品を設計、製造、輸入、販売または供給する者は、合理的に実行可能な限りにおいて、その物品が適切に使用された場合に安全であり、かつ健康に対する危険がないこと、およびすべての所定の要件に適合することを保証しなければならない。(第10条)
職場で使用する物品を施設内に設置する者は、合理的に実施可能な限り、建築または設置の方法が、その物品が適切に使用される場合には、危険なものとなることまたは健康に対する危険を生じさせることのないようにしなければならない。(第10条)
職場で使用する物質を製造、輸入、販売または供給する者は、次のことを行わなければならない。
(a)合理的に実行可能な限り、当該物質が適切に使用された場合に安全であり、健康に対する危険性がないことを保証すること。
(b)職場での当該物質の使用について、および当該物質に関連する健康および安全に対する危険性について、ならびに当該物質が適切に使用される場合に安全であり、健康に対する危険性がないことを保証するために必要な条件について、および当該物質に関連する事故が発生した場合に従うべき手順についての情報が入手可能なことを保証するために必要な措置を講じなければならない。(第10条)
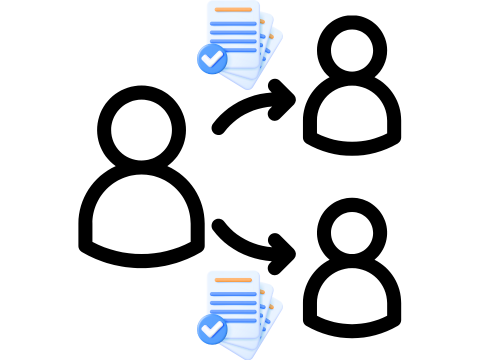
すべての被雇用者は、職場において自分自身および他人の健康と安全に配慮しなければならない。また、雇用者に課された法令上の義務や要件が遵守されるよう協力する責任がある。与えられた正当な命令や安全に関する規則・手順には従う必要があり、安全でない状況に気づいた場合には、速やかに雇用者や安全衛生の代表者に報告しなければならない。(詳しくは第14条参照)
すべての最高経営責任者は、合理的に実行可能な範囲において、その雇用者に本法に基づいて課されている義務が適切に履行されるようにしなければならない。
最高経営責任者は、規定された任務のいずれかを自らの管理下にある者に割り当てることができるが、法的責任は免れず、業務を割り当てられた者は最高経営責任者の指揮命令の下で行動しなければならない。(詳しくは第16条参照)
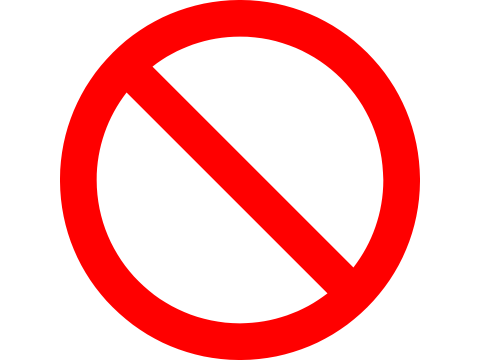
第10条第4項の規定に従い、もし供給された機械器具や物質が、誓約された条件に照らして安全性や健康リスクに関する法的要件を満たしていないと判断された場合は、そのような機械器具や物質の販売、供給または取引は禁止される。(詳しくは第22条参照)
雇用者は、本法に基づいて雇用者に課された義務の履行(安全装備の提供、安全訓練の実施、健康診断等)に要する費用を従業員の報酬から控除してはならない。(詳しくは第23条参照)
雇用者または使用者は、職場で発生したまたは業務に起因して発生した以下のような事故について、所轄の検査官に通報しなければならない。
(a) 人の死亡
(b) 人が負傷または病気となり、病院に入院する必要が生じた場合
(c) 以下のいずれかが発生した場合
・無人の機械の動作による事故
・爆発
・ガスの逸出
・有害物質の放出
・機械、設備または構造物の重大な故障や崩壊(詳しくは第24条参照)
雇用者は、被雇用者が以下の行為を行ったことを理由にして、解雇・処罰・その他の不利益な扱いをしてはならない。
・本法に基づき、検査官に対して情報提供や通報を行った場合
・本法または規則に従って、自らの権利や安全を主張した場合(詳しくは第26条参照)
目次
第1条 用語の定義
第2条 労働安全衛生諮問委員会の設置
第3条 労働安全衛生諮問委員会の役割
第4条 労働安全衛生諮問委員会の構成
第5条 労働安全衛生諮問委員の任期および報酬
第6条 労働安全衛生諮問委員会における専門委員の設置
第7条 労働安全衛生方針
第8条 雇用者の被雇用者に対する一般的義務
第9条 雇用者および自営業者の被雇用者以外の者に対する一般的義務
第10条 職場での使用を目的とした品目および物質に関する製造業者等の一般的義務
第11条 指定業務
第12条 指定業務に関する雇用者の一般的義務
第13条 通知義務
第14条 被雇用者の職場における一般的義務
第15条 妨害、損傷、誤用しない義務
第16条 特定の義務を負う最高経営責任者
第17条 安全衛生管理者
第18条 安全衛生管理者の役割
第19条 安全衛生委員会
第20条 安全衛生委員会の役割
第21条 一般的禁止事項
第22条 特定品目の販売禁止
第23条 特定の控除禁止
第24条 特定事象に関する検査官への報告
第25条 業務上の疾病に関する主任検査官への報告
第26条 報復行為の禁止
第27条 主任検査官の指名および役割
第28条 労働大臣による検査官指名
第29条 検査官の役割
第30条 検査官特別権限
第31条 調査
第32条 正式調査
第33条 合同調査
第34条 主任検査官の調査、取り調べに対する妨害または協力の拒否
第35条 検査官の決定に対する不服申し立て
第36条 情報開示
第37条 被雇用者または受任者の作為または不作為
第38条 犯罪、罰則、および裁判所特別命令
第39条 特定の事実の証明
第40条 免除
第41条 本法は合意の影響を受けない
第42条 職務の委任および譲渡
第43条 規則
第44条 規則への安全衛生基準の組み込み
第45条 通知の送達
第46条 治安判事裁判所の管轄権
第47条 国家の拘束力
第48条 条項の抵触
第49条 法律の廃止
第50条 略称および発効
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 1993年労働安全衛生法 |
| 公布日 | 1993年7月2日 |
| 所管当局 | 雇用・労働省 |
作成者

株式会社先読
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム
無料メールマガジンの申込み|
希望の情報分野を選択可能
登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。
「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。
★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
(不定期)
メルマガ|全般(全分野)
当社で扱う情報分野全般の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。
メルマガ|化学物質
化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。
メルマガ|環境
環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。
メルマガ|先端技術
先端技術分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社で言う先端技術分野とは、人工知能(AI)、仮想・拡張現実(VR・AR)、自動運転、エコカー、デジタルトランスフォーメーション(DX)などをいいます。
メルマガ|新領域
新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。